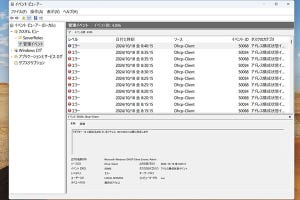バージョン1709以降も続く「Fluent Design」
筆者の個人的感想だが、WindowsというOSは先進的なデザインを採用してこなかった。それでも万人に分かりやすさを示し、ユーザーが好みのデザインを適用できる自由度は評価すべきだと考える。振り返ればMicrosoftはWindows XP時代のLuna、Windows Vista時代のWindows Aero、Windows 8.x時代のModern(Metro)Style Designとその時々の回答を示し、ユーザーは好みに応じた可否を下してきた。Windows 10はWindows 8.xのモダンUIを踏襲しつつも、Windows 7ライクな操作性を目指してきたが、バージョン1709では、「Fluent Design」という新デザインシステムを導入する。
コード名「Project NEON」で開発を続けてきたFluent Designは、フラットデザインから没入可能・空間対応可能なデザインや、マルチデバイス化に伴う多様な入力方法へ対応するため、モダンUIとUWPアプリケーションの親和性を高めると同時に、ユーザーの視認性を高めるデザインだとMicrosoftは説明する。アプリケーション開発者は「Light(光)」「Depth(深度)」「Motion(動き)」「Material(素材)」「Scale(規模)」と5つのコンセプトを元に、ユーザーの目を惹くアクセントを盛り込むことが可能になるという。例えば「『光』は場面に応じて注意喚起やユーザーの興味を惹き、『素材』で現実世界に近い感覚的な爽快感を与える。アニメーションでデータの意味を表現する『動き』を、『深度』で奥行きという物理的環境を演出して、『規模』でオブジェクトの大小と2Dから3Dへの拡張を実現する」と現時点で理解して構わないだろう。
Fluent Designはアプリケーション開発者向けのデザインシステムであり、我々エンドユーザーが具体的にアプローチする必要はない。既に「電卓」など一部のUWPアプリケーションにはFluent Designが組み込まれている。下図は電卓がアクティブ/非アクティブな状態を並べたものだが、非アクティブ時は黒字に白文字のシンプルなデザインながらも、アクティブ時はボタン以外に透過処理が加わり、マウスカーソルがある部分はさらに配色が切り替わる仕組みだ。
「Grooveミュージック」もハンバーガーメニューに透過処理を加え、マウスカーソルをアルバムジャケットに重ねると、ジャケットの配色を計算して、適切な色を用いたハイライト表示を行う仕組みが加わっている。
このように各所へ統一したデザイン効果が加わり、我々はUWPアプリケーションが使いやすくなる。これがエンドユーザー視点のFluent Designだ。ただし、Fluent DesignはWindows 10 バージョン1709で完成するものではない。Microsoftは現時点を"Wave 1"と定め、選択時のハイライト表示を可能にするReveal Highlightや、アクリル風の素材をUWPアプリケーションに加えるAcrylic Material。画面遷移する際に元の画面を残すConnected Animations、遠近感を演出するParallax、アプリケーションの状況に応じてコントロールを変更するConscious Controlsを実装した。なお、Windows InkもFluent Designに合わせて機能的な変更が加わる予定だ。次の"Wave 2"では360度メディア再生の実装を予定している。さらにその後も音声やZ深度レイヤー、立体音響など多くの機能を採用する予定だという。
現時点でFluent Designがどのように進化し、どのようなUX(ユーザー体験)を我々に与えるか断言できないものの、1つ分かっているのはMicrosoftがWindows 10プラットフォーム全体を意識してFluent Designを構築していることだ。例えばMR(複合現実)デバイスの「Microsoft HoloLens」やWindows Mixed Reality対応デバイスによる3D体験は、多くがUWPアプリケーションをベースにしている。現在のScaleは遠近視差などに留まっているが、この概念を拡大させることで、利用方法が大きく異なるPCやMR/VRデバイス上のUWPアプリケーションでも類似したUXを得られるのではないだろうか。