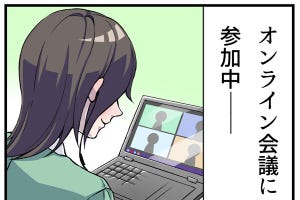Perception-based High Definition Haptic Rendering~物理シミュレーションの重みと堅さを体験
最近の3Dゲームシーンでは「物理シミュレーションの導入」が1つのトレンドになっている。大量の物が互いに衝突したり破壊されたりする様が物理シミュレーションベースで描かれる様は見応えがあるが、そういったコンピュータ内物理シミュレーションを、現実の人間がインタラクトしたりさわったり出来たらきっと楽しいはずだ。
しかし、これには1つ問題がある。
バーチャル世界を生身の人間が感じる仕組みはHAPTICS(触覚学)という学問で研究されているが、この触覚学の世界の制御は毎秒1000回程度の解像力でやらないとリアルな触感としてのダイナミックレンジが表現できない。たとえば触感制御の解像力を毎秒300回程度にしてしまうと柔らかい触感までしか再現できない。HAPTICSの分野では「堅い触感」の再現が難しく、これを実現するためには最低でも毎秒1000回の制御が必要だというのだ。
一方、コンピュータグラフィックス(映像)がスムーズにリアルに見えるためには毎秒60コマ(60fps)の分解能があれば十分とされる。つまり映像と触覚の人間の許容解像力には10倍以上の開きがあるということだ。ならば映像の方も1000fpsでそろえればいいではないかという話になるのだが、実際には、大局的な物理シミュレーションを一般的なスペックのPCで1000fpsで行うことは難しい。
そこで、電気通信大学、知能機械工学科、長谷川研究室が発表したのは、被験者がインタラクトする可能性がある近傍の物理シミュレーションのみを1000fpsで行い、それ以外の部分の物理シミュレーションは通常の60fps程度で行うというLOD(Level of Detail)的な実装だ。これにより物理シミュレーションと触覚制御をともに1000fpsで行うことができるためつじつまを合わせることが出来る。なお、物理シミュレーションはバーチャルリアリティ向けに最適化が施された内製のSpringheadを使用している。
デモそのものはシンプルで分かりやすいものになっていた。
被験者はSPIDAR(SPACE INTERFACE DEVICE ARTIFICIAL REALITY)と呼ばれるデバイスにくくりつけられた金属球を握り、これを三次元的に動かしたり、回転させることで、3Dグラフィックス映像中に登場するカーソル的な3Dモデルを操作することが出来る。
SPIDARは東京工業大学 精密工学研究所 ヒューマンインタフェース研究室で研究開発されたHAPTICSデバイスだ。SPIDARには8個のモーターが仕込まれており、さらにこのモーターにはワイヤーがくくりつけられており、被験者の球体への操作を読み取ると同時に、SPIDAR側で作り出した衝撃を球体へ伝達できる、いわばフォースフィードバック付きの入力デバイスになっている。
ブースでのデモは、被験者は3Dグラフィックスシーン内で分身となるカーソルキャラクタをSPIDARで操作して、シーン内に置かれた他の複数の3Dオブジェクト達と衝突させるなどしてインタラクトできるようになっていた。
カーソルをシーン内の箱にぶつけるとゴチンという衝突の感覚がSPIDARを通して伝わる。シーン内の箱を複数個いっぺんにカーソルで押そうとすると、一個よりも二個、二個よりも三個動かす方が思い手応えになる。カーソルの上に箱を落とすと、カーソルにあたるたびにSPIDARにした向きの反動が伝わり、衝突の衝撃もリアル。シーン内のオブジェクトには材質としての情報も設定されているので、堅いものにカーソルを衝突させたときと、普通の柔らかさの物を衝突させたときでは明らかに手応えが異なっている。これもおもしろい。
なお、被験者が操作する球と、画面内の対象物が衝突したときの被験者へのフィードバックは、その対象物の堅さに応じた振動を返すことで表現されている。
物を触ったときの感触の波形は、物の堅さによって違うことが知られており、堅い物は初期の振幅が大きく急速に減衰する波形になるが、柔らかい物になると初期振幅はあまり大きくない変わりに周波数が低く減衰が遅い。堅い波形を描くためには高い周波数の振動を再現する必要があるのはこういう特性があるからなのだ。
こうした画面内の3Dグラフィックスとの双方向インタラクティビティの研究は、医療分野の訓練、機器の遠隔操作、設計支援などへの実用化、応用化を目指し研究が進められている。