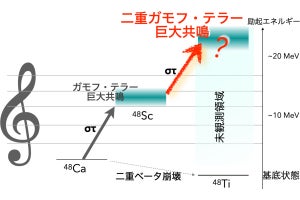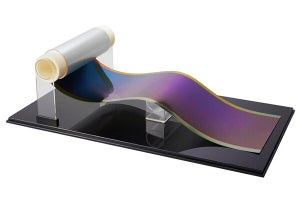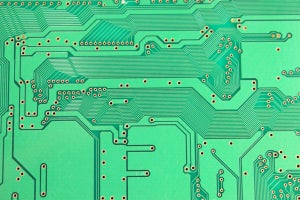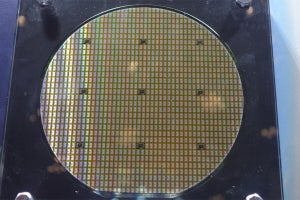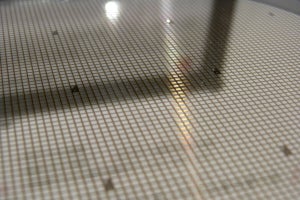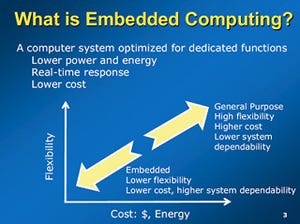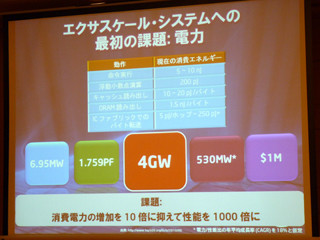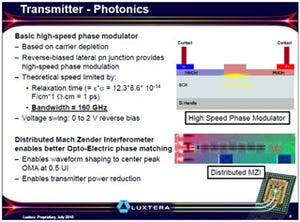この発表に続いて、IntelのEfi Rotem氏がSandy Bridgeの電力制御にフォーカスした発表を行った。Rotem氏はSandy Bridge power architectという肩書である。
Sandy Bridgeでは各部の動作回数を数える100個のカウンタを持ち、それぞれの動作にともなう消費電力の重みを掛けて、全体を加算することにより消費電力を計算するデジタルパワーメータを装備している。また、リーク電流などのスタティックな消費電力は電源と温度の関数であり、これも計算して電力に加算している。Sandy Bridgeでは、このデジタル電力計の情報を入力として、各種のアルゴリズムを用いて使い勝手の良さを保ちながら電力を減らすという制御を行っている。
Sandy Bridgeでは、CPUの仕様に書かれているクロック周波数はP1で、この周波数では連続して動作できることが保証されている。これに対してP0というより高速のクロックで動作させる状態が可能であり、このP1以上、P0以下の領域をターボ状態という。そして、CPUのビジー状態に対応してP2、3…という省電力のクロック低減状態があり、アイドルの場合はさらに低いクロックのT状態が存在する。
例えば、Core i7-2920XMという製品では、CPUクロックのP1は2.5GHzであるが、P0では3.5GHzまでクロックを上げられる。また、この製品のグラフィックス部はP1では650MHzクロックであるが、P0では2倍の1.3GHzまで高速化できるようになっている。ただし、このP0状態は消費電力が大きいので長時間動作させることはできない。
そこで、パッケージの温度の低い状態ではクロックをP0に引き上げて最大に高速化し、温度が上昇するにしたがって階段状に消費電力がTDPとなるP1クロックまで引き下げるというのがターボブースト2.0テクノロジである。パッケージが熱くなるまでには30~60秒の余裕があり、PCとして使う場合は、大部分の処理はこの時間内に終わってしまうので実質P0で動作させることができるという。
また、Sandy BridgeではメモリコントローラがCPUチップに内蔵されており、この中にDDRメモリのリード、ライト回数をカウントし消費電力を計算するメモリ用の電力計が装備されている。この機能を使い、メモリの過熱を防ぐためメモリのアクセス回数を制限したり、メモリの消費電力減らしたりする使い方をするようになっているという。