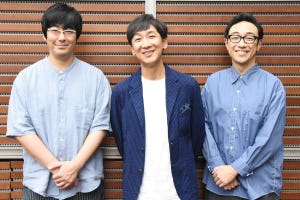注目を集めるテレビ番組のディレクター、プロデューサー、放送作家、脚本家たちを、プロフェッショナルとしての尊敬の念を込めて“テレビ屋”と呼び、作り手の素顔を通して、番組の面白さを探っていく連載インタビュー「テレビ屋の声」。今回の“テレビ屋”は、バラティ番組の構成作家から、舞台やドラマの脚本なども手がけるオークラ氏だ。
幅広いジャンルで活躍する中で、テレビというメディアにどのような意識で臨んでいるのか。そこで自身がやりたいこととは――。
-
オークラ
1973年生まれ、群馬県出身。97年にプロダクション人力舎に入って芸人として活動し、その後放送作家に転向。バナナマン、東京03の単独公演の初期から現在まで関わり続け、『トリビアの泉』『はねるのトびら』『そんなバカなマン』(フジテレビ)などを担当。現在は『ゴッドタン』(テレビ東京)、『バナナサンド』『週刊さんまとマツコ』(TBSテレビ)、『バチくるオードリー』(フジテレビ)、『午前0時の森』(日本テレビ)、『バナナマンのバナナムーンGOLD』(TBSラジオ)などを担当する。近年は日曜劇場『ドラゴン桜2』(TBSテレビ)の脚本のほか、乃木坂46のカップスターWeb CMの脚本監督なども手がけ、21年12月に著書『自意識とコメディの日々』を出版した。
■「舞台だと面白いのに、テレビコントだと面白くならない」
――当連載に前回登場したディレクターの椎葉宏治さんが、オークラさんについて、「今はバラエティではもちろんですけど、ドラマとかもやってるのがカッコいいですし、天才やなと思います。あと、僕はオークラさんとの“小競り合い”が好きです」とおっしゃっていました。
椎葉さんとは『バナナ炎』(TOKYO MXほか)というバナナマンの番組で、演出と構成作家という関係で知り合ったんですけど、小競り合いは設楽(統)さんが仕掛けるんです(笑)。椎葉さんの性格の悪い部分を煽って、僕が怒るっていうやり取りで。まあ、実際は性格悪くないんですけどね(笑)
――今回は「テレビ屋の声」という連載なので、テレビの構成作家としての側面を中心にお伺いしたいと思います。
あまり構成作家という自覚はないんですけどね(笑)
――初めて関わったテレビ番組は、マッコイ斉藤さんが手がけた『SURE×2ガレッジセール』(TBS)だそうですね。
そうです。それまでテレビに作家がいるなんてことすら、あまり意識していなかったくらいなんですけど、元々僕は芸人で、舞台のコントが好きだったんです。それでコント作家になって、当時は三谷幸喜さんとかが注目されるようになった時期でした。僕はシティボーイズにハマっていたんで、シティボーイズの作家をやっている三木聡さんが好きで、三木さんも構成作家をやっているということを知って、興味を持ち始めて。その頃、たまたまおぎやはぎと知り合って、彼らがマッコイさんの知り合いで紹介してもらいました。
――ライブの作家からテレビの世界に来てカルチャーショックを受けたことはありましたか?
ありましたね。テレビバラエティも好きでしたけど、自分がものを作る目線では見てなかったし、ダウンタウンの影響もあるから、カンペを出してそれを言ってもらうときに、言葉一つにしても食ったことを考えようとするところがあったんです。でも、それはあんまりウケないんですよね。そしたらマッコイさんがカンペを取り上げて、一言「バカ」って(笑)。シンプルに分かりやすく、誰にでも伝わるものを作んなきゃダメなんだなって感じた記憶はありますね。
――『ウラ日テレ』(日本テレビ)という番組でやりたかったコント番組を早々に担当されていますね。
日テレが若手ディレクターを育成するというので、ネットで動画配信が始まったくらいの段階で、動画配信をやって視聴者投票してもらうみたいな番組だったんです。ディレクターが自分で見つけてきた芸人と日テレの番組をパロディにしたコントを作るっていう企画で、バナナマンとかラーメンズ、おぎやはぎとかも出演して、僕も作家として呼ばれました。だけど、作るコント作るコント、全然面白くならないんですよ(笑)。「なんで舞台だと面白いのに、テレビコントだと面白くならないんだろう」ってすごく悩みましたね。
テレビコントって、見方というか、視線をカメラワークによって制限されちゃうじゃないですか。この人がセリフを言ったときにこの人の顔を映して、次のセリフを言った人の顔を映して、みたいな。だから、誰の感情で見れば良いのかが、意外と難しいんだっていうことに気づきました。その後、フジテレビの『はねるのトびら』に参加するんですけど、そこでテレビの見せ方を学んだ感じがしますね。
■「誰の感情で動いているのか」が分かるのが成立する企画
――『はねるのトびら』には、最初はハマらなかったとおっしゃっていましたね。
ハマらなかったですね。今思えばですけど、あの時代ってテレビでお笑いをやっている人がみんなゴリゴリというか、イケイケこそが笑いみたいな考え方があったと思うんですよね。異常に体育会系の空気というか。別に悪い人たちでは決してないんですけど、後輩とかの笑いをスカすような文化があったというか。
――とはいえ、番組開始から1カ月ほどで「ナレーション」というオークラさんが書いてシリーズ化したコントも始まってます。
「ナレーション」のときはまだ良かったんですよ。実はその後なんです。僕は考えすぎちゃうところがあるんで、自分の中の正解が出ないとドツボにハマっちゃうんです。そこから自分の中で作り方とかルールが分かると抜け出せるんですけど、1年間くらいは苦労しました。
――オークラさんの著書『自意識とコメディの日々』では、『はねるのトびら』を通して、「何が成立して何が成立しない企画なのかが分かった」といったことを書かれていましたが、具体的にはどのような部分なんですか?
誰の感情で動いているのか、というのが分かるものが成立する企画だと思います。ただ面白い現象を見せるためだけの企画っていうのは、演者さんも見ている方も感情が乗りにくいから成立しない。この人にこういう気持ちがあるから企画がスタートして、目標に向かっていく。例えば、嫌いなものを食べる姿が面白いとしても、どうしてそれを食べるんだという理由がないといけない。そういう感情のラインというか、筋道がないと企画が成立しないんじゃないかと思いますね。
――その後、『トリビアの泉』(フジテレビ)に参加されます。笑いの要素がありながら情報性も強い番組ですが、それまでとは違いましたか?
フジテレビで『世界で一番くだらない番組』という三木さんや遠藤達也さんがやっていた番組があったんですけど、ものすごいくだらないVTRを作っている番組で僕は好きだったんです。『トリビアの泉』を企画してチーフ作家だった酒井健作さんは若手の頃、三木さんの下でやっていた方で、三木さんの映像ネタが好きなんです。それでお互いに話していて、酒井さんが「雑学を教える番組をやるんだけど、雑学の実証の仕方で、そういうくだらないVTRを作りたい」って言って始まったのが『トリビアの泉』だったんです。
だから、もちろん雑学も調べたりはしましたけど、情報をやっているというよりは、ネタを作っている感覚でしたね。酒井さんもまだ30歳くらいで、僕も29くらいだったんで、今考えると相当若い奴らが集まってやってました。酒井さんには、「何が今、世の中で興味を持たれていて、それにどうやって自分の持っているくだらないものを足して見せていくんだ」っていうのを教わりましたね。
――その頃はもう作家業だけで生活できていたんですか?
『トリビア』がゴールデンに行ったあたりで食えるようになったのかな。その少し前に月20~30万もらえるようになって、当時家賃5万の家に住んでたんですけど、信じられないくらい金持ちになった気分だったんですよ(笑)。それで気を良くして15万くらいのところに引っ越したらお金が全然足りなくなって、びっくりしましたね(笑)