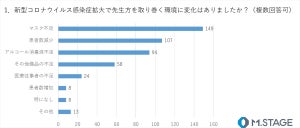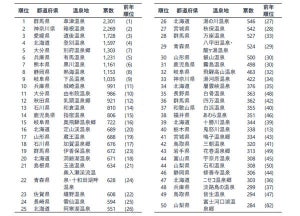第3の点は、約100年前のスペイン風邪の教訓です。スペイン風邪についてはこれまで何度か取り上げてきましたが、実は日本では第2波が深刻でした。
日本では大正7年(1918年)9月頃から流行が始まり、翌8年(1919年)春頃まで続きました。この間の患者数は約2,117万人、当時の人口の約37%にも及び、死者は約25万7,000人に達しました。
このときの流行では、現在の東京駅や日本銀行本店旧舘を設計した建築家の辰野金吾や、演出家・文芸家の島村抱月などの有名人も亡くなり、島村抱月の愛人だった女優の松井須磨子が後追い自殺を遂げるという悲劇も起こりました。ようやくこの年の夏にいったん収束したかに見えたのですが、秋以降になって第2波が日本を襲ったのです。第2波は翌年の大正9年(1920年)春頃まで続き、患者数241万人、死者12万8,000人を数えました。
患者数は第1波の10分の1近くに減ったようにみえますが、それでも大変な人数であり、何よりも衝撃的なのは死者数が第1波の約半分に達したことです。その結果、致死率(患者数に対する死者数の割合)は第1波の1.22%から第2波は5.29%へと跳ね上がりました。月別に見ると大正9年(1920年)の3月と4月は10%を超えています(内務省衛生局編『流行性感冒「スペイン風邪」大流行の記録』より)。致死率から見る限り、第2波のほうが深刻だったと言えます。
しかもスペイン風邪の流行はこれで終わりではありませんでした。大正9年(1920年)秋以降には第3波が起きています。第1波、第2波に比べると感染者数と死者数は比較的少なくてすみましたが、それでも致死率は第1波より大きくなりました。結局、スペイン風邪は日本で約39万人の命を奪い、収束まで3年近くかかったのでした(ちなみに全世界での死者は2,000~5,000万人、致死率は2.5%以上と推計されています)。
もちろん、スペイン風邪と今回のコロナウイルス感染症は別のものであり、当時と現在とでは衛生環境なども違うので、同列には論じられませんが、第2波の恐ろしさは十分わかると思います。
第2波リスクへの備えと経済的支援が不可欠
以上の3点から言えることは、第2波のリスクは決して軽視してはならないということです。経済再開を急ぎすぎて第2波が大きくなってしまえば、元も子もありません。
最近発表されている感染者数は一時期に比べるとかなり減少していることは確かです。しかしゴールデンウィーク明けに人出が増加している傾向が感染増加につながっていないかが気になるところです。その結果が数字となって表れるのは約2週間後です。
しかし西村康稔新型コロナ対策担当大臣は、特定警戒地域以外の34県については早ければ14日にも緊急事態宣言を解除する可能性を示唆し、特定警戒の13都道府県の中でも「新規感染者ゼロが続いていれば解除が視野に入ってくる」と述べました。これだと、ゴールデンウィーク明けの感染状況を確認する前に解除する地域が出てくることになります。少し急ぎすぎではないでしょうか。このような報道が相次ぐこと自体、さらなる緩みを招くことにもなりかねません。
もちろん解除が検討できるということは、それだけ状況が改善してきたわけで、喜ばしいことではあります。しかし急ぎすぎは禁物です。解除ムードに流されてはいけません。むしろ急ぐべきなのは、経済的な苦境に立っている人や企業への支援をもっと手厚く、かつ迅速に行うことです。そのうえで第2波リスクへの備えをとることを前提に、解除や緩和の条件と段取りをしっかりと進めていくことが必要です。