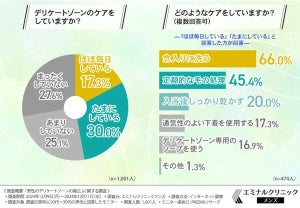第二のコーナーは「Ⅱ 身を潜めた日本美術─西洋的な表現との融合、触れて愛でる感覚」と題されている。1880年代に入り30代半ばで創作活動も中盤を迎えたガレは、作風に大きな変化を見せる。これまでのような日本美術からのあからさまな借用、転用は影を潜めて、西洋的な表現との融合を試みているのだ。
たとえば、展示されている「ペリカンと翼龍」と題された壺。透明ガラスに茶褐色ガラスを厚く被せた表面に、ペリカンとドラゴンが睨みあう。善なるペリカンは透明ガラスの白で、悪を象徴するドラゴンは黒褐色。どう見てもこれまでの華麗なジャポニスムとは無縁に思えるこの作品は、葛飾北斎の『富嶽百景』にある「登竜の不二」からモティーフを借り、西洋風のシンボルに置き換えたと言われる。日本美術を自国の文化と融合させて、新たな表現を生み出そうとするガレの姿が見えるようだ。
さらには、会場に展示された碗「花」や、碗「菊風」と名付けられたガラスの器。これもまた先のコーナーで見た華麗なジャポニスムとは明らかに異なる。だが、ここでガレが表現しようとしたのは、日本の茶道に見られる「触れて愛でる感覚」だったという。手にすっぽりとおさまる小ぶりの作り。触れたときのきめ細かい彫り具合など、「触れて味わう」ことに重要な意味を持たせている。こうした碗が、瀬戸黒茶碗や尾形乾山の茶碗と並んで展示され、比較しながら鑑賞することができる。
こうしたガレの日本美術への理解の深まりに、大きな影響を与えた日本人がいた。それが、当時農商務省の技師としてナンシーに留学してきた高島北海だ。後に画家として活躍する北海の才能は、すでにナンシーの芸術家たちにも大いに認められ、その日本画は彼らに大きな影響を与えた。ガレも北海と親交を深め、かつ大いに影響を受けたと言われる。北海とガレの交流を示す書簡や、北海の作品も展示され、北海との出会いがガレに日本美術への理解をより深めたことを窺わせる。
「もののあはれ」も理解した"日本人"ガレ
4階会場から階下の3階に移動すると、次のコーナー「Ⅲ 浸透した日本の心─自然への視線、もののあはれ」が現れる。ガレは、1904年に白血病で突如この世を去るが、このコーナーにはいよいよ1900年代、円熟したガレの最晩年の作品が並ぶ。会場でまず目に飛び込むのが、きのこの形をした有名なランプ「ひとよ茸」だ。
「ひとよ茸」は、数日間で成長すると、夜に笠を開き、一夜にして柄だけを残して溶けてしまう。ガレは、この短命な茸の成長を3段階で表した。この作品に代表されるように、ガレは1890年代に入ると、花や昆虫そのものの姿を作品にするようになる。茄子の姿をそのまま写しとった花器「茄子」や、清楚なヴェロニカの実を象った香水瓶「ヴェロニカ」など、ガレの徹底した写実主義には驚かされるばかりだ。ガレのガラス器は、彫刻の域に達したと言っても過言ではない。これもまた、ジャポニスムの大いなる影響の賜物であった。
場内にはガレの作品と並んで、茄子そのものを打物で見事な水滴に作りあげた明治期の打物師・平田宗幸の「茄子水滴」や、全長1m以上ある大きな瓜をそのままに、そこにとまる鳥や蛇の姿をリアルに描いた正阿弥勝義の「瓜形花器」、まるで生きているような渡蟹が器上で戯れる初代宮川香山の「色絵蟹高浮彫水鉢」などの作品が展示されている。大胆にして緻密なこうした日本人の手になる作品の数々は、現代の日本人にも大きな驚きと感動を与えるだろう。
さらにこの展覧会では、日本の美意識をさらに深く理解したガレが「もののあはれ」の感覚までも理解していたのではと提言する。その顕著な作品が「過ぎ去りし苦しみの葉」と銘された壺だ。まるで東洋の陶器かと見まごう出来栄えのこの作品は、枯葉が舞い落ちる一瞬の情景を切り取ったかのようだ。ガラス表面は痛々しさを醸しだし、器の上部にはメーテルリンクの詩文「過ぎ去りし苦しみの葉」が刻まれている。
|
|
|
|
大輪のカトレアを熔着させた花器。背面には萎えた枯れた花を熔着させ生命のはかなさを描いている。エミール・ガレ 花器「カトレア」 1900頃 サントリー美術館 |
本物の蘭の花がまとわりついたような花器。ガレの作品は立体化し、彫刻の域に達していく。エミール・ガレ 花器「氷の花」 1900頃 サントリー美術館 |
円熟期のガレを代表するこの作品は、それまで西洋美術が決して題材に選ぶことのなかったテーマを扱っている。「芸術家は自然を再現することで、『秋の哀れ』といった真の象徴を無意識のうちに創りだす」と語ったガレだが、こうした感覚はまさに日本人の「もののあはれ」に相通じる美意識と言えるだろう。こうしてますますジャポニスムを深化させたガレは「ナンシーに生れた日本人」と評されるほど、独自の芸術を確立していく。