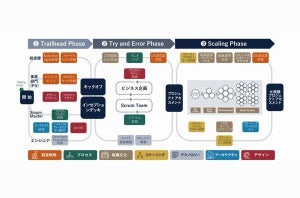ステップ3:システム統廃合の検討
ステップ2で「俯瞰整理」を行うことで、各システムの関連性や、業務や機能の重複状況などが見えやすくなります。そこで、次のステップとして、システムの統廃合による業務の最適化、スリム化を検討します。
A社では、この過程で、各システムの現状の業務仕様にばかり目が行ってしまい、「このシステムは複雑だから統合できない」「現状のデータ連携の都合で統合できない」といった意見が数多く出され、取り組みが滞りました。
このステップで大切なのは、「How」(どのように統合するか)ではなく、「What」(何を実現すべきか)を主題に議論を進めることです。システム統廃合の案は、あくまでも全体方針に基づく「あるべき姿」をイメージしながら検討します。それを意識して全体を見直すと、利用頻度が低いシステムや、他のツールで代替可能なシステムなどが浮かび上がってきます。
A社の場合も、「What」に基づく議論を重ねることで、システムのスリム化への道筋が見えました。業務とシステムが「どうあるべきか」を常に意識することで、サイロ化したシステムも全体最適な構造へと変えていくことができます。
ステップ4:移行分類の策定
ここまでの検討と議論があって、ようやく、それぞれのシステムをどのようにモダナイゼーションしていくかの分類に入ります。
A社では、「競争領域」の業務を担うシステムが、自社ビジネスの源泉であり、独自性の高い業務を多く取り扱っているという判断から、これらをクラウドのPaaSを活用してクラウドネイティブなシステムとして再構築(リアーキテクト)する方針としました。競争領域に属するシステムをクラウドネイティブ化することで、変更や改修を迅速に行い、市場環境や経営戦略の変化へ追従できるようにすることを意図しています。
一方、「非競争領域」の業務を担うシステムには、ビジネス上の独自性がなく、定型化可能な業務が該当するため、再構築を避け、SaaSへの置き換えを進めました。これによって、再構築の対象となるシステム数は減り、運用コストも削減できます。そこで生まれた余剰のリソースと人材は、競争領域に投入できます。それだけでなく、システムのSaaS移行に合わせて業務にも見直しが入るため、業務プロセスの最適化といった副次的な効果もあります。
ただし、グローバルで展開しているSaaSを採用する場合には、各地域の商習慣や法令対応など、SaaSの機能だけでは、どうしても業務要件に合わない部分が出てくる可能性があります。その場合は、将来的なメンテナンス性を考慮し、SaaSに個別のカスタマイズを行うのではなく、クラウド上に周辺機能を別途構築し、拡張機能(アドオン)として連携させる方針としました。
A社の事例では、移行分類の検討の中で、業務領域の見直しが行われ、既存の大規模システムは“競争領域”としてクラウドネイティブに再構築する一方、一部のサブシステムについては“非競争領域”としてSaaSに切り出す方針となりました。また、懸念されていたデータ管理要件も見直されたことで、クラウド活用が大きく推進される結果となりました。
ステップ5:人や組織などのリスキリングを計画する
多くの検討や決断を経て、自社のIT環境が「こうあるべき」という“To-Be”のイメージができたとしても、IT部門にクラウドネイティブを実現できる人材がいなかったり、運用スタイルが従来と変わらなかったりするようであれば、「モダナイゼーション」の成果は十分に得られません。これらをケアするために、クラウドならではの技術や運用スタイルに関する技術習得のためのトレーニングや実践が必要になります。
また、リアーキテクトによって業務プロセスも変わるのであれば、エンドユーザーが、それに習熟するためのプログラムが求められるでしょう。
A社の場合は、リアーキテクトの対象となったシステムの中から、1つをクラウドネイティブ化のパイロットシステムとして選定し、先行してノウハウの蓄積と人材育成を進めるプロジェクトとしました。また、エンドユーザー向けにも、新たな業務プロセスに習熟するためのトレーニングプラン(社内説明会など)を策定し、組織的に取り組んでいます。
モダナイゼーションを「リアーキテクト」の絶好の機会と捉える
DXを視野に「モダナイゼーション」へ取り組むのであれば、既存ITの枠組みだけでなく、その業務特性を踏まえたシステムの整理と、“あるべき姿”を見据えた業務見直しを含む「リアーキテクト」を前提とすることが重要です。
そして、過去の経緯から、業務とシステムとの関係が複雑で、見えづらくなっている企業こそ、これらのステップを通じて状況を整理していくことで、モダナイゼーションを“絵に描いた餅”ではなく、フィジビリティ(実現可能性)の高い計画として進めていくことが可能になります。
特に経営層は、リソースの消費に終わりがちな「マイグレーション」にとどめるのではなく、「モダナイゼーション」はより大きな付加価値を生む可能性の高い「リアーキテクト」の絶好の機会であると理解し、積極的に促進する必要があるでしょう。それは、 IT投資によるビジネスへの貢献を最大化し、効果的に自社のDXを進めるための推進力となるからです。
著者:藤井 崇志
Ridgelinez株式会社 Manager Technology Group