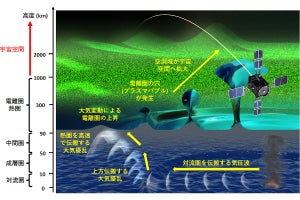ここで観測された地殻変動に基づき、同地域のテクトニクスや地震活動も考慮して変動源を推定したところ、2020年11月末からの3か月間に、約1400万m3もの流体が深さ16kmまで上昇したと推定されたという。それらの流体が同地域地下にある透水性の高い逆断層帯内で拡散することで、同断層の深さ14km~16kmで「非地震性逆断層すべり(スロースリップ)」を誘発し、さらに断層帯の浅部側で活発な群発地震を誘発した可能性があるとしている。
そして、2020年11月から2022年6月までに上昇した流体の総量は約2900万m3(東京ドーム約23個分)に達し、このような大量な流体の上昇が長期にわたるスロースリップと群発地震を引き起こした原因であることが考えられるとした。
研究チームは、この流体の上昇とスロースリップの発生は、能登半島北東部周辺の活断層帯における応力を増加させると同時に、群発地震震源域周辺での大地震の発生を促進させる可能性があるとする。さらには、群発地震での地震動による応力擾乱が活断層帯に作用することで、大地震の発生時期が早まる可能性があることも指摘されたという。
地震やスロースリップの発生には、流体の移動に伴う断層帯の強度低下が重要であることは以前から指摘されていた。しかし、実際の地殻変動観測によって地下の流体の移動とそれに誘発されたスロースリップが捉えられた例は、世界的にも珍しいという。また、2年半もの長期にわたる地殻変動の変化が、能登半島のような非火山地域で観測された事例はほとんどないとしている。
また5月5日のM6.5の地震も、地下の流体移動とスロースリップによって発生が促された可能性があるとする。今回の研究で明らかにされたような流体とスロースリップおよび地震発生の事例は、実際の断層帯の特性を絞り込むために必要不可欠な情報だといい、流体がスロースリップや群発地震、さらには大地震の発生に与える影響を、これらの現象間の相互作用も含めて定量的に解明できれば、群発地震や大地震の発生予測に向けた研究の進展する可能性があるとした。
研究チームは今後、5月5日の地震に至るまでの流体やスロースリップの移動などを、さらに時間分解能を上げて推定することを試みると同時に、国土地理院、ソフトバンク、大学のGNSSデータの統合解析を続け、その結果を政府の地震調査委員会などに報告することで、地殻変動の現状把握に貢献していくとする。
また、今回の研究はソフトバンク独自基準点が電子基準点網を補完する能力を有することを示したとし、地殻変動研究分野においての利用が今後一層進むことが期待されるとしている。