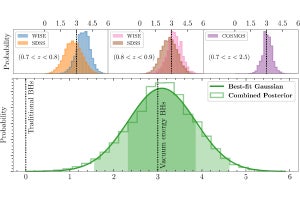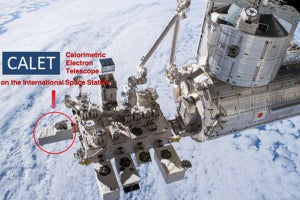超新星の再増光は、センチ波ではこれまでに何例か観測されていた。しかしセンチ波におけるシンクロトロン放射は、その大部分が放射後すぐに衝撃波や星周ガスに吸収されてしまうため、もともと放射された量を正確に知ることが困難だ。それに対し、アルマ望遠鏡が観測可能なミリ波帯なら、より正確なガスの情報を捉えることが可能だ。これにより今回、ミリ波帯で超新星の再増光を観測することに成功したのである。
再増光が爆発後200日の時点で見られなかったのは、超新星爆発で発生した衝撃波が、末期に撒き散らされた濃いガスに到達していなかったためだと考えられており、その後衝撃波が到達し、1年以上が経ってから再増光が観測されたと推測されている。
-
超新星爆発前後のイメージ。(1枚目)画面中央のオレンジ色の星がSN2018ivc。青色は伴星。(2枚目)伴星との重力相互作用によって爆発直前(爆発の約1500年前)に星周物質がばらまかれる。(3枚目)超新星爆発の瞬間。(4枚目)爆発で飛び散った星の残骸が時間差で星周物質に届き、約1年後以降に電波再増光として観測された。(C)ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), K. Maeda et al.(出所:阪大プレスリリースPDF)
この増光の強度とその時間変化を理論による予測と比較することで、超新星爆発の位置から0.1光年ほどの距離に、濃いガスが分布していると考えられるという。さらに、このようなガスの分布は、超新星爆発の約1500年前に連星相互作用により星周ガスが剥ぎ取られた場合に実現すると推測されたとする。
なお大質量星の生涯は、連星系を成さない場合や連星の軌道半径が長い場合は、生涯を通じて連星相互作用の影響を受けない「単独星進化」の経路を辿るという。一方で軌道半径が短い場合は、爆発のずっと以前に連星相互作用を起こして、進化最終期では静かな状態で超新星爆発を起こすタイプの「連星進化」の経路を辿ると考えられている。
今回の事例はその中間にあたり、これまで観測されておらず、体系的な理解が欠けたミッシングリンクとなっていたとする。京大の前田教授は、今回の成果がそのミッシングリンクに対する「非常に重要な成果」としており、また今後もアルマ望遠鏡の突発天体現象観測による成果に期待するとしている。
-
(左)超新星爆発直後にハッブル宇宙望遠鏡によって撮像されたM77の可視光画像。SN2018ivcの位置が示されている。(C)Based on observations made with the NASA/ESA Hubble Space Telescope, and obtained from the Hubble Legacy Archive, which is a collaboration between the Space Telescope Science Institute (STScI/NASA), the Space Telescope European Coordinating Facility (ST-ECF/ESA) and the Canadian Astronomy Data Centre (CADC/NRC/CSA).(右)上は、アルマ望遠鏡によるSN2018ivcの爆発から約200日後の画像。下は約1000日後の画像。約300~500日後の時点で始まったと考えられる、明確な再増光が確認できる。(C)ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), K. Maeda et al.(出所:アルマ望遠鏡Webサイト)