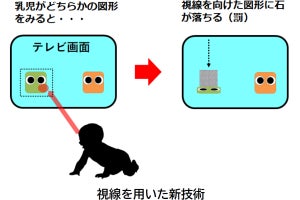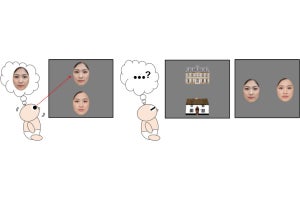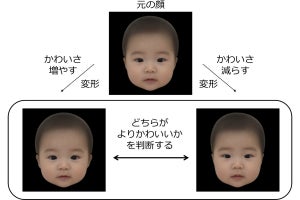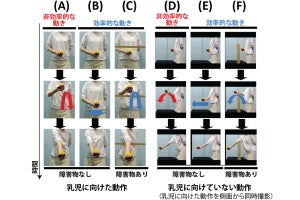この仮説を検証するため、文化の異なる日本の4~5歳児80名と米国の4~5歳児58名が参加した、2つの比較実験が行われた。1つは、待ち時間が長いと予想される日本の子どもたちと、逆に短いと予想される米国の子どもたちとの比較で、もう1つは、それをプレゼントに変えたものだという。日本の子どもたちはプレゼントを開けることを待つ習慣があまりないと想定されることが理由であり、実験では、どちらも目の前の1つを取るか、15分待って2つ目も得るか、という内容としたとする。
実験の結果、日本の子どもたちは、ギフト条件では半数が5分以下の待ち時間だったのに対し、食べ物条件では6割近くが15分待つというもので、事前の予想通りであった一方、米国の子どもたちは、食べ物条件では半数が4分以下と予想通りだったが、ギフト条件では半数が15分程度待つという、予想外の結果が示されたという。
この結果は、米国の子どもたちは誕生パーティーやクリスマスパーティーなど、特定の機会にしかプレゼントをもらうことがないことが一般的なことが、まず影響している可能性があるとする(日本の子ども一般的に、何かのご褒美など、年間を通してプレゼントをもらえる機会が多いと考えられるという)。
また、米国の子どもたちは、友達が帰るまではもらったプレゼントを開けない、クリスマスツリーの下にプレゼントが用意されてから何日も待って開けるなど、プレゼントを開けることを待つ経験が多い傾向にあるという。こうした経験が、ギフト条件の待ち時間に反映されている可能性が十分にあると考えられるともしている。
これらの結果から、子どもの満足遅延は、単に自らの注意や思考を制御する認知能力の高さを反映しているのではなく、文化内で蓄積された報酬を「待つ」習慣によって支えられていることが示唆されると研究チームでは説明している。
研究チームによると、今回の研究成果については、満足遅延課題では、対象となる報酬や個人によって異なる心理プロセスを測定している可能性があることを示唆するものであるとする。たとえば、日本の子どもの場合、マシュマロテストの待ち時間は、主に食べるのを待つ食卓習慣の強さや習慣を作る際に必要となる、集団の行動に対する感受性が反映されている可能性がある。一方、プレゼントを開ける場面での待ち時間は、自らの注意や思考を制御する認知能力の高さや他者への信頼感などの影響をより強く受けるかもしれないとしている。
また今回の結果は、子ども個人の認知能力のみならず、個人を取り巻く他者、集団、文化により支えられている可能性が示されており、子どもたちを取り巻く環境を教育・福祉の中でどう形成してゆくかが、子どもの満足遅延にも大きな影響力を持つと考えられるとしており、今後は、子どもの満足遅延がどのように形成され、そしてその個人差や発達差が将来的に重要な意味を持つのかどうかといった、長期的な視点を持った研究の実施が望まれるとしている。