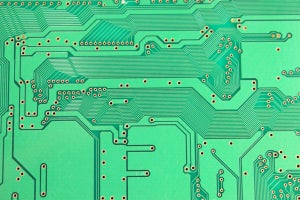IJKK1.0という呼称が気になったのですが。こういうときは、これまでを「1.0」と称し、新たな取り組みは「2.0」と位置づけることが一般的だと思うのですが(笑)
鈴木:確かにそうかもしれませんが(笑)、これまでにない取り組みであり、スクラッチで開始した取り組みであったことから、あえて「IJKK1.0」と呼んでいます。
インテルは、今後、どんな方向に向かうのでしょうか?
鈴木:デジタルトランスフォーメーションという言葉があちこちで使われていますが、この言葉が示す表現の範囲は幅広いといえます。インテルでは、これをもう少し絞りこんだ形で、「データセントリックトランスフォーメーション(DcX)」という表現を用いています。これは、IoTやネットワーク、データセンターを結んで、データをいかに生かすかということにフォーカスしたものになります。
インテルの立場から見れば、データをいかに活用するのかが最も重要であり、企業の競争軸は、蓄積したデータを迅速に処理し、真のビジネス価値に転換することができるか、あるいはできないかという点に移行することになります。
ガートナーの調査によると、日本の企業のうち、データの利活用によってビジネス成果を十分に得ている企業は、わずか3%に留まっています。日本の企業にとって、データをどう活用するかが大きな課題になります。
そして、もうひとつの懸念は、「データデバイド」が起こることです。
「データデバイト」とは?
鈴木:ひとことでいえば、データを活用しうる企業と、データ活用に関心がない企業、データを使えない企業との間に差が生まれるということです。かつて、コンシューマの領域でデジタルデバイドが起きたように、これからは企業におけるデータデバイドが発生し、企業格差が起こると考えています。これは必ず起こります。そうしたなかで、インテルの役割は、データデバイドに陥る日本の企業を少しでも減らすことにあるといえます。
あらゆる企業において、デジタルトランスフォーメーションが求められ、新たなビジネスを創出していくなかで、データをどういう形で扱うかということが課題になっています。しかも、そのデータはさまざまな形があり、共有するデータもあれば、社内に限定して利用するデータもあります。これまでは業界ごとに独立していた仕組みが、データだけは業界の枠を超えてつながるようになり、企業がそれをどう生かすのかということが重要になる世界が訪れています。それをうまく活用して生きていくことができる会社と、そこに関心を持たない会社との間にデータデバイドが発生し、それが競争力の差に直結することになります。
日本では、2025年の崖に加えて、データをどう使うかということを真剣に考えなくてはいけない時期に入ってきており、データデバイドに対する危機感を持つべき時期にあります。
東京電力パワーグリッド、中部電力、関西電力、NTTデータが出資しているグリッドデータバンク・ラボは、送配電事業から得られる電力データを利用して、社会課題の解決やビジネス価値の創造につなげようという取り組みを開始しています。電力データ活用の気づきと可能性を発信するとともに、データと企業、企業と企業を結びつける場所を提供し、電力データと異業種データを組み合わせた新たなサービスやソリューションを創出し、これらを社会に実装していく取り組みを進めています。業界を超えてデータを扱うという流れが生まれていること、それによって生まれるメリットをしっかりと理解しないと、これから広がるデータデバイドにおいて、「あっち側」に陥ることになります。
インテルは、2019年に日通や楽天と協業し、その成果を発表しています。日通との協業では、物流向けIoTソリューションの「インテルCLP」を展開。楽天とは5G向け領域で協業を発表しましたが、これらは、まさにデータデバイドの「こちら側」の事例だといえます。
また、沖電気工業とは、AIエッジコンピュータ「AE2100」で協業していますが、これもデータを活用するための有効な取り組みのひとつです。
これらに共通しているのは、主体はそれぞれの会社であり、インテルはそれをサポートする役割を担っている点です。そして、こうした事例を数多く紹介することで、日本の企業がデータデバイドに陥らないために、意味があるアドバイスをする役割を担っていきたいと考えています。
インテルは、単に半導体を提供する会社ではありません。もちろん、コンサルティング会社でもないし、SIerでもない。ただ、新たなビジネスを一緒に考え、ビジネスマッチングをすることができる。これは、インテルが持つ中立な立場であるからこそ、実現するものだといえます。
多くの企業にとって、データセントリックトランスフォーメーションが重要な課題となっているのは明らかです。インテルは、そこに大きな貢献ができる会社だといえます。
2020年は、企業のデータセントリックトランスフォーメーションを支援する企業であるという認知度をさらに高めていきたいですね。