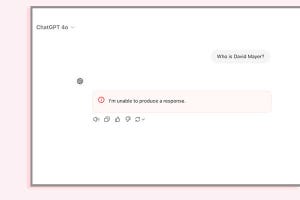そして、実際のプロダクトリサーチにおいて大武氏を中心とした日本の研究開発チームが重視したのは、消費者の“リアルな声”なのだという。データマーケティングが全盛のこの時代において、あえて消費者モニターひとりひとりの声に耳を傾けることにこだわり、およそ8年間で5500名以上のモニターに協力を受けたとしている。
なぜデータマーケティングだけでは十分ではないのか。大武氏は「もちろん、ビッグデータは参考にしている」とした上で次のように説明する。
「入手がしやすいビッグデータは競合他社も手に入れる。量的データから見える消費者のニーズは“当たり前”のものが多く、それだけを見たプロダクトリサーチをしてしまうと製品はコモディティ化してしまう。競合他社の製品に対して差別化を目指すためには、消費者に実際に会って生の声を聞きながら、消費者のインサイトを探ることが重要だ。製品の独自性は、消費者に寄り添うことから生まれてくる。ビッグデータの活用だけでは厳しい日本の市場環境で勝ち続けることはできない」(大武氏)
大武氏をはじめ研究開発チームはこうした考えから、アンケート調査をしたり、ときには消費者の自宅に訪問して製品プロトタイプを一緒に試してみたりしながら、約8年を掛けてジェルボール3Dを開発していったという。中には、“洗濯機の中でフィルムが溶けない”と電話越しに1時間怒られたり、「早く製品化してほしい」というエールを何度ももらったり、リアルな交流の分だけ様々なエピソードが生まれたという。
「(実物を見せながら)“人生の節目に買ったこの白いブラウスをいつまでも大切に着たい”という消費者の声に触れたときは鳥肌が立つ思いだった。こうしたリアルな声が製品を作る大きなモチベーションになった」(大武氏)
定量的に消費者のインサイトを分析するデータマーケティングは、マーケティングの効率が上がる一方で消費者のリアルな姿を見なくなるという懸念をはらんでいる。もちろん、データから見える消費者のニーズとの整合性を担保できれば“売れる商品”を作ることはできるかもしれないが、一方でデータに依存しすぎるプロダクトリサーチは作り手の熱量を下げる結果になるのではないだろうか。P&Gの開発姿勢からは、データ全盛の時代においてもリアルな声にも寄り添うことが重要であることがわかってきた。
大武氏は今後も、日本における消費者の厳しい声に耳を傾けながら商品開発を続け、その知見をグローバルの資産として活かしていくとしている。
「日本の洗濯環境は世界一厳しいといっても過言ではなく、消費者の製品に対する要求も世界一厳しいといえるのではないか。そして、素晴らしい競合他社と切磋琢磨できる市場環境もある。日本の厳しい消費者に鍛えられた製品は必ずグローバルで通用する。日本は今後人口の減少とともに一般的に消費規模が縮小していくと言われているが、P&Gのグローバル戦略にとって日本は戦略的なマーケット。日本向けに製品開発をしてグローバルに展開していくというプロセスは、今後も継続していきたい」(大武氏)