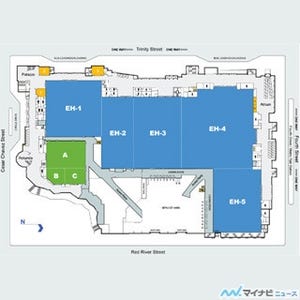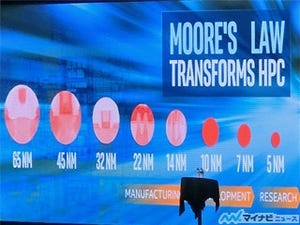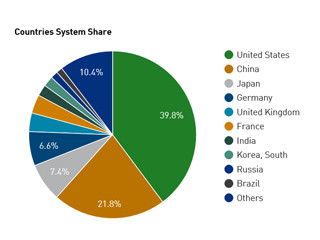中国「Sugon」のブースに展示されていたサーバモジュールは、コールドヘッドでCPUなどの高発熱のLSIを冷やすというもので、ASETEKやCoolITと同じ方式である。しかし、コールドヘッドの形は、これらの会社のものとは異なっており、Sugonと書かれているので、自社製であると思われる。
富士通の展示していたFX100スパコンもコールドプレートを使う水冷方式を採用している。銅色のパイプが水を通しパイプで、CPUに取り付けられたコールドプレートに水を供給している。このやり方は京コンピュータから変わっていない。
フランス「Bull」が11月12日に発表した「Sequanaサーバ」のボードは、中央にある3つの箱から、上下に2本の銅色のパイプが出ている。これらはヒートパイプと思われ、CPUの熱を3つの箱に運んでいるものと思われる。そしてボードの中央には横方向に水を通すパイプがあり、熱を運び出しているものと考えられる。
「Manycoresoft」という韓国の企業が「MCS-4240」という水冷クラスタのノードを展示していた。冷媒としては水でも絶縁性の液体でも良いとのことであった。
製品名も付いているので製品として販売されていると思われるが、Manycoresoftの住所はソウル大学の中のビルの一室となっている。
次の写真は、IBMの研究所が開発しているSKA(Square Kilometer Array)電波望遠鏡のデータ処理装置のプロトタイプである。SKAは膨大なアンテナ群から連続して4Exabit/sで入ってくるデータを処理する必要がある。これに必要な演算能力は2ExaFlop/sを超えると見積もられている。
このため、データ処理装置は高密度に作る必要があり、14cm×5.5cm程度の小さなプリント基板に計算ノードを収容し、データを処理するSoCに銅の伝熱板を押し付けるという構造になっている。そして、この伝熱板は両端の銅のブロックにねじ止めされて熱を伝える。このブロックには冷却水が通っており、SoCの発熱を外部に運び出すという構造になっている。
ロシア「RSC Group」のTornadoサーバモジュールは、プリント基板に搭載された部品の高さに応じてアルミのブロックを彫って、発熱の大きい部品にアルミブロックが密着するように加工する。さらにアルミブロックには冷却水を通すパイプを埋め込む。
このカスタムメードのコールドプレートを使えば、高さの異なるLSIがプリント基板に搭載されていても、すべてのLSIにコールドプレートを接触させることができる。また、富士通のFX100のように、冷却水の銅パイプが高さを取ってしまって、実装密度を下げるという問題もない。
イタリア「Eurotech」のAurora HiveもRSCと同じようなカスタムメードのコールドプレートを使っている。しかし、写真に見られるように、コールドプレートの外側は冷却水の通路が見えるような構造になっている。
そして、Aurora Hiveは、130mm×105mm×325mmのモジュールで、19インチラックに4列16段収容できるようになっている。モジュールの最大ピーク電力は1300Wとなっており、ラック全体では83kWとなる。
なお、SC15では展示されていなかったが、IBM、HPE(Hewlett Packard Enterprise)、SGI、Lenovoなども水冷のHPCシステムを販売しており、ハイエンドサーバ各社は殆どの会社が水冷のサーバシステムを販売しているという状況になっている。