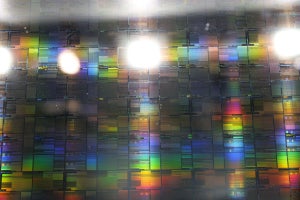震災直後よりも災害復興で用いられるレスキューロボット
2人目の登壇者はNPO国際レスキューシステム研究機構(IRS)会長で、東北大学大学院情報科学研究科の田所諭教授。IRSは2002年に設立された組織で、これまでも災害向けに能動スコープカメラなどが活躍しており、今回の震災の直前、3月8日から10日かけて米国で災害救助訓練施設で実際にどれくらい使えるかの検証実験を行っていたが、現地時間の10日に地震が発生したという報を受け急遽帰国したという。同氏も12日に帰国し、14時間運転して仙台に帰り着いた。その時点で地震発生後40時間が経過しており、仙台市消防局と協力して開発してきた能動スコープカメラを持ち出して消防局に行ったものの、今回の震災の主な事象は建物倒壊でなく、津波と原発であったこともあり、倒壊家屋を調べるよりも津波で取り残された人をヘリで救助することの方が優先度が高く、その時点で活用されることはなかったという。
14日に能動スコープカメラとQuinceなどの提供を東北経産局へ打診したものの、返答はなく、また、被災した工場などにもほとんど電話がつながらない状態で、対応どころではないという認識となり、当初のシナリオであった倒壊からの救助という線は、この時点ではなくなったという。
3月17日より福島原発対応に向けてQuinceの改造が開始されたほか、このころになると、ロボットを使って調査してもらいたいという話も出始め、全壊建物調査や港湾調査などのほか、4月12日からはJAEAチームニッポンの車両への3次元・熱画像カメラの搭載に向けた開発も始まった。阪神淡路大震災から新潟中越地震を経て、「それらの経験で、いきなり被災地に持ち込んでも使われないということが分かり、配備をして、準備をして、訓練をしないといけないというのが反省点であった。これまで、その反省点から準備をしてきており、米国での駐車場の倒壊で能動スコープカメラを瓦礫の下の状況やどのように応力がかかったかの調査を実施したり、独ケルンの公文書館が倒壊した際にも作業に参加するなどのほか、Quinceは千葉市消防局に半年間試験配置され、問題点の洗い出しなどが行われてきた」(田所氏)と、実践投入経験や実際に活用してもらう消防局との連携なども行ってきたが、「結果として、役に立ったとも言えるし、役に立たなかったと怒られても仕方ない」(同)とし、「建物が倒壊して、何が起きているのかを調べて、救助に役立てる。阪神淡路大震災ではこの方法で役に立ったが、今回は津波がメインでこのシナリオと一致しなかった」とも振り返った。
Quinceは、原発で活用できないかという話が出ているが、どういう改良が行われたのかや、どう活用されるのかは、大塚実氏のレポートが詳しいのでそちらの譲るとして、田所氏は、「我々の災害対応ロボットは高度救助機材」だと自分達が開発してきたロボットを表現する。「隊員の能力を拡大したり、隊員がダメージを受けないようにする。隊員の変わりにいけないところを調べる。また、被災者の支援を人の手に余ることを実現することを求められている。単に開発しただけでは役に立つことはない。これは10年間の開発で分かっており、そのために色々と押さえるポイントがある。例えばユーザーマッチング。災害時、ユーザーが何を必要としているのかは、ユーザーも分かっていない。また、状況によりニーズは変わってくる。メンテナンス性なども重要。時間の制約もあり、必要な機能はすぐに出せる必要があり、そのためには訓練も必要だったり、数が出せる必要がある」と、災害時のニーズにマッチしたロボットを用意する必要があるとする。しかし、「ビジネスとして考えると、マーケットサイズが重要で、ロボットの開発はできるが、(買う人も企業も自治体もいなければ)製品化は難しいということとなる。費用対効果を考えると、ロボットが必要であれば、それを活用してくためにロードマップを示していく必要があり、配備と活用に向けた10カ年計画などを立てる必要がある」と指摘した。
また、「ロボットの操作を簡単にし、訓練を必要なくすれば良い、と言う人がいるがそれは間違い。ベーシックなことを行わせて、しっかりと基礎を養う必要がある。そして、そうしたやる気のある人にしっかりと行き渡るように産官学で連携してく必要がある」とも指摘した。