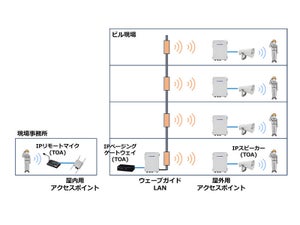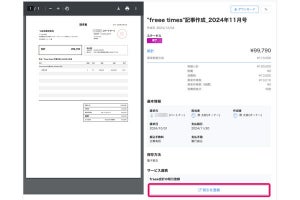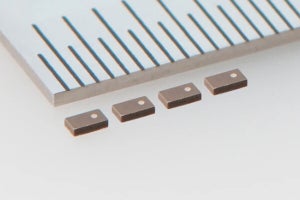8月3日(火)、東京ミッドタウンにて「言葉のデザイン2010」第3回となる研究会が開催された。第1回、第2回ともに「文字(書体)」を使う側(アプリ開発など)、「文字(書体)」を作る側(デザイナーなど)に基調報告を行ってもらったが、今回はさらに踏み込み、「言葉」そのものを扱う方々をお招きした。小説家の高橋源一郎氏と、エディター/ライターの橋本麻里氏である(ちなみに両者は父娘でもある)。
ディレクターの原研哉いわく「デザイナーの視点のみで言葉をうんぬんしても、言葉の生態を捉えることはできないのではないか。いま、言葉がどういうふうに変わろうとしているのかを、言葉のプロフェッショナルに聞きたいと考えています」
前半は、橋本氏が聞き手となり、高橋氏の考えを語ってもらった。後半は、原研哉、永原康史を交え、変化する環境について、意見交換を行った。
一身にして二世を経る
橋本「日本文学の書き手は、長い間、ペンで書いてきたわけですが、1980年代以降、ワープロで書く作家が増えてきました。いまは、パソコンに向かい、ワープロソフトやテキストエディタを使っている方も多いでしょう。時代の変化やテクノロジーの進展にともない、書く環境は変化します。その際、文体も影響を受けるものでしょうか」
高橋「受けますよ。福沢諭吉は『一身にして二世を経る』と言っていますが、ぼくの場合、手書きの原稿からキーボードへの変化が、まさに『一身にして二世を経る』だった」
橋本「デビュー作の『さようなら、ギャングたち』(1981年)は、もちろん手書きで?」
高橋「そうですね。当時のやり方としては、まず、下書きを万年筆で書いて、その後、サインペンで清書していました。『さようなら、ギャングたち』は、原稿用紙にして500枚強。清書するだけで、23日間もかかりました。一日20枚が限界です。もうね、本当に苦行で。下書きと清書を一回でできないかなあと夢想していたら……」
橋本「ワープロが登場したと」
高橋「ペンで書いていたときは、当然、片手だけを使うわけですが、ワープロの場合は、両手が使える。モノラル録音からステレオ録音になったようなものです(笑)。同時に、頭で考えていることを、ダイレクトに出力しているような気分にもなった」
橋本「執筆時の肉体的な苦痛からは解消されたわけですね」
高橋「キーボード入力のおかげで、書くことが苦痛じゃなくなった。と同時に、それが現代文学の貧困を招いた気もする(笑)」
橋本「どういう変化が生じました?」
高橋「気をつけなきゃいけないのが、"とりあえず書けてしまう"こと。たとえば、万年筆で書いていたときは、モンブランを使っていたのだけれども、モンブランという時点で、重々しい名作が書けてしまう気がする。キーボードの場合、口語に近いものは、圧倒的に書きやすい。逆に、手書きだと、口語のスピードに追いつかない」
橋本「ここ20年ほどの日本文学の動向を見たときに、どういう変化があったと思いますか」
高橋「キーボードで執筆することと関係していると思うけど、口語体を採用した小説が増えたよね。それから、肉体的苦痛から解放されたわけだから、"長いもの"が書けるようになった。だって、いくら書いても疲れないんだもん。村上春樹の『1Q84』も、手書きだったら、2巻目で完結していたと思う(笑)」