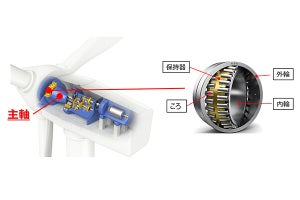点から線へ
――昨年10月に行われた『Tai Rei Tei Rio』コンサートでは、10人の演奏家たちにその想いをどのように伝えて、ひとつの音楽へと導いていったんですか?
高木「"背後霊を連れて来て下さい"って言ったんです(笑)。"先祖の霊ってあるでしょう。演奏する曲はこういうものですが、自分のルーツにちゃんと足を根付かせて演奏して下さい。そうすれば、違うメロディーを弾いても間違ってもいいんです"と。皆さんやはり同じ日本人の血を持っているからなのか、わかってくれて」
――すごいですね! 一言で感覚を共有できるなんて。今回、CDでも映画『或る音楽』でもその一部始終を音と映像で体感できるわけですが、何かひとつの真理に真っすぐに向かっていく力強さを感じました。それは言葉にしづらいのですが、脳天を直撃して、細胞が揺さぶられるような感覚とでもいうか。
高木「今、音楽として捉えられているのは、ここ100年ぐらいの間に新しく作られたシステム上の音楽なんですよね。もちろんそれを否定する気はありません。ただそれが『らくだの涙』やサハラ砂漠での経験のような、何千年という年月をかけて育まれた音楽からは、外れているところが確かにある。例えば日本のルーツミュージックをやろうとしてもお手本が残っていないんですよ。日本人として日本の音楽をやりたいと思っても、“点”しか残っていません。そこに昔と今の断絶を感じてしまいます。同時に、自分の血にはわずかかもしれないけど、日本の音楽の痕跡がしっかりと残っている気がします。とても細い点や線ですが。でもそれを繋いでいけば、僕の聴きたい音楽はきっとできると思って、今回試みました」
――ジプシー・バイオリンやイーリアンパイプスなど、すごく有機的であたたかい音色も印象的で。普段聴き慣れていない音なのに、どこか懐かしさを感じるんです。それに音はもちろん10人の呼吸すらも共鳴しているようで。
高木「最終的には、いかに演奏者それぞれの自我を消していくのかということが課題でした。もちろん、コンサート直前には、やるべき方向も見えて"音楽"としては十分まとまっていましたし。それがいよいよ舞台にあがる直前、いざやるぞってなった時に、演奏者全員集まって手を繋いで5分間ほど黙祷したんです。すると練習では味わうことのなかった、なんとも言えない気持ち良さが込み上げてきて。みんなもそれは一緒だったんです。そこでようやくこのコンサートでやろうとしていたことの本当の意味を感じあえた気がします」
細胞が奮え、涙が出る感覚を求めて
――『Tai Rei Tei Rio』が掲げるテーマは、高木さんが今後も音楽を続けていく上で、欠かせない大きな表現の軸になるのではないでしょうか。
高木「例えば満天の星空や台風による大津波。自分が何も反応できない、あらがえない大きなものに遭遇した時というのは、もはや心や身体は全然役に立たなくて、細胞が奮える感じ。それは音楽と向き合う時も同じで、泣きたくもないのに涙がでるような感覚。この体験がしたくてずっと音楽に寄り添っていたんだなって。だからこの体験をもっと掘り下げていくためにも、生活も変えていきたいと思っているんです。もっと田舎に引っ越す予定なんですよ。住まいは古い日本家屋なんですけど、そこには光も闇も清潔さも汚さも、全部ある感じがするんです。新しいマンションだと、そういったものが上手に排除されていて、絶対に安全なものしか備わっていないじゃないですか。それが今の自分の感覚からすると、我慢できませんでした。できるだけ自給自足の生活もしていきたいし、こういう感覚を持って日本各地を旅したい。きっとそこから湧き出てくる音や映像があるんです」
――10年活動してきたなかで、たどり着いたひとつの境地がここにありますが、それを携えた上で、高木さんが次にどんな作品を届けてくれるのか。今から期待してしまいます。
高木「次に作りたい作品は決まっています。音楽として整う一歩手前のものを発表してみたいと。曲の原石ですよね。それは、子どもが気持ちを解放して、自由にピアノを弾くような状態に近い感覚かもしれない。それゆえ、今回以上に伝わる確信が持てません(笑)。今も昔も音楽が持つ本質的な力は、形は変わっているけれど、意味は変わっていない。それを踏まえた上で、今、自分が生きてきた時間と目の前にある世界に対応したものを表現することが何より大切だと思っています」
インタビュー撮影:波多野匠