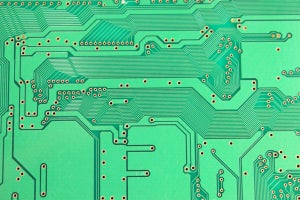DXとは単なるシステム化やデータ活用の話ではない。デジタルツールを導入したり、取得したデータを分析して活用したりすることも重要ではあるが、それだけではDXとはいえないのだ。
もっと視野を広げて考えるべきだとすれば――では、DXとは経営改革のことなのだろうか。「それは正しいが、それだけではない」と話すのは、10月28日に開催された「ビジネス・フォーラム事務局×TECH+フォーラム DX Day 2021 October 探索するDX経営」に登壇した東京大学未来ビジョン研究センター客員教授、経営共創基盤シニア・エグゼクティブ・フェロー 西山圭太氏だ。
DXに必要な思考法とは?
DXとは何か。その問いに対する西山氏の答えはこうだ。
「DXとはシステムと経営、双方向の旅である」
システムと経営を行ったり来たりすることで、2つの間には重なり(共通項)が生まれる。その重なりを形で表現するなら「横割りのレイヤー構造」だ。従来多くの日本企業が慣れ親しんできたのは、これとは真逆の縦割りのレイヤー構造であり、このギャップこそが日本企業がDXをなし得ない原因の1つになっているといえる。
では、どうすればDXを実現できるのか。
西山氏によると、必要なのは、DXを形成する横割り構造を生むための「抽象化」という思考法である。また、横割り故に、個社のビジネスだけでなく、周辺にある産業自体の構造も同時に変わっていくことも知っておかなければならない。つまり、DXの先には、産業自体の構造が変わる「IX(インダストリアル・トランスフォーメーション)」があるということだ。
このような点を踏まえた上で、DXの思考法を探っていくことにしよう。
次世代のリーダーに求められる「抽象化」能力
そもそも、デジタル化とはなんだろうか。
「かつてコンピューターが生み出された頃、人類が考えたデジタル化とは、『人間が持っている課題をコンピューターに解かせる』ということでした。ところが、それには問題がありました。コンピューターに人間の課題をどう伝えればいいか分からなかったのです」(西山氏)
そこで、当初は人間がコンピューターに歩み寄っていった。毎回、エンジニアがプログラムを書き、コンピューターに読み込ませ、得られた結果を現場で試す。非常に手間がかかり、大変な方法だった。
一方で現在はどうか。今最も身近なコンピューターであるスマートフォンについて考えてみよう。スマートフォンはいつでも手元にあり、さまざまなアプリを起動して瞬時に切り替えながら作業を行える。世界中のデータにアクセスし、ユーザーが自分で課題を解決していける。
この進歩は、コンピューターの処理能力の向上だけがもたらしたものではない。変化を促したのは「思考法」だ。すなわち、「全部、同じやり方で解けるのではないか」という考え方がイノベーションを生んだのだ。
例えば、OSも同じ発想で生まれたものだ。ビル・ゲイツは「どんなPCでも、1つのOSでさまざまなアプリを動かせるはず」という考え方からWindowsを開発した。アプリ自体は多種多様だが、それらが動作する「プラットフォーム」という共通項を作ったのだ。
また、Google社も同様である。同社の創業者であるラリー・ペイジやセルゲイ・ブリンらは、「人によってやりたいことは違っても、PCの前に座った人が誰であれ、その人が知りたいこと、やりたいことを画面に自動的に表示する”1つの方法”があるはずだ」と発想した。それこそが、Googleという検索エンジンを生み出した思考法である。
「何か1つのやり方をつくれば、全部が一気に解決するのではないか」という発想が、破壊的なイノベーションを生み出してきた。この思考法に必要なスキルこそ「抽象化」であり、「次世代のリーダーには分野を超える抽象化能力が必要だ」と、西山氏は見解を示す。
この点をさらに単純化してみよう。
西山氏はビフォアデジタルを「昭和の発想」、アフターデジタルを「令和の発想」と位置付け、両者の違いを次のように説明する。
「高度経済成長期は先進国に追いつくという目標があり、それを具体化することに注力していました。具体的に新しい業界、会社、製品が増えることがイノベーションであり、顧客の注文を取り入れて機能を追加してきました。ところが、今はこの先に何が起きるか分からない時代です。テクノロジーの世界では、『分野と関係なく一気に解ける』ということが起きているのです。そうした中では『そもそもこれって何?』という抽象化した問いが重要になります」(西山氏)
むろん、ビジネスでは具体化も重要ではある。しかし、日本は具体化ばかりに寄り過ぎていた。それこそが課題なのだと西山氏は指摘する。具体化には強いが、抽象化に弱い――それが日本の現状だ。
「少なくとも、抽象化ができないのはデジタル化において致命的な欠陥です」(西山氏)