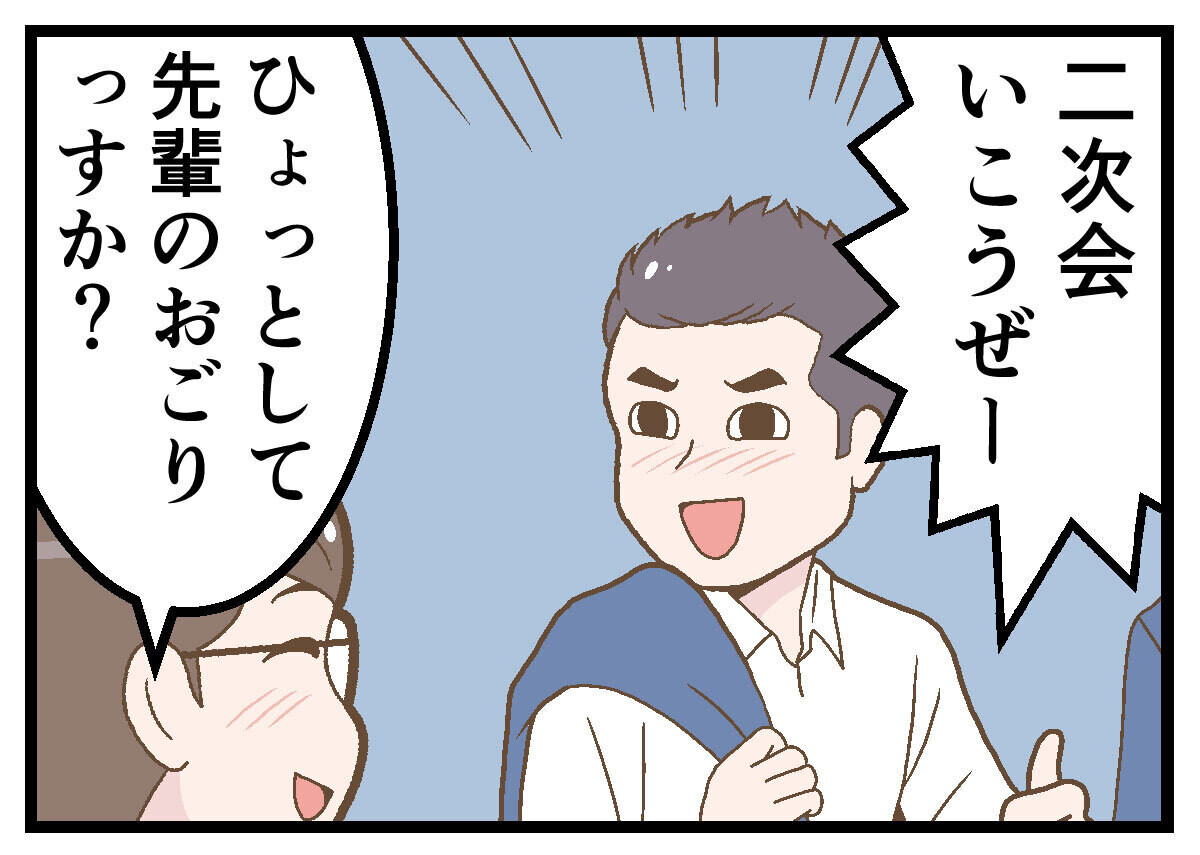先ほどの表では一見すると、配偶者の相続分は優遇されているように思えますが、日本人の財産内容を考え合わせるとその理由が見えてきます。
日本では、住まいの取得には膨大なお金を必要とします。また、かつては住まいの耐用年数が短かったため、生涯に一度は住まいの取得のための出費が不可欠でした。したがって、日本人の財産の大部分は居住用財産が占めています。
相続時にこの居住用財産を切り刻んで分配するわけにはいきません。他の法定相続人が法定相続分や遺留分を要求したら、最悪住まいを売却して、資金を作らざるを得ないかもしれません。残された配偶者が住み慣れた住まいを手放さなくてはならないケースもあるのです。多くのケースでは配偶者も高齢化していると思われますので、新たな住まいを見つけるのも簡単ではありません。
法定相続人が配偶者と子どもであれば、配偶者が相続した財産はいずれ子どもに引き継がれます。しかし、「子どもがいない」「再婚で義理の子どもがいる」などのケースであれば、そのまま今の住まいに住み続けられないことも考えられます。
40年ぶりの民法改正の中身
上記の背景を受け、政府は2018年3月31日、死亡した人(被相続人)の配偶者が自宅に住み続けることができる権利「配偶者居住権」の新設を柱とした民法などの改正案を閣議決定しました。配偶者の住まいに関する改正は以下の内容となっています。
配偶者の居住の保護……配偶者が相続開始時に居住している被相続人所有の建物に住み続けることができる権利を創設し、遺産相続の選択肢の一つとして取得できます。
遺産分割……婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、配偶者が居住用の不動産(土地・建物)を生前贈与したときは、その不動産を原則として遺産分割の計算対象としてみなさないことが盛り込まれます。
遺言制度……自筆ではなく、パソコンなどでも自筆証書遺言の財産目録を作成できるよう、法務局が自筆証書遺言を保管する制度を創設されます。相続人となった配偶者が今までの住まいに住み続けるためには、遺言が有効です。遺言を気軽にできる制度が求められています。
実は私の両親も、40年ほど前に父親が会社員から自営に転身するにあたって、この制度を利用しました。一般に起業した事業が成功する比率は高くありません。万一の場合に備えて住まいの権利を確保しておけば、一緒に事業を行ったり、保証人などになったりしない限り、住むところは確保できます。
幸いにも、我が家では問題となる事態には至りませんでしたが、定年退職後に自営するケースは現在増えています。住まいさえ資産として残れば、年金で何とか生活できる基盤は維持できます。
■ 筆者プロフィール: 佐藤章子
|
|
一級建築士・ファイナンシャルプランナー(CFP(R)・一級FP技能士)。建設会社や住宅メーカーで設計・商品開発・不動産活用などに従事。2001年に住まいと暮らしのコンサルタント事務所を開業。技術面・経済面双方から住まいづくりをアドバイス。



![[特集]介護保険制度を基本から理解する 第1回 介護保険ってそもそも何?](/article/nursing_care-1/index_images/index.jpg/iapp)