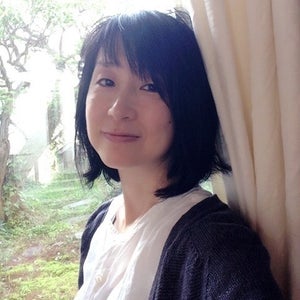『さよならテレビ』(東海テレビ)と『エルピス-希望、あるいは災い-』(カンテレ)。ドキュメンタリーとドラマでジャンルは異なるものの、“テレビ報道”の裏側を描くというタブーに切り込んだ自己批判の姿勢に、業界内外で大きな反響があがったが、それぞれのプロデューサーを務めた阿武野勝彦氏(東海テレビ)と佐野亜裕美氏(カンテレ)は、互いの作品に強く励まされていたという。
今回、そんな2人の初対談が実現。全4回シリーズの第2回は、テレビの現場で何が起きているのかを探るため、自社の報道部にカメラを入れて取材した前代未聞の作品『さよならテレビ』がもたらした波紋を阿武野氏が明かすほか、系列局だからこその懐の深さなどについて語り合った――。
■佐野氏「まるで自分を見ているかのようだった」
阿武野:僕は『エルピス』を見て、“怒り”を感じたんですね。「ジャーナリズムどうしたの? テレビどうしたの? 今のままでいいの?」という。その怒りに激しく僕は反応してしまうんですね。つまり、四六時中思っているけれど、どうすることもできない、この徒労感というか無力感というか、そういう気持ちを逆なでされるような、あるいはギリギリ締め付けられるような…。それは、僕自身の怒りとドラマのメッセージが共振しているんだと思うんです。佐野さんの中に、そういう“怒り”はありましたか?
佐野:それこそ、脚本を作っていた2017年、18年は本当にいろんなことに怒っていました。その当時は、“システムが人を殺す”ということが脚本家の渡辺あやさんとの間の大きなトピックでした。何かがヒットするとそれに倣えとなって、そこからはみ出るものは許容されにくくなってしまうこととか、人間の価値とか、観客を信じていないところとか、声が大きい人の言うことにみんなが倣えになってしまう。そういったこととの戦いに疲れ果て、怒って、またいろんなことをしては怒られ……その頃に渡辺さんのところに行ってその怒りをいっぱい話していました。一方で渡辺さんは、当時の政治のありようにとても怒ってたんですよ。そういった当時の我々の怒りとやり場のない気持ちが込められた台本になったと思います。
脚本を作っていた当時、「『さよならテレビ』ってすごいドキュメンタリーがあるらしいよ」とウワサが流れてきて、当時は見る方法がなくて、フジテレビに在籍していた友人に頼んでDVDを焼いてもらって見て、それを島根に送って…みたいなことやってたんです(笑)
阿武野:そのことを大島新さん(『なぜ君は総理大臣になれないのか』など監督)が「裏ビデオのように出回っている」と週刊誌に書いたんで、僕は「裏ビデオ」は上品じゃないから「密造酒」にしてほしいとお願いしました(笑)
佐野:でも、本当に密造酒みたいにこっそり回って、いろんな人に「見たほうがいいよ」って勧めたり、見た後にいろんな人から「見る? 貸すよ?」と言われたりして。それこそ、『エルピス』を報道の皆さんが見たときの「見た? 見た?」っていう感じですよね(笑)
阿武野:ちょっと小声で(笑)
佐野:自分の姿って、私にとっては醜悪なんですよ。できるだけ自分を客観的に見て、相変わらずダメな人間だ、と反省して苦しんでばかりいるのですが、『さよならテレビ』は、そこにいるのが自分じゃないのに、まるで自分を見ているかのようで、本当に苦しかったですね。
阿武野:やっぱり苦しいですよね。
佐野:いやあ、苦しいですね。でも、その苦しさからしか始まらないということもよく分かるので、ちょうどその頃『エルピス』の脚本を作っていて、「これは絶対にやらなきゃ」とすごく励まされました。
■阿武野氏「いまだに会社の中はすごく居心地が悪い」
阿武野:同じ2017年に、永井愛さんが『ザ・空気』(※)という演劇を作っているんですよね。『エルピス』が6年温められたという話を聞いたとき、同じ時期に、日本のどこかで、メディアのあり方とか、表現の自由とか、民主主義についてとか、根本から考え直さないとダメだと叫びたい人たちがいたんだなと思ったんですよ。それを、演劇作品にして表現した永井さんもいれば、ドキュメンタリーにした僕たちもいて、そして、時を経て全国ネットのドラマで佐野さんたちが展開したというのは、変な言い方ですけど、「答え合わせしてみてごらんよ。『さよならテレビ』は時代感覚として“◯”だったじゃん…」って、『エルピス』に励まされましたね。
『さよならテレビ』を放送した2018年に僕たちは社内でボコボコにされて、2019年も冷たい視線を浴び続けて、2020年にどさくさ紛れて映画にして、これで突っ切ったつもりでしたが、いまだに会社の中はすごく居心地が悪いですね。
(※)…人気報道番組の放送数時間前、ある特集の内容について局の上層部から突然の内容変更を命じられ、編集長やキャスターは抵抗するが、局内の“空気"は徐々に変わっていき――という舞台作品。
佐野:今もですか?
阿武野:今でも、です。ただ図々しくて、鈍感力みたいなものがありますので。それに、僕が辞めたら他のスタッフが責任を強く感じちゃうだろうから、辞めるわけにはいかない。
佐野:そうか、それはそういう状況になりますよね…。『エルピス』は、フィクションなので逃げられる部分はあって。モデルというか、キャラクターの参考にした方もいるので、たぶん本人は「自分のことだな」って分かると思うんですよ。でも「フィクションだし」って逃げ道がある。ドキュメンタリーだとその人そのものが映っているからこそ強いけど、逃げ道がないっていうことなんですよね。東海テレビさんでそうなっているとは、全然知らなかったです。どんな人が怒ってるんですか?
阿武野:当時の報道部長はすごく怒ってましたね。「許さない」という気持ちが長くあったと思います。で、『さよならテレビ』が、一つの引き金になったかもしれませんが、彼は東海テレビを辞めて大学教授になりました。この前、その彼が『さよならテレビ』を学生たちに見せたと言うんですね。「え、見せたの? 君、あんまりいい感じに映ってないよね」って言ったら、「そんなことは、いいんですよ」と。「それで学生の反応は?」って聞いたら、今の3回生は入学式もなかったし、講義もオンラインで、サークル活動もなく、友達ができないまま就活に突入なんです。しかも、授業料は満額とられるから、学生が「こんなもん『さよなら大学』ですよ」って。教授は即座に「それドキュメンタリーにしようよ」と。それで今、彼のゼミで『さよなら大学』を制作中です。
佐野:それは面白そうですね!
阿武野:それをちょっと手伝ってほしいと言うんです。つまり、プロの編集マンに見てもらったり、音効さんにサウンドの処理を教えてもらったり、学生の実地研修ですね。
佐野:そんな協力までされるんですね! そうなると、その活動そのものを撮りたくなりますよね。
阿武野:そうですね。粗編(集)を見て、「これは放送できるかもしれないね」っていう話をしてます。教授になった報道部長を『さよならテレビ』は、深く傷つけたかもしれないけど、人生の中でプラスに変える力を見せてくれていますよね。他にも、「撮るな!」って怒ってた編集長が報道部長になって、最近になって「僕、系列で挨拶するとき名刺いらないんですよ」とかニコニコして言ってたり(笑)。「東海テレビのイメージを著しく損ねた毀損した。これから東海テレビに入ってくる学生なんかいない」って散々非難されたけど、今500人入社希望者がいると、半分は「『さよならテレビ』を作った局だから」と言ってくれるそうです。そういう意味で、この“さよならテレビ騒動”っていうのは、仕掛けた側が最終的には負けなかったと思うんだけど……中島さん、合ってるかな?
――はい、合っていると思います。
阿武野:『さよならテレビ』は、時間とともに社会的には大きく価値が転換したのに、やっぱり会社の中は変われないんですね。
佐野:そうですよね。一枚岩ではないけれど、意外と強固なんですよね。
阿武野:「熱しやすく冷めやすい」と日本の悪い国民性のような中で、ジクジク自説を曲げない頑固な人間がいるというのを、プラスに考えてみてもいいかなと思うこともあります。だって、みんなが一斉に手のひらを返したように「よかったよかった」って急に言い出したら気持ち悪いですもん。それって、戦争するとき、国民がそっちの方向に一気に盛り上がっちゃうみたいなことになりかねないんで。本気で会社のイメージを傷つけたと思っているなら、それを言い続けてほしいと思いますね。
佐野:よく渡辺さんが、「そもそもなぜ人はそんなに傷ついちゃいけないのか?」と言っているんです。例えば、ドラマで「更年期」という言葉を使わないほうがいいと言われたこともあったんですけど、その理由は「更年期」という言葉が出てくるだけで嫌がる視聴者がいるからと。でも、「更年期という言葉が出てくるだけで仮に見た人が傷ついたとして、それは何がいけないんですか?」と言っていて、それは確かにその通りだなと思ったんです。今のお話を聞きながらそのことを思い出しました。