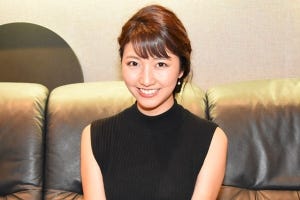普段はニュース原稿や番組の進行台本を読む機会が多いテレビ局のアナウンサー。同じ「読む」作業といえども、紙芝居の朗読は大きな違いがあるという。
内田アナは「役がある方たちは、普段口にしない独特な言い回しのセリフが多いですし、今回私が担当しているナレーターも、冒頭台本1ページ分の文量があって、まず『飽きられないかな?』という心配がありました。これだけの量を1人で読み続けて単調になってしまうと、つまらなくなって聴くのをやめてしまい、その後の面白いストーリーが聴いてもらえなくなってしまうかもしれないというプレッシャーがあったんですけど、みんなで読み合わせをしたときに、メリハリの付け方など色々なアドバイスを先輩たちからもらって、それを取り入れられるようになってから、自分の中でも『長いなあ』と感じなくなっていきました」と手応えがあった。
佐々木アナは「1つの原稿を数日かけて読むということがないんです。例えばニュース速報などは、生放送中に入ってきた最新情報を、いかに瞬時に正確に伝えるかが勝負です。1つのものを繰り返し読むというのは新鮮ですし、『こう読みたい!』とか欲も出てくるんです」と、大きな違いを明かす。
収録を終えると、どのアナウンサーも「楽しかったです!」と満足して、また参加したい気持ちになるそう。梅津アナにその醍醐味を聞くと、「ちょっとした声色で演じ分けることができることですね。収録に来るまでにいろんなパターンを考えていますし、実際に収録して『こんな感じで録ってみます?』『じゃあこんなパターンはどうですか?』といったやり取りで自分の引き出しを開けていく感じがあるんです。演じるという感覚は普段あまり味わえないので、楽しいですね」と声を弾ませた。
■アナウンサー同士が刺激を受ける機会に
「デジタル紙芝居」の取り組みは、アナウンス室内のコミュニケーションの活性化にも一役買っているという。
佐々木アナは「コロナ禍になってからのほうが、よく人としゃべっているような気がします。番組の時間帯が違って、今まであまり話したことのない人ともオンライン上でつながることで、コミュニケーションが増えた部分もありますね。もちろん、本当は業務ではない他愛のない話をしたいんですけど」といい、内田アナは「一緒にナレーターを担当している井上アナとは生活リズムが合わず、普段顔を合わせる機会がほとんどないので、オンラインの読み合せでイメージの共有をして、実際に録音が終わった後に初めて会えて『すごく良かったよ!』と声をかけ、感想を伝える感じでした」と振り返る。
フジテレビではかつて、『ラヴシーン』というアナウンサーによる朗読舞台を開催していたが、2013年で閉幕。この経験者である梅津アナは「圧倒的な先輩たちの朗読に触発されて、真似してみようとすることで、追いつけないんだけど、自分の表現が変わっていくのが楽しかったのを覚えています。今は、アナウンス室の先輩・後輩の関係での一緒に読む場がなく、刺激を受ける場面がなかなかないと思うので、良い機会だなと思います」と話した。