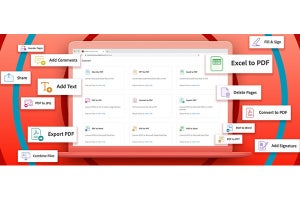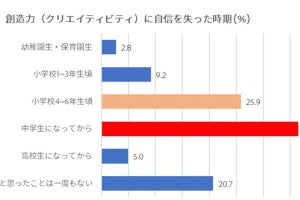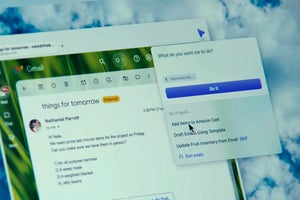レイアウトグリッドなど、日本に特化した機能を実装
InDesign 1.0日本語版で、日本に特化した重要な機能としてレイアウトグリッドがあげられる。当時の(そして今もそうだが)日本での雑誌制作の現場では「レイアウト用紙」と呼ばれる用紙が利用されている。レイアウト用紙とは、ページをすべて文字で埋め尽くしたら何文字入るのかがわかるように□(四角)で埋めてあり、簡単に文字が計算できるようになっている。編集者は写真はここに置くから文字数は何文字減る…といった計算が簡単にできる優れた仕組みだ。
このレイアウト用紙は日本独自の写植時代から引き継がれている文化で、欧米語圏にはない文化だ。したがって、それをデジタルで再現する機能は英語版のInDesignにはなかったし、競合のDTPソフトにもなくて、デザイナーが欧米向けのレイアウトに職人芸ではめ込んでいたのだ。
それがHOTAKAこと日本語版InDesign 1.0には「レイアウトグリッド」機能として標準で搭載され、日本で紙をベースに行われていたワークフローがそのままデジタルで再現できるようになった。
そうしたレイアウトグリッドへの対応や、ルビなどの日本語特有の表現に対応したテキストエンジンの開発にアメリカ側で関与したのが、現在アドビでインターナショナル製品/戦略ディレクターを務めるプリシラ・ノブル氏ら、当時の日本語版InDesign開発チームだ。日本で生まれ育ったこともあり、日本語も流暢に操るノブル氏は、PageMaker 6.5のQA(品質管理)担当としてアドビに入社した。
そして英語版のInDesignが作られるのを横目でみながら、「日本語版には日本のDTP環境にあった特別なバージョンが必要だ」と思い、それをInDesignのチームなどにアピールしたが当初はなかなか聞いてもらえなかったという。しかし、その当時の製品を統括していた、後にアドビのCEOとなるブルース・チゼン氏に電子メールで直訴した結果、日本語版だけのチームが作られることになったのだとノブル氏は説明した。
明治の文豪・夏目漱石のあの作品をベンチマークに
そうしてできたInDesignの日本語版「HOTAKA」開発チームだが、そこに配属されたのが1998年にアドビに入社した中村美香氏だ。現在もアドビで日本市場向け製品全般のUXおよび戦略リサーチを担当する中村氏は、当時InDesignのチームで動作検証を担当していた。
その中村氏は、InDesign日本語版の動作検証においてある目標を立てた。手元にあった夏目漱石全集の「草枕」をInDesing日本語版で作ることを目標にし、それを完全に作れるようにすることをテスト項目にしたのだ。
中村氏によれば、夏目漱石全集を選んだ理由として、すでに著作権などが切れており、テキストは青空文庫などの形で公開されているため、全文を自ら入力する必要が無いことが大きかったという。まずは書籍を定規でサイズを測り、そこからだいたいのサイズを計算してInDesignでレイアウトを入れて組んでいった。
中村氏は「最初はボロボロで思ったようにはできなかった。しかし、テスト担当としてはおいしい素材を見つけたという気持ちだった。もちろん製品としてはそのままでは出荷できないので、何度も組み直したりしながら製品としての質を上げていって、最終的に草枕が完全に組めるようになった段階で出荷した」と述べ、言ってみれば「草枕ベンチマーク」をクリアできるようになったからInDesign 1.0 日本語版を出荷したのだと説明した。
当初は重かったInDesign、Mac OS XやIntel Mac移行期に競合から乗り換えが進む
いろいろな人の「想い」を乗せてリリースされたInDesign 1.0日本語版だが、Webサイト「InDesignの勉強部屋」を運営する森裕司氏によれば「正直、最初の1.0は重くて使えなかった」というのがユーザーとしての率直な評価で、「1.0で仕事の入校用データを作ったことは一度もない」のが実際のところだった。InDesign 1.0日本語版が非常に野心的な製品で、その後のInDesignの飛躍に資したのは間違いないが、さりとて当時のMacintoshのCPU(PowerPC)にとっては処理が重すぎた、そういうことだろう。
森氏によれば、印刷物の多くがInDesignで作られるようになったと感じたのは、InDesign CS2からだった。その頃は、DTPデザイナーにとってもハードウェア側の大きな進化をうながされた時期だった。というのも、AppleがオープンソースのUNIXをベースにしたMac OS Xへの本格的な移行を進めていたのと、それと同時にCPUをIBM/MotorolaのPowerPCからIntelのIA(Intel Architecture)へと移行期に当たっていたからだ。
アドビの岩本氏によれば「その当時は、多くのDTPデザイナーがMac OS 9に留まっていた。印刷所とバージョンを合わせる必要などもあり、なかなかMac OS Xへの以降が進んでおらず、秋葉原の中古市場などではOS 9が動作するG4が高値で取り引きされる状況が続いていた。InDesignはCS3でUniversal Binaryへの移行を果たし、PowerPCでもIAでも動くようにしたこともあり、PowerPC+OS 9からの移行期に競合からInDesignへ移行したユーザーさんが多かったと理解している」とのことで、そうしたAppleのCPUアーキテクチャの移行にもいち早く対応したことも、競合からInDesignへの移行を促した理由のひとつだった。
そしてもうひとつ、InDesignが支持されるようになった大きな理由がある。「Creative Suite」でPhotoshopやIllustrator、そしてAcrobatといったDTP市場の定番ツールとセットになったことだ。2012年にはサブスクリプション型のサービスとして提供される「Creative Cloud」の一部になってからは、PhotoshopやIllustrator、Acrobatに続き、現在のAdobe Fonts(当初はTypekitと呼ばれていた)というフォントもセットで提供されるようになり、DTPデザイナーにとって魅力が向上し、現在に至っている。
その結果、現在ではInDesinは多くの印刷シーンで利用されるようになっており、今や印刷の世界ではQuarkではなくInDesinが事実上の標準となっている。さらには「地方自治体の広報誌などでも多く利用されているし、最近では電子書籍の作成も多く使われている」(アドビ 岩本氏)と、従来とは違うシーンでの利用も増えている。
その意味では、「Quarkに対抗する製品を作りたい」という、20年前のアドビのもくろみは十分に実現されたといえるだろう。