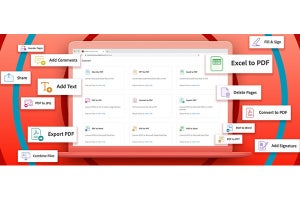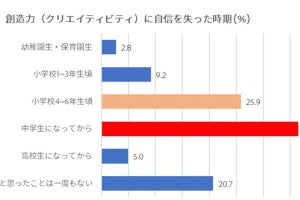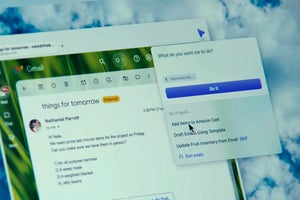アドビがクリエイター向けに提供しているサブスクリプション型のクリエイターツール「Creative Cloud」(クリエイティブクラウド)に含まれる、DTP(DeskTop Publishing)ツールが「InDesign」(インデザイン)だ。
現時点での最新バージョンはInDesign 2021だが、最初のバージョンになるInDesign 1.0が米国でリリースされたのは1999年8月31日で、2019年にリリースから20周年を迎えた。ただ、この英語版InDesign 1.0には日本語の機能は含まれておらず、開発コードネーム「HOTAKA」と呼ばれていた日本語版InDesign 1.0がリリースされたのは2001年1月26日、2021年が20年の節目の年になる。
2021年2月6日には、InDesignのユーザー団体「InDesignの勉強部屋」などの主催による、InDesign日本語版20周年を記念した「InDesign 20周年記念オンラインイベント」が、YouTube配信の形で開催された。同イベントには、日本語版InDesign 1.0のリリースに関わった当時のアドビの関係者などが集合し、当時は言えなかった開発秘話などを明らかにした。
本稿ではイベントで言及されたことに加え、アドビのプロダクトマネージャー・岩本崇氏と「InDesignの勉強部屋」を運営するデザイナー・森裕司氏に独自取材し、InDesign日本語版がリリースされた当時の印刷業界事情についても記載していく。
DTP市場を作ったAldusを買収したアドビ
DTP(DeskTop Publishing)とは、本や雑誌を印刷所で刷るための「版下」のデータを、PCで作成することを意味している。DTPが当たり前になる前は、印刷所では写真植字(略して写植)という手法を利用して版下を作っていた。写真の原理を用いて文字を印画紙などに印字するため、そうした呼び方がされていたのだ。
その写植に利用する専用機「写真植字機」は一台数百万円と高く、扱える職人さんの数にも限界があった。雑誌や本を印刷するには、印刷にかかる時間とその写植にかかる時間を計算して、入稿(版下や写真を印刷所などに納めること)する必要があった。
それを大きく変えたのが、1985年にAppleのMacintosh用のソフトウェアとして投入されたAldus(アルダス)社のPageMaker(ページメーカー)だ。Aldus PageMakerのブランドで知られていたPageMakerは、当時アドビが開発して提供していたページ記述言語「PostScript(ポストスクリプト)」と組み合わせて利用することで、写植機に匹敵するようなクオリティで印刷することを可能にしたのだ。
このため、80年代後半~90年代にかけて、徐々に写植機はDTPに置き換えられていき、雑誌や本を出版するような出版社から印刷所への入稿は版下やフィルムといったアナログな媒体から、MO(エムオー、カバー付きの磁気ディスクで当初は128MBの容量だったメディア)などのデジタルメディアへと変化していった。
筆者も90年代後半はフリーのライターとしてPC雑誌の作成に関わっていたので、校了(校正が終了するの意味で、雑誌の完成を意味する出版用語)時期になると、編集部にDTPデザイナーがやってきて格好良いレイアウトを作ってくれたのをよく覚えている。そしてでき上がった雑誌のデータは、MOに入れて、時間があればバイク便で、時間がないときには編集者自身が自分で印刷所まで届ける、それが日常だった。
アドビはこの市場に後発としてやってきた。正確に言うと、DTPという言葉を作り出したAldus社を1994年に買収したので、それ以降参入したとも言うことができるし、Aldusの歴史もアドビの歴史の一部だと考えれば、その前から参入していたともいえる。
90年代のDTP市場のスタンダードは競合の「Quark」だった
だが、90年代のDTP市場ではそのアドビ/Aldusの競合だったQuark(クォーク)社のQuarkXPress(クォークエクスプレス、現在の最新バージョンはQuarkXPress2020)が圧倒的なシェアを誇っていた。
なぜかと言えば、データを受ける印刷所側のDTP環境が圧倒的にQuarkであるところが多かったからだ。当時のDTPソフトはQuarkだろうが、PageMakerだろうが、データを出力するDTPデザイナー側の環境と、印刷所の環境をそろえるのが当たり前だった。ソフトウェアをそろえるだけでなく、ソフトウェアのバージョンもそろえることが業界の常識だったのだ。バージョンといっても、バージョン3とかバージョン4といった整数の部分だけでなく、バージョン3.11とかバージョン4.21みたいな小数点以下の細かなバージョンも合わせる必要があった。
というのも、そうしておかないと、ソフトウェアのバージョンの違いでデータの解釈に微妙な違いがあったりして、その結果デザイナーの意図が印刷に正しく反映されないことが起きるからだ。このため、Quarkでかつ、印刷所にあるQuarkのバージョンと同じバージョンの環境を作っておく、それがDTPデザイナーの常識だった。
このため、猫も杓子もDTPなら「Quark+Macintosh」の状態が続いていた。それが90年代のDTPの現状だったといえる。
対Quarkを見据えて、画期的なDTPソフトとして開発されたInDesign
強力な競合製品だったQuarkに対して、アドビが90年代の後半に開発してきたのが、同社が「K2」(ケーツー)の開発コードネームで呼んでいた新しいDTPソフトウェアだ。なお、K2とはカラコルム山脈にある世界第2位の高さの山で、後にこのK2の日本語版となる製品は「HOTAKA」(穂高、飛騨山脈の穂高岳のこと)というコードネームになるなど、この当時のDTPソフトウェアコードネームは山の名前で統一されていたようだ。
K2は元々アドビが買収したAldusがPageMakerの新世代製品として開発していた製品で、対Quarkの切り札として「InDesign」という新しいブランドが与えられ、最初のバージョンとなる「InDesign 1.0」が1999年8月31日に米国でリリースされた。
だが、このK2ことInDesgin 1.0は英語版のみのリリースで、日本語版は投入されなかった。当時の日本市場は、アドビにとっては米国に次いで2番目に大きな市場で、ビジネス的にはリリースしない理由はなかったはずだが、それでも日本語版は出なかった。なぜかと言えば、欧米と日本ではDTPに必要とされる要素が違っていたからだ。
90年代はどんなソフトウェアでもそうだったが、まず英語版が開発され、それから各国語版が展開される形になっていた。特に日本語や中国語などはダブルバイト(1文字を表示するのに2バイトのデータを必要とすること、英語などはシングルバイト=1バイトで1文字の表示が可能だった)になっており、どうしても後回しになりがちだった。
しかし、このInDesignがリリースされた2000年前後は、最初からダブルバイトに対応できるようにソフトウェアが作られ、日本語などのダブルバイト圏への展開が容易になってきており、英語版と日本語版が同時にリリースされるのも珍しいことではなくなってきていた。遅れがあっても、数年かかることはなくて、せいぜい数カ月のレベルになっていた。
そうした状況だったのに、InDesignの日本語版のリリースが遅れた理由は、アドビ Creative Cloud プロダクトマネージャー 岩本崇氏によれば「日本語のDTP環境にきちんと対応するため」だった。
「例えばルビなどの日本語特有の文字レイアウトなどに対応する必要があった。そうした日本語にきちんと対応したテキストエンジンを開発したため、英語版のバージョン1.5に近い段階でのリリースになった。英語版のバージョン1.5の機能も一部取り込んだと聞いている」とのことで、日本語特有の機能をできるだけ取り込もうとしたからだという。