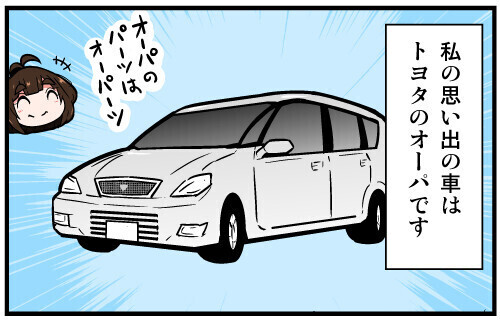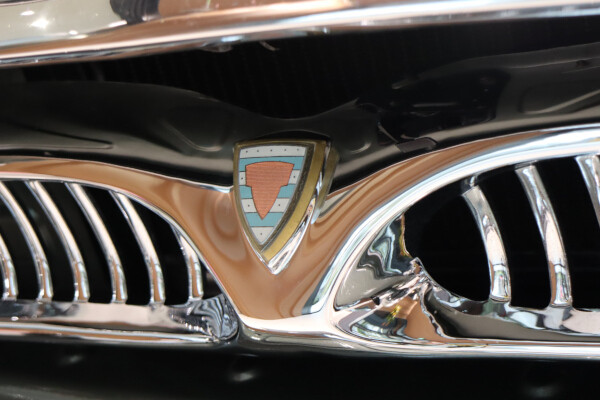クルマの本質を突くホンダの開発姿勢
前型よりも何かを向上させることにプライオリティーを置かず、あくまで消費者が喜ぶ本質を追求する。そんな開発姿勢をクルマの至るところで感じることができる。この考え方は、まさしくホンダ創業者の本田宗一郎が、他社の真似ではなく、独創によってホンダを確立した姿勢に通じる。
田中LPLは、「フィットの前の『ロゴ』、あるいは1980年代の『シティ』も、そういうホンダらしいコンパクトカーでした。中でもシティは、オーバーフェンダーを装備した高性能車やオープンカーのカブリオレ、そして、商用バンのシティプロなど、魅力ある派生車を生み出す創造力を喚起しました。フィットを開発するにあたっては、かつてのコンパクトカーの魅力も研究したんです」と話す。
ホンダの独自性はホンダファンを生みだした。その源泉は、2輪から4輪事業へ進出する際に生み出したミッドシップエンジンの軽トラックや、オープンスポーツカーを開発した過去へと遡ることができる。それらは単に奇をてらった商品ではなく、他に例をみない唯一無二の魅力を生み出そうとした本田宗一郎の志が具現化したものだった。
田中LPLは、「1958年の誕生以来、『スーパーカブ』が形を変えていないのは、それが本質を突いた開発であったからで、もはや変えようがないということです。新型フィットもそういうクルマを目指しました」と語る。
「ことに、クルマのパッケージングについては、軽自動車を見れば分かる通り、日本が得意とする技術なのではないでしょうか。日本発の発想も、そこが原点です」。そんな考えで田中LPLは、顧客に喜んでもらうべく、新型フィットの開発を全方位で見落としなく進めたというのである。
自動車開発を本社に集約、ホンダらしさの今後は
ホンダの開発を担う本田技術研究所は、ホンダの100%子会社でありながら、本社の上位に位置づけられてきた組織だ。2輪、4輪、汎用製品の全領域において独創を生み出してきたのが研究所という組織なのである。こうしたホンダの体制は、創業者・本田宗一郎の意志でもある。
2輪のスーパーカブも、4輪の「シビック」や「アコード」も、そして今日の「N-BOX」も、全て研究所の創意工夫から生まれた製品だ。ロボットの「アシモ」や「ホンダジェット」も同じである。例えば米国には、ホンダの芝刈り機を使い、ホンダのバイクに乗り、そしてホンダ車を愛用する優良顧客がいる。他にはない何かが、ホンダのあらゆる製品にあるからこそ、こうしたホンダファンが存在するのだろう。
研究所は永年にわたり、失敗することをよしとし、その失敗を次なる開発の糧としてきた。その上で、失敗は一刻も早く取り返すことが求められる。開発の過程には評価会が設けられ、役員から開発担当者が厳しく内容を精査される。出された課題に答える開発を全力で行うことにより、独創を実現する力としてきた。
研究所には「R」と「D」という開発担当がある。「R」はいわゆる先行開発で、新しい価値を生み出す技術開発を行い、「D」はそれを商品として完成させるための開発を担う。そして、ホンダエンジニアリングという独自の生産設備会社が、研究所が開発した製品を量産できるよう、設備を独自開発してきたのである。他の生産設備会社では量産できないような開発を研究所が行っても、それをホンダエンジニアリングが完成車として実現させることで、他にないホンダならではの新車が誕生してきたのであった。
それがホンダの強みであり、ホンダファンを惹きつけることができた要因でもあったはずだ。
しかし、ホンダは今年2月、本田技術研究所から、デザインを除き、4輪車に関する商品開発機能の全てを本社に統合する方針を発表した。また、ホンダエンジニアリングも本社に合併する予定だという。ホンダの四輪事業は利益率が低く、2018年度第4四半期には赤字を計上している。研究所の機能を本社に統合するのは、四輪事業で巻き返しを図りたいという思惑からだろう。
この動きは、ホンダ車をホンダらしく生み出すために本田宗一郎が形作った組織形態を転換することを意味する。新体制で作るホンダ車から、ホンダらしさが薄れてしまいはしないかという懸念が残る。
本田技術研究所の社長はホンダ本社の役員を兼務するが、本社の社長とは対立構造を持つ立場で意見を戦わせることが、ホンダの成長につながってきたのではないだろうか。本社の意向を受けるままに新車を開発するのでは、新型フィットのような新車を生み出すのが難しくなりそうで心配だ。
あえて正しい運転姿勢にこだわり、N-BOXとは違う独自の魅力を盛り込んだ軽自動車「N-WGN」に続き、4代目にしてコンパクトカーの本質に原点回帰し、熱く語れる魅力にあふれたクルマとして登場した新型フィット。これらのクルマから伝わってくるホンダらしさに今後も期待し、注目し続けたい。