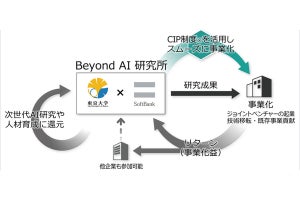変化する社会にどう対応していくべきか
司会:日本の社会すべてにおいて、すべての産業と置き換えても良いかもしれませんけど、AIを活用しましょうとなったとき、コンサルティング企業やSIerが、そのすべてを賄えるわけがリソース的にないわけですよ。そうなったときに、AIを作ってくれるのはそういう会社で良いかもしれませんけど、それを渡された使う側は、どの程度、作ってくれる側との知識や技術の溝を埋める必要があるのでしょう。そもそも埋める必要があるのか、という点も含めてちょっと聞いてみたいと思います。
保科:例えば、料理ロボットを使って料理を作るとしましょう。どのタイミングで何を投入し、何度でどう加熱するかなどの最適解は、過去の調理データを投入することでロボットが学習し、美味しい料理が完成するかもしれません。
このように今後、素人でも使える便利な仕組みが次々と出てくると思います。ただし、何も知らないで盲目的に信じて使ってもよいのかというと、それは違うと思います。
ロボットがどの程度の学習でどこまでの精度で動くのか、という勘所を掴んでいなければ失敗も起こり得ます。例えば、この料理ロボットは食材を大雑把な種類だけで判断し、味見もできないから、料理に合った肉を自分で選ばなければ美味しく作れない、などということは普通に起こるでしょう。根本的に、今やっていることに疑問を持つということは、技術がいくら進んでも必要になってくるのかなと思います。
宅島:現場でAIを適用する場合、ルールやプロセスというものと、必ずセットになって入ってくると思いますので、知識や教養として持っていないといけないところと、そうでないところを分けて考える必要がある気はしますね。
藤原:こういう話は、学生のときに学んだことが一生涯通用するわけがないという前提に立ってもらわないと、成り立たないと思うんです。
というのも、私が学生のときに勉強した数学とか、応用数学、計算機科学と今の内容ではまったく違います。でもやっぱりそれを教えているわけです。それは学生のときに学んだことを使って教えているわけではなくて、学習して、今のことに近づけて教えているわけです。
学ぶ方も、そうだということを覚悟してもらわないといけないんだと思います。例えば、料理があって、数十年前の料理のガスコンロでグツグツと煮込んでいた料理と電子レンジで何分です、あるいは圧力をかけて5分でできますというのはまったく違うし、使える調味料だって違っている。だけど、日常生活では、家庭でそうやって料理をしている人だって、ちゃんとそういうことを学んでいるわけじゃないですか。だったら、こういう計算科学、データサイエンスに関わるもの、製造に関わるものだって、やはり製造の現場はちゃんと学ばないといけない。それは今までだって、そういう人たちは新しい技術を学んできたわけですけど、データサイエンスはちょっとそれと毛色が違っているところがあって、どうやって新しくリフレッシュして、みんな習っていけばよいのかを考えるべきなのではないかなと思いますね。
僕が言うのもなんですが、今教えていることが10年間通用するとはとても思えないんですよ。だから、10年後にまた学びなおさないといけないのだったら、そのつもりで教える方も学ぶほうもやりましょうね、というようにすれば、極めて気が楽になるんじゃないかな、という気がしてます。
司会:定期的に自分の知識をチェックしていく姿勢を身に着けておきましょうということですね。
保科:最新の論文を読むなど新しい動向にアンテナを張り、それを自分の分野にどう活かすか考えることが大切です。課題解決のためにどう理論を構築し、どういうデータを集めて、どのように理論を検証し、課題解決につなげるのか。全体のプロセスは変わりませんが、技術はどんどん進化していきますので、変化についていける基礎体力が問われます。特に学生の採用の際などには、そこをみていますね。
異分野交流のススメ
司会:そういう基礎体力を持って、横に移れるか、という話につながるか分かりませんが、マイナビニュースのテクノロジー分野で扱う話題なんかも似たようなもので10年以上前は半導体と組み込みがメインだったんですが、半導体やその製造技術がいろいろなところで使われるようになって、そうやって同じ系譜の技術が垣根を越えて横展開されていることを端からですが、見えてくるわけです。そういった意味では、企業と研究機関という経路の違う2つの組織に所属する上田さんは、まさにその体現者な気もしますけど、行き来する中でいろいろ混ざったりしないんですか?
上田:NTTは企業ですし、IPの問題がありますから、理研の取り組みと分けて、一緒にしてはないですね。
理研もNTTもAIという道具は持っているんですけど、これだけではインパクトは無いです。今でこそ、NTTも機械学習をやっていますと言っていますが、昔は、そこまで表だって持ち上げてなかったわけです。それはなぜかというと、AlphaGoとかWatsonのようなものを作っていないからですね。道具としてはすばらしいのだけど、それを活かしたものを作っていない。
よく死の谷と言われますが、これが学術の世界なら良いのです。世の中の人にわからなくても、ノーベル賞を取ったんだから、すごいことだ、と言えるわけですから。しかし、工学などの分野では、モノができないとダメということもあって、機械学習のような応用数学にアルゴリズムといっただけでは、インパクトが弱いです。それが医学や防災という分野で、使いたいと言ってくれると、成果を具現化することができるようになりWin-Winの関係になるわけです。
そういった意味では、機械学習の人たちがほかの分野の人たちと連携がしやすくなったので、良い流れになってきたと思います。ただ、ここで重要なのは言葉が全然違うということを認識しないといけない。極端なことを言うと、日本語とフランス語で会話をしているような状態になり、お互いに何を言っているのかがわからないといった状態に陥るんです。そこをやはり時間をかけて、彼らの問題としていることは何で、我々はそこにどう貢献していけるかといったコミュニケーションをうまくとらないといけない。
コミュニケーションに関しては、理研AIP(革新知能統合研究センター)のセンター長である杉山さん(東京大学 大学院新領域創成科学研究科 複雑理工学専攻 複雑システム講座 複雑計算科学分野の杉山将 教授)が、海外にも知人が多く、海外の大学とワークショップをしているのですが、ワークショップでは、一般的な自分たちの研究成果を話して終わり、ではなく、ディスカッションなんですね。適当にグループ分けをして、例えばロボットについて1時間議論をしてもらって、その結果を発表してもらうといったことをやっている。
これが直接研究成果につながるかはよく分からないんですが、コミュニケーションという自分の意見を言う、人の意見を聞く、新しいものを作る、ということにつながるのは確かだと思います。こういう活動は日本では少ないですね。
AIPの特別顧問を務めていただいている金出武雄先生も、日本の論文はつまらん、と良く仰っておられます。イントロ部分で、これこれこういうことがあるが、こういう欠点がある、それを私が非線形化するとかなんとか書いてあるんですが、新しい問題を言っていないというんです。そこには、Howに関するインプルーブ(改善)を言っているだけで、新しい問題を作ったりできていない。そういうことは欧米が強いわけです。それはなぜかと言えば、そういうディスカッションを日ごろやっていて、自分1人になってもそういう考えをめぐらせているからなんでしょう。それが新しい独創的なアイデアにつながる。
日本は改良したりするのが得意なので、ものづくりにおいては、確かに市場を押さえてこれましたが、これからのAI時代、サービスの時代になる。そうすると改良じゃダメなんです。最初に検索エンジンを作ったGoogleがすごくて、あるいは最初にFacebookを作ったのが良くて、二番煎じじゃもうダメなんですよね。だから、やはり異分野とディスカッションしていくということが、結果的に良い結果を生み出していくと思うわけです。
保科:アクセンチュア・イノベーション・ハブ東京では、異分野ディスカッションに積極的に取り組んでいます。さきほどもお話しましたが、ワークショップにはデータサイエンティストとデザイナーが共に参加します。そこに、業界の専門知識を持ったコンサルタントと課題を持ったお客様が加わり、一緒にプロジェクトに取り組みます。目の前に見えている表層的な課題では無く、そもそもの根本的な課題は何なのかを洗い出し、皆で議論を重ね、実験的な取り組みも交えながら課題解決を目指しています。
司会:そもそも論の課題は何か、ということは往々にして忘れやすくて、よく小手先の技術にこだわった話になったりしますよね。
保科:はい。製品や技術の話が先行しがちですが、まずはお客様の課題は何か定義する必要がありますね。
真に生き残るサービスを考えるには、目の前に見えている課題よりも、5年後、10年後の社会課題について様々な分野の人たちと話し、考えることが有効でしょう。決して答えがあるわけではありませんが、そういうことを考えながら、今の自分の持てる強み、例えば今所属している会社の強みを活かして、どうサービスを作ったらよいのか考え続けることが重要です。そして考えるだけでなく、足りないところは様々な分野の方々とお互いの得意分野を組み合わせながら実際にサービス作りを行い、上手く行かなればどんどん次の手を打っていくことです。
藤原:自分自身の経験で恐縮なんですが、東大から7年くらい筑波大学に行ったんです。東大では物理工学で、物性物理だけのグループだったんですが、筑波大に行って、物質工学系というところに職を得たんですけど、これは物性物理はもちろんですが、金属工学、電子工学、応用化学、白川先生(白川英樹 現 筑波大学 名誉教授。2000年にノーベル化学賞を受賞)と同じところだったんですけど、それから生命科学、みんな同じところに入っているわけです。
いわば、強制的に異分野交流をさせられていたわけです。これは非常に私にとって、自分の分野を広げる意味で役に立ったし、結構嘘も吹きこまれもしました。異分野だったので何を言われても、みんな本当に聞こえてくるところがあって、声が大きい方が勝ってしまうという風土を経験したわけですね。でもやはり、異分野交流という経験は、自分の分野を広げるのにものすごく役に立ちましたね。
現在、私は数理科学の分野に居るわけですが、物理と比べて、例えば理論物理についてもずいぶんと言葉が違うわけです。それから発想も違う。そういうところで、もちろん、数学そのものを議論しているわけではないですが、かなり色々、そういう人たちから学んでいるというのがあります。
ただ、だからといって、学生にいきなり異分野交流をさせよ、というのはあまり感心しない。専門をきっちりと勉強しなさいというのが先です。本来、きちっと専門を持つべきで、きちっとした専門を持ってもらって、その後に異分野交流などをかなり強制的にやった方が良いと思っています。すべての目的に対して、それは正しいんじゃないかなと感じますね。
保科: アクセンチュアでは、色々な分野の博士を採用しているとお話しましたが、分野は何であれ1つの領域をしっかりと理解し、自身の力で研究を遂行した、という博士課程ならではの経験を評価しています。しっかりと自身の専門分野を持ったうえで、他の領域にも興味を持ち、他分野でも自身の知見を活かせる幅広さのある人材が、アカデミックだけではなく、ビジネスにも有用だと思います。
藤原:そういう意味だと、異分野の人とコミュニケーションできるという能力が結局は一番必要という感じがしますね。応用数学の人と、物性、計算をする人が会ったときに、やはり言葉が違う。ほとんど重なっているはずなのに、お互いに言葉が通じないということを非常に経験しましたね。