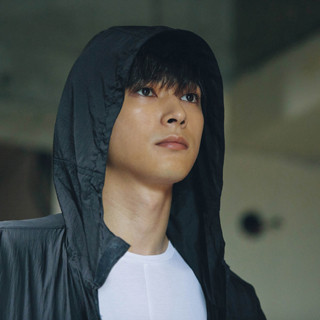異常に多かった打ち合わせ
――ドラマ24の枠に出演することを、喜んでくれる俳優さんもいたと思いますが。
おかげさまで。特に第1話「裸で誘拐された男」の神保さんは、ほぼ全編、全裸でスーツケースに入っている役なので不安でしたが、嬉々として演じて下さいましたね。逆に第2話「違法風俗店の男」の光石(研)さんは、「川栄ちゃんに裸見られるの恥ずかしいなー」ってしきりに言ってました(笑)。
――光石さん、『バイプレイヤーズ』でお話を聞いたときから、オフのエピソードがかわいらしいですよね。神保さんといい、光石さんといい、1話、2話と裸が続きましたが、それは偶然なんですか?
偶然です。ただ、第3話「夫が女装する女」でも野間口(徹)さんが下着姿になりますし、第6話「未来から来た男」でも佐藤二朗さんが全裸になりますし……けっこう裸ありましたね。光石さんと野間口さんは下着姿、神保さんも肌色の下着で撮影でしたけど、佐藤さんの撮影はド全裸で前貼りでした(笑)。佐藤さんは、メイキングのカメラに「お父さんの仕事はこれなんだぞ」と息子さんへのメッセージを発してました (笑)。
――もともとは下北沢を舞台にするのではなく、すすきのを舞台にした「すすきのダイハード」を考えていたそうですね。
風俗ビルの立てこもり事件を描く単発ドラマなんですが……。でも、この企画はテレ東とはいえ通らないなと思いました。スペシャルドラマとしてはマニアックだし、全編風俗ビルのワンシチュエーションっていうのも……。でも気に入っていたので、ドラマ24用に書き直しました。ワンシチュエーションパニックというテーマを残し、しかも小劇場の劇作家が競作するオムニバスドラマ。テレビの外の新しい才能を登用できるメリットもあるので、興味を持ってくれるんじゃないかと思ったんです。
――プロデューサーとして11話を詰めていくのは大変だったのでは?
脚本の打ち合わせの本数は異常に多かったですね。普通のドラマって数カ月前から準備して、第1話はすごい時間をかけて打ち合わせを重ねるけど、最終話のころには撮影が迫ってて、5日くらいで書いてるなんてことも。最初のころの丁寧さはどこに行ったんだって(笑)。今回のように、一人の作家さんが1本しか書かないのであれば、数カ月間、その1本のためだけに納得いくまで打ち合わせすることができます。もちろん、すんなり脱稿した方もいらっしゃいます。
映像作家との化学反応
――11人の劇作家さんがいましたが、何か印象に残るやりとりはありましたか?
細川(徹)さんは、「俺はコント作家なのに劇作家のくくりに入っていいのかな」なんて言われてましたね。でも、身も蓋もないピンチを書くのはさすがでしたね。あと、サンプルの松井さんは「普段は何も起こらないことを面白がる演劇をやっていたけど、今回は何かが起こることが求められるから、それが大変であり、新鮮でもあった」という話をされていました。
――今回、「身も蓋もないピンチにあう」という、共通の「しばり」があるわけですが、劇作家さんにとっては新鮮なのではないでしょうか。
劇作家の方って自身に書きたいテーマがあると思うので、テレビのプロデューサーから、こういうテーマで書いて下さいって言われることって稀だと思うんですよ。でも、皆さん面白がってくれてました。松井さんの「所詮、一人の作家に書けるテーマなんて一つしかなくて、それをいろんな角度からやってるんです」というお話が印象的で。松井さんのテーマは「自分という人間の中の変容」のようなもので。最初から女装を書くって決めてましたね。皆さんの得意なテーマに『下北沢ダイハード』という企画をぶつけていった感覚です。
――第3話「夫が女装する女」の最後のオチに意外性があってジーンときました。一話、一話、テイストが違っていたけれど、第9話の「幽体離脱した男」は、今、若手の俳優さんたちが、小劇場の舞台にどんどん出ているという実際の状況と、すごくリンクしていると思いました。この作品も優しい結末でしたね。
ロロの三浦(直之)さんも、僕の企画趣旨を聞いて、いろいろなピンチを考えてくださったんですけど、三浦さんが本来やりたいことに立ち帰ろうということになりまして。それがボーイミーツガールだったんで、あの形にたどり着きました。
――今回、映像を担当するのが、3人のミュージック・ビデオの監督だったということですが、それはどういう狙いだったのででしょうか。
コミカルな要素を映像にできる人として関(和亮)さんにぜひお願いしたいと思いました。もともと関さんのミュージック・ビデオが好きだったし、他局のスペシャルドラマもよかったし。そこから企画の打ち合わせを重ねるうちに、だったら「劇作家×映像作家」という打ち出しで、普段テレビを作っていない人同士の化学反応が面白いんじゃないかと思い至り、MVで活躍する映像ディレクターさんにお願いする事になりました。
――実際に劇作家と映像作家の組み合わせでやってみてどんな化学反応がありましたか?
今回は作家性の強い劇作家陣の世界を映像に落とし込む企画だと思うんです。その点で、ミュージック・ビデオの監督は、ミュージシャンの作った詞や曲の世界をどう映像に落とし込むかというのが仕事の根底にあるので、うってつけだったなと。関さんは画がストーリーを邪魔しちゃいけないんじゃないか、どうやったらストーリーが見やすくなるのかってことに重きを置いたとおっしゃっていたので、すごく俯瞰で見ているんだなと思いました。
――この企画、実際にやられてみていかがでしたか?
11話のドラマを、一からキャスティング、一からロケハン、一から脚本打ち合わせしないといけなかったので、毎回スペシャルドラマを作っているみたいでした。現場の方からも「俺たちがダイハードだったよ」って言われました(笑)。オリジナルでオムニバスの深夜ドラマなんてなかなかないので、出演者や作り手がこういう企画に楽しんで参加してくれるという自信はあったんですが、視聴者にもこの変わった取り組みをちゃんと面白がってくれる人がいる、と感じられたことが良かったですね。
そして、ずっと好きだった小劇場で活躍する人たちをフックアップできたことも嬉しかったです。個人的な野望としては、このドラマが実現したことによって、元ネタの「すすきのダイハード」も何かしら着地すればいいなと思っています(笑)。
<著者プロフィール>
西森路代
ライター。地方のOLを経て上京。派遣社員、編集プロダクション勤務を経てフリーに。香港、台湾、韓国、日本などアジアのエンターテイメントと、女性の生き方について執筆中。現在、TBS RADIO「文化系トーラジオLIFE」にも出演中。著書に『K-POPがアジアを制覇する』(原書房)、共著に『女子会2.0』(NHK出版)などがある。