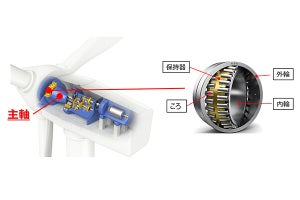――多岐にわたる応募作に通底する選出基準というのはあるのでしょうか?
永井 : デザインとして評価できるのか、ということが最終的には重要ですね。コトや仕組みのデザインにおいても、デザインとして評価できるのかという観点は、常に大事にしています。
柴田 : 全体の方向性はフォーカス・イシューなどで審査委員長が示して、それを受けて各グループの中でジャッジをしていきます。そこでなにか問題があったり、議論が必要なものは、皆で意見を出し合います。
――やりとりの多いジャンルなどの傾向はありますか?
柴田 : やはり、以前から応募の多かった工業製品などよりは、新しいものの方が評価の蓄積が少ないので、いい意味で議論が活発になりやすいです。
また、今年の傾向として、スタイリングだけでない新しさを持つ応募作がいくつか見られました。いわゆるモデルチェンジではない、本質的な変化があった感覚です。
――本質的な変化とは、具体的にどういった変化を指すのでしょうか?
柴田 : グッドデザイン賞はエントリーされた製品を実際に触ったり使ったりして審査をします。だからこそ言えることなのですが、見た目の変化は極端ではないのに、使い心地や体験が驚くほど変わっているものがいくつかありました。
見た目にすごくかたちが変わったというデザインよりは、一見すると見た目の変化は見られない。写真だけで見たら、何が変わったのかわからないようなものに、触ってみてはじめてわかる変化があったということです。
――いわゆるUX/UIの部分でしょうか?
柴田 : はい。そういう部分ですとか、質感や使用感ですね。たとえば学生服が出品されていて、見た目は既存のものと変わらないけれど、伸縮性があったり、一見何の変哲もないペンだけれど、書いてみると驚くほどの使い心地の変化があったりだとか。カタチで差別化というより、実際のデザインに関わったその後の体験だとか、使ったあとの気持ちを重視した応募作が多かったように感じられました。