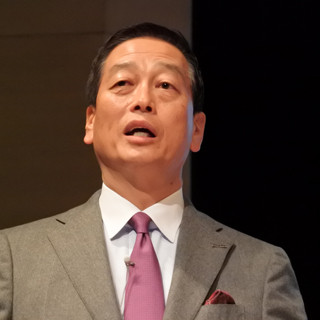朝日新聞社は2月20日、「『女性にやさしい』その先へ! 」と題したフォーラムを開催。前編では、資生堂の魚谷雅彦社長が、同社の働き方改革について語った内容をお伝えした。フォーラムの後半では、「『育休世代』のジレンマ 女性活用はなぜ失敗するのか? 」の著者であるジャーナリストの中野円佳さんら6人が議論を展開。今回は、彼女らが時短勤務中の子育て社員にも遅番や土日勤務などに取り組んでもらう資生堂の制度改革、いわゆる「資生堂ショック」について語った内容を紹介する。
|
|
左からジャーナリストの中野円佳さん、みずほフィナンシャルグループダイバーシティ推進室長の五十嵐伊津子さん、21世紀職業財団会長の岩田喜美枝さん、日本女子大学人間社会学部教授の大沢真知子さん、セブン&アイグループダイバーシティ推進プロジェクトリーダーの藤本圭子さん、NPO法人ファザーリング・ジャパン理事で、三井物産ロジスティクス・パートナーズ代表取締役の川島高之さん |
「キャリアアップもできる社会」という時代の転換点にいる
――「資生堂ショック」にまつわる社会現象についてどのように考えますか
中野さん: 日本の企業で行われてきたのは、多くが女性に対しての仕事と育児の「両立支援」だったと思うのですが、やっと「均等支援」に焦点があたってきたなという印象を持ちました。
私は現在、生後3カ月の子どもがいて会社員としては育休中です。でもそこで、例えば今回のフォーラムの参加打診についても、「中野さんは産後間もないから参加できないのではないか」と考えられるのは、過剰な配慮なんですね。とりたいチャンスはとりたいです。
今日は子どもを夫とベビーシッターに任せています。そしてベビーシッター代は会社が出してくれているのですが、そういう形で支援をしてもらえたらキャリアアップを実現することができる。一律に「両立支援」だけを進めるという段階から、「均等推進」を考える段階にきているということだと思います。
岩田さん: 最初の「ショック」という言葉の使われ方は、女性に優しい資生堂が優しくなくなった、女性活躍が後退したことに、働く女性たちがショックを受けたというリアクションだったと思います。しかし女性活躍において先進的な企業であれば、これはいつかどこかで必ず直面する問題の1つです。
これまで両立支援のために、社員の仕事を免除して育休なり時短なりを取り入れてきた。しかし今回のことは、社員をシフト勤務から外すやり方がうまくいかないと気がつき、その対策を打ったということです。では別の企業ではどうするのか、そのことを世の中に問うているというのが本質的な「ショック」の意味なのではないでしょうか。
大沢さん: 私は米国の女性の生き方が大きく変化した1975年から1987年まで、アメリカで生活していました。そこで感じたのは、アメリカの女性活躍ははじめに「アファーマティブアクション」があってその後、「ダイバーシティ」の方向に大きくシフトしていったということです。
その中で、「ワークライフバランス」という概念が生まれてくるのですが、それで何が起こったかというと、男性が変わります。男性の家庭進出が起きて、女性の社会進出が可能になる。これが、今欧米を中心に巻き起こっているジェンダー革命と呼ばれるものです。
しかし日本では、女性の活躍が「アファーマティブアクション」でなく、「両立支援」から始まっていきました。なぜかというと、日本では「会社が社員を育てる」という考えで社員に投資をしているので、女性がどれだけ定着してくれるかが大きな関心だったからです。その結果、全体的に見るとまだまだ離職率は高いのですが、正社員の女性の継続率は高まってきている。では次の段階に行こうよという機運になっていると思います。子どもをうみ育て、さらにキャリアアップもできる社会を作ろうよ、という時代の転換点に来ていると思いました。
藤本さん: 端的に言うと、言葉だけが一人歩きしているという印象がありました。両立支援が職場関係に支障をきたしていたとしたら、それは現場でのコミュニケーション不足が問題です。時短で働いている人たちというのは全ての人が早く帰ることに対して負い目を感じていると共に、周囲への感謝の気持ちも持っています。この「感謝の気持ち」を土日出勤やノルマを達成するなどの「覚悟」へ変えていくのはマネジメント側の責任なのです。
これらの負荷を克服するには、日頃から自分が期待されているとか、評価されているという実感がないとうまれてこない。常日頃からタイミングよく、上司あるいは管理職がメッセージを出し続けることによって、覚悟が醸成されていくのではないかと思っています。