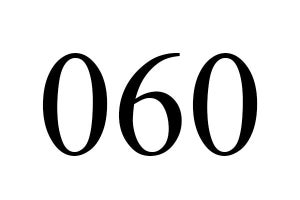田中社長はこうしたUIについて、「指で触れる度にさまざまな表情を見せる。今の自分をアップデートすることで変化する感覚に近しい感じ」を目指したもので、「本当の意味でのinfo.barができた」と胸を張る。
HTCとコラボレーションしたハードウェアとなるため、スペック的には2012年冬モデルの「HTC J butterfly」とほぼ同等。ディスプレイは4.7インチHD液晶だが、レンズなどのカメラスペック、クアッドコプロセッサ、LTEの対応などは同様のスペックとなる。ホーム画面のiida UI以外の部分も、HTC J butterflyと同じだ。
「"選べる自由"のもう1つの新しい選択肢」がINFOBAR A02であり、田中社長は、これが今年のauの目指す方向性の「ティザー」「触り」と今後の展開を示唆する。春モデルは、INFOBAR A02の1機種だけでなく、4月までに端末を含めた「いろんな発表をしたい」(田中社長)と明らかにしている。
なお、INFOBARはこれまでシャープが製造していたが、田中社長は「やりたいことを実現できるメーカーを選んだ。ほとんど中身は当社がやっている」と話す。メーカーの変更について、大きな理由はないとしている。
最中ではなく羊羹(ようかん)
INFOBAR A02は、プロダクトデザイナーとして深澤直人氏、インタフェースデザイナーとして中村勇吾氏、サウンドデザイナーとして小山田圭吾氏を起用。外観とUIの一体感のために、「力強くパートナーを組んでやろうとした」(深澤氏)という。
KDDI プロダクト企画本部プロダクト企画1部の砂原哲氏によれば、スマートフォン版INFOBARは、「スマートフォンとフィーチャーフォンのいいとこ取りをしようとした」ため、コンパクトなボディで、フィーチャーフォンライクなスマートフォンを作ろうとしていたという。
今回は、「写真や音楽、動画、電子書籍、SNSといったスマートフォンならではのサービスを、普通の人にもより使いやすく」という観点からデザイン。その結果がINFOBAR A02だという。また、バッテリの持続時間やパフォーマンス、ストラップホールなどといった従来機の不満点の解消も図った。
砂原氏は、「デザインコンセプトはハードウェアとソフトウェア、プロダクトとユーザーインタフェースをいかに同調させるか、いかに1つの塊として作ることができるか」といったことを考えてデザインしたという。深澤氏は、従来のデザインが「最中(の皮)と(その中身の)あんこで、内側(UI)と外側(外観)を別々にデザインして組み合わせた」ものだが、今回は「羊羹(ようかん)」と表現する。
この羊羹というのは、「"外見と中身"というより、"中身"だけ。その中身の味や感触も一体にデザインしようとした」ことの比喩で、そのために、デザイナー同士も一緒になって開発をしたという。
今までのINFOBARでは、タイル状のキーを用意して一体感を表現していたそうだが、Android OSがハードキーを排除していく中で、側面のファンクションキーを新設し、片手操作を容易にする工夫を加えた。こうした点は「今までのINFOBAR色を盛り込んだ」(深澤氏)という。
|
|
|
|
側面のボリュームキーの右側にあるのがファンクションキー。電子書籍や音楽などに素早くアクセスできる「List View」にアクセスできるほか、着信、終話、画面オンなどの機能がある。ちなみに、このボタンサイズとパネルのサイズは一致しており、この辺りも一体感を出しているそうだ |
|
UI側からは、ホーム画面のスクロールでパネルが柔らかい物体のように動くという効果を追加している。これは、「UIの中に新しい感覚や質感を立ち上げたかった」と中村氏は言う。中村氏によれば、「ゼリーの物理的な挙動をシミュレートするプログラムというかアルゴリズム」を組み込んだことで、「物理的な質感を持っている」というUIに仕上げた。ハードウェアの素材や肌触りによる質感だけでなく、「アルゴリズムで質感を出そうとした」という意図を中村氏は説明する。
さらに、パネルにさまざまな情報を表示できるようにしたことで、ユーザーごとのUIになるという点から、砂原氏は「コンテンツが表に出ていること、それを使ってさまざまな表情を出せること、それで自己表現ができること、そのため、非常に愛着が持てる」端末だとアピール。中村氏も「自分でデザインするスマートフォン」とUIの特徴を話す。
サウンドに関しては、インドネシア・バリ島の伝統楽器ガムランボールを深澤氏が聴いて、「多層な音が入り込んでいて奥行きがあった」ことから、これがインタフェースと連動するのではないか、という発想から採り入れたという。
これを担当したのがソロユニット「コーネリアス」としても活動するミュージシャンの小山田圭吾氏。「新しいスマートフォンの音の姿」という「高い球」(中村氏)が投げかけられ、これに小山田氏が応えたという。着信音や目覚ましの音など、トータルでのデザインに加え、ホーム画面のパネルに6つの音をランダムに割り当て、パネルを移動させてほかのパネルに触れると音が重なり合う、という仕組みを採用した。
これによって、「音と動きと全体が塊となって、1つの世界を作り込んでいる」(中村氏)。深澤氏は、見て、触れて、聴いてといった具合に「五感で全部吸収できるようなものになっている」と話す。
田中社長は、こうしてできあがったINFOBAR A02が、「10年前にやろうと思っていたことがここまできた」と強調。深澤氏は、「こんなに高い完成度のものができるという、長年夢見ていたイメージが実現した」とアピールする。砂原氏は、「手に持ってもらわないと魅力が伝わりにくい」としつつ、従来のINFOBARユーザーだけでなく、多くの人に使ってもらいたい端末に仕上がっている、と自信を見せている。
(記事提供: AndroWire編集部)