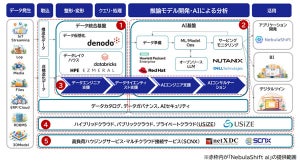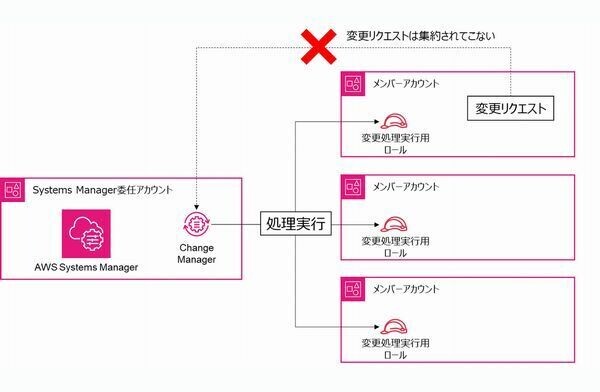オンプレミスとクラウドの比較
では、中小企業のIT管理者は今、オンプレミスとクラウドのどちらを選ぶべきなのか。
残念ながら、その答えはケースバイケースで、端的な解を出すことはできない。各種のメリットやリスク、コスト、利用シーンなどを考慮しながら、自社にどちらが合うのかを選ぶほかない。また、現在は、クラウド技術発展の過渡期にあり、今後数年間でシステムの常識が様変わりする可能性もある。そういった将来性も考慮しなければならないので、選択はさらに難しい。
ただし、明確な答えは出せないが、ある程度の指針を示すことはできる。以下、オンプレミス向けの技術とクラウド向けの技術の双方を提供しているマイクロソフトの話も交えながら参考情報を紹介しよう。
コストの比較 - 数字に表れない"管理コスト"もポイント
中小企業にとって最大の関心事はやはりコストだろう。
月額課金形態で提供されるクラウドに対して、オンプレミスはハードウェアやソフトウェアを買い切って運用するかたちになる。したがって、オンプレミスでは初期費用が嵩むものの、長い目で見ると、毎月料金を払い続けるクラウドよりもトータルコストが低くなる可能性もある。
では、どのくらいの期間使い続けると、クラウドのコストがオンプレミスを超えるのか。
|
|
|
日本マイクロソフト デベロッパー&プラットフォーム統括本部 クラウドプラットフォーム推進部 エバンジェリストの安納順一氏 |
オンプレミスでもハードウェアやソフトウェアのサポート費用がかかるし、クラウドは従量課金サービスが多いのでユーザー数やデータ量によって費用は大きく変わってくるため、一概には言えないが、マイクロソフトの中小企業向け試算では、「Windows Azureを利用した場合、5年間使い続けてもオンプレミスの3割強程度で収まる」(日本マイクロソフト デベロッパー&プラットフォーム統括本部 クラウドプラットフォーム推進部 エバンジェリストの安納順一氏)という。
しかも、クラウドの場合、主な管理作業をサービス事業者にすべて任せられるので、管理工数を大幅に削減できる。この管理コストは人件費に反映される数字で、直接のコストとして換算されるケースは少ないが、トータルコストの中では大きな割合を占める。専任のシステム管理者を置けない中小企業の場合、作業は決して早くはないだろうから、影響はさらに大きいはずだ。
中小企業ではSaaSが有力、ただしニーズに合うかが問題
管理業務のことを考慮すると、中小企業においては、IaaSよりもPaaS、PaaSよりもSaaSのほうが有力な選択肢と言える。特に、IaaSに関しては、OSや仮想化、ネットワークなどのインフラ知識が必要になるため、ある程度のスキルを持った管理者でなければ対応が難しい。選択肢から外さざるをえない企業も少なからずあるだろう。
管理業務を重視すると、本命は、システム面の管理業務のことをほとんど意識する必要がないSaaSになる。ただし、SaaSに関しては、当然ながら、ユーザー側の要望に合ったサービスが提供されていないと導入できない。メールシステムやスケジュール管理、会計システム、CRMなど、多様なサービスが提供されているが、例えば、セキュリティ要件が合わなかったり、ユーザーのアクセス制御が想定どおりにできなかったり、といった細かいニーズの不一致はよくある話だ。SaaSの導入でも、通常のシステムと同様、事前にしっかりと要件を整理してから検討を進める必要がある。
クラウドの不安点 - パフォーマンス、セキュリティ、システム連携
ここまでクラウドの利点ばかりが目立っている印象があるが、クラウドにも問題がないわけではない。例えば、パフォーマンスである。昨今のネットワーク環境は高速になったものの、クラウドでは遠隔地のサーバにアクセスすることになるため、オフィス内に設置されたサーバに比べると確実に遅くなる。海外にサーバがあるようなサービスでは、レスポンスが秒単位になるケースもあるだろう。大手企業のサービスの中には、データをキャッシュするサーバを国内に設置して高速化を実現しているものも多いが、念のため、事前にチェックしておくべきである。
また、クラウドと切っても切り離せないのがデータ損失/流出のリスクだ。自社のサーバであればさまざまな手立てをとれるが、外部のサーバとなるとできることは限られる。大手企業のサービスは、世界各地のデータセンターにデータを複製して保持しているうえ、最新のセキュリティ技術を導入しているため、実際には社内のシステムよりもリスクが低いと言えるが、外部に機密情報を置くのは不安との理由から、高度の機密情報を扱うシステムでは敬遠するケースも多い。
そのほか、SaaSに関しては、システム連携が必要になった際の制約が多いという点も頭に入れておくべきだろう。自由にいじれる環境ではないので、サービス事業者が提供するAPIを介して連携することになるが、どこまでのことができるのかを事前に調べておく必要がある。