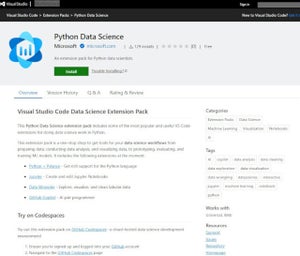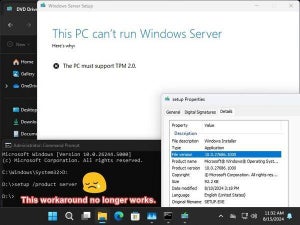はじめに
NTTデータ先端技術株式会社にてアジャイル開発並びに技術調査業務に従事している志田です。私はアプリケーションエンジニアとしてJavaを利用したミドルウェア開発からキャリアをスタートし、紆余曲折を経て今ではインフラ6割、アプリケーション4割くらいの配分で業務を行っております。キャリアの中ではデータセンターの設計のために耐荷重計算をするといった業務から、3Dのバーチャルショッピングモールの実現検討であったり、はたまた自社開発プロダクトの営業として動いたりと様々な経験をしてきました。
これまではアプリケーション開発とインフラ構築は境目がはっきりしており、担当のエンジニアはどちらかを知っていればプロジェクトが遂行できていました。様々な技術革新によって少数のエンジニアがシステム全体を統制することができるようになりました。たとえばクラウド技術によってハードウェアを設置することなくサービスの提供が可能になるといった変化が起こりました。このため、システムエンジニアの担当も明確にアプリケーション開発、インフラ構築と分離することなく一人の担当でシステム構築の最初から最後まで対応するといったことは珍しくありません。同様にシステムエンジニアに対する要求もインフラの準備からアプリケーションの開発、運用まで全てを一つの組織に依頼するといったことも増えてきました。このことから、システムに関わるライフサイクルの全てに対応できるエンジニアとしてフルスタックエンジニアという言葉も生まれてきました。
私自身もアプリケーションエンジニアからインフラエンジニアにキャリアチェンジをした経験があり、ある意味フルスタックエンジニアと呼べなくもないと感じています。ただ、それがエンジニアとしての最終のゴールなのか、理想のエンジニア像なのかといった点は甚だ疑問であり、本連載では過去の経験や現在、そして未来の動向からエンジニアとしての理想像はなんなのか、そして理想に近づくためにどのようなことをしていくべきなのかについて考えていきます。
DXとデジタル人材
現在、世の中はDX推進をキーワードにエンジニアに対する要求が高まってきています。DX推進にて掲げるデジタル人材というエンジニア像は現在人材不足が声高に叫ばれています。IPAにて定義されているデジタル人材のタイプとその充足状況は下図の通りです。
参考元:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)https://www.ipa.go.jp/
・デジタル・トランスフォーメーション推進人材の機能と役割のあり方に関する調査(Copyright 2019 IPA)
・参考日:2022年9月30日(金)
現実世界での問題をデジタルの問題に落とし込んでいくプロデューサーやビジネスデザイナーといった役割もありますが、システムの全体的なデザインを行うアーキテクトやエンジニア/プログラマといった役割もDX推進という観点では概ね不足しているという認識を持たれています。国内のIT技術者は122万人と言われ決して少なくない人数ですが、多くの企業はデジタル人材不足を感じており、DX人材として定義されているエンジニア像と現状のIT技術者の間にギャップがあると考えられます。
デジタル人材に関しては明確にこれが出来ればデジタル人材と定義するものや、デジタル人材認定証といったものはありませんが、一般的に「最新技術を活用して組織を成長へと導く人材」と言われています。以下の例は経済産業省にてDXを推進するにあたって必要な開発手法・技術について整理したものです。すでにインフラ、アプリケーションの垣根なく様々な技術要素が混在しているのがわかります。DX人材とは、これらの技術に対して知見を持ち、かつビジネスマインドを持った人材というのがDX人材という言葉から想起される人材像になると考えられます。
参考元:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)https://www.ipa.go.jp/
・DX白書2021 第4部 DXを支える手法と技術(Copyright 2021 IPA)
・参考日:2022年9月30日(金)
DX需要は高まっていきつつも現在組織・企業が求めるようなデジタル人材は揃えることができず、DXが停滞するといった状況は今後何年か継続していくと考えられます。その中で、恐らくエンジニア側でも二極化が進んでいくのではないかと予想しています。一つは専門の技術領域を持ち、その技術だけで組織に貢献できるエキスパート・エンジニアです。現在のAI技術者やデータサイエンティストはこのエキスパートに属するものとなります。もう一方は技術全般を把握しているが特定の専門領域を持たないジェネラリストです。私見ですが、今一般的に言われているフルスタックエンジニアは、エキスパート/ジェネラリストと分類した際のジェネラリストを指す言葉になっているのではないかと思います。
理想のエンジニア像 = エキスパート + ジェネラリスト
前章で二極化すると書きましたが、二極化することのデメリットはコミュニケーションの断絶が発生してしまうことにあります。ある課題を解決する際に特定技術を掘り上げているエキスパートは自身の専門領域外の課題に関しては対応が難しく、広く把握しているだけのジェネラリストでは上手く問題が解決できない可能性があります。
理想のエンジニア像とは特定の分野に依存せず、広く専門領域を持ったエキスパートとジェネラリストの融合形ではないかと考えています。エキスパート/ジェネラリストと分離せず両方の特性を持ったエンジニアこそを目指すべきだと考えています。この両方の特性を持ったエンジニアが自然発生的に生まれるのであれば昨今のDX人材の不足などは起こっておらず、日々普通に業務を遂行するだけではなかなかこの理想のエンジニアになることは難しいでしょう。
理想のエンジニアに近づいていく第一歩は自身の専門でない、得意でない技術領域のエンジニアとコミュケーションを取っていくことで、これが重要だと考えています。コミュニケーションが重要になるという部分は、エンジニアは何の為に働くか、何に喜びを覚えるかと密接に関係しています。もちろん業務だから、稼がなくてはならないから、も重要なモチベーションですがエンジニアの多くは知的好奇心を満たすということもモチベーションに繋がっていきます。その中で他の技術領域の専門家と話すという行為は知的好奇心を満たしやすい行為になり、自然とモチベーションも高まっていきます。
このエキスパートとして専門を持ちつつ、他の専門家と意見交換できるというエンジニア像はITだけでなく顧客との関係もそうあるべき、と考えています。以前ある製造業の顧客と一緒に新しい実験システムを開発する案件がありました。顧客は自分達の持っている製品に関して誰よりも詳しく、誇りを持っていました。これに対して我々も先進のIT技術に関しての知識に誇りを持ち、顧客要望を叶える技術提案を日夜ぶつけ合って議論するというプロジェクトでした。お互いが専門領域を持ち、その専門領域を融合することで新しい価値を作り出すという、DX推進と言っても差し支えないプロジェクトでした。
どうやって理想のエンジニアに近づいていくのか
他の技術領域のエンジニアとのコミュニケーションを活発に行うだけで上記の理想のエンジニアになれるかというと、それだけでは難しいと考えております。重要なのは未知の領域の技術にどうやってアプローチしていくかになります。本連載では、過去の経験、実例から未知の領域に対してどういったマインドでどのように取り組んでいったかを提示していきたいと思います。未知の領域は水平領域(たとえば、様々なアプリ系技術に精通しているなど)と垂直領域(ビジネス、アプリからインフラ、運用まで)それぞれに対して指します。
もしこの記事を読んでいる方でまだご自身の成長のプロセスがハッキリとしていない方がいれば、当方としてはまず何かの技術領域でのエキスパートを目指すことをお勧めします。なぜならどのような技術でも技術的普遍性とでも言うべき共通項を持ちます。どのような技術、プロダクトでもそれが生まれた背景にはある課題があり、それを解決する方法、改善する方法として技術やプロダクトがあります。往々にしてその解決されるべき課題はパフォーマンスの問題であったり、非効率であったり複雑である、面倒である、人間が直感的に理解しにくいなど技術に依らず非常に人間的な問題である事がほとんどです。このため、技術要素に様々な差異はあれ、解決したい課題は共通で理解できる事が多いため一つの専門知識、経験を持つことで他の技術領域の習得は時間がかからないことが多いと言えます。
最も効率の良い育成方法はトラブルシューティングを実施し、問題の検出から解決までを経験する事です。クラウド技術の普及によりアプケーションとインフラの境目がなくなって来ている今でこそ、トラブルの解決にはアプリケーションの知識だけでなくインフラからセキュリティまでありとあらゆる知識を総動員して解決にあたる必要が出て来ています。ただ、トラブル自体は狙って起こせることではなく、またできる限り遠慮したい業務ではありますので、次善策として技術的引き出しを増やしていくことが挙げられます。技術的引き出しを増やすことによって、さまざまな技術要素での専門家とコミュニケーションが取れるようになり、エキスパート同士のコミュニケーションを活性化することで理想的なエンジニアに近づいていきます。
本連載では技術的引き出しを増やしていくために様々な技術領域について過去、現在、そして未来の動向を説明していきます。本連載記事を読んでいただき、ご自身の引き出しを 増やすことを支援できれば何よりです。
※本記事はエヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社から提供を受けております。著作権は同社に帰属します。
[PR]提供:エヌ・ティ・ティ・データ先端技術