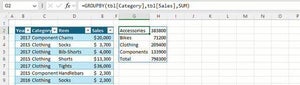ミロ・ジャパンが提供し、日立ソリューションズが販売するチームの共同作業を支援するビジュアルコラボレーションプラットフォーム「Miro」。世界ではすでに3,500万を超える利用者数を誇り、日本でも70万人のユーザーを獲得している。
Miroが実現する新しい働き方とはどういうものなのか。そして企業にどのような価値をもたらすのか。ミロ・ジャパン 代表執行役社長の五十嵐光喜氏、日立ソリューションズ シニアエバンジェリストの松本匡孝氏の対談から探っていきたい。
-
左:ミロ・ジャパン合同会社 代表執行役社長 五十嵐 光喜 氏
右:株式会社日立ソリューションズ シニアエバンジェリスト 松本 匡孝 氏
五十嵐氏が語る「Miro」の魅力
──まずはMiroの特徴について伺いたいと思います。五十嵐さんから見て、Miroとはどのようなツールですか?
五十嵐: みなさんは業務改善や課題解決、新しいサービスの開発などをする際、日々頭の中で考えを巡らせていると思います。しかし、頭の中から何かに落としこまないとその先には進めません。それはアナログな時代では紙だったり、デジタルな時代ではPowerPointであったりしました。
ただ紙やPowerPointは、スペース、字数、スライドなどツールによる制限があり、どうしても志向が切り替わるタイミングが発生してしまいます。この制限を解放したのが「Miro」です。Miroはいわば"広大な模造紙"であり、自由にアイデアを落とし込んでいけるツールといえるでしょう。
──"広大な模造紙"という表現は非常にわかりやすく感じました。ですが、Miroでできることはそれだけに限らないと感じます。
五十嵐: はい。どんなに優れた方でも、一人で考えることには限界があります。多種多様な人の考えが入り交じるからこそ、世の中に良いものが生まれていくわけです。30~40年前に世界を席巻した日本企業の強さの要因は、ワイワイガヤガヤと意見をぶつけあっていたことにもあると思います。Miroは、これを再現したプラットフォームと言えます。
-
ミロ・ジャパン 代表執行役社長 五十嵐 光喜 氏
──それでは、五十嵐さんから見てMiroの最大の特徴とは?
五十嵐: Miroは10年以上前に創業し、お客様と対話しながらブラッシュアップを続けています。その知見を凝縮したのが、"使いやすさ"です。
たとえば自動車は、スペックが似通っていても乗り心地はそれぞれ異なりますよね。培われたナレッジが詰め込まれているからです。ビジネスサイズでなにかを買うときはスペックで比べがちですが、車は乗り心地やハンドリングを見ますよね。Miroも同じで、全従業員が使うものだからこそ、初めてMiroを使う人も思いのまま使いこなせるよう、操作性の高さを追求しています。
さらに、操作性だけではなく、ベストプラクティスを形にするために1,000を超える豊富なテンプレートを用意しており、他のツールとの連携も可能です。しかしやはり土台にあるのは"使いやすさ"と言えるでしょう。
──近年、働き方改革やDX(デジタルトランスフォーメーション:Digital Transformation)、コロナ禍といったキーワードがあるなかで、Miroは企業にどのような利益をもたらすのでしょうか?
五十嵐: 1つ目は社員のエンゲージメントです。現在のハイブリッドワークにおける会議では、会議室に集まった人とリモートで繋がっている人がいます。すると、議論の主戦場は会議室になり、リモートの人はオブザーバーやコメンテーターになってしまいます。これでは、エンゲージメントは下がってしまいますので、企業の継続的な成長にも悪影響を及ぼします。
しかしMiroのオンラインホワイトボードが主戦場になれば、参加者全員が意見を交換し易くなります。我々もいまハイブリッドワークを行っていますが、オフィスにいてもみんなモニター画面を見て、その中でディスカッションをしています。これからはこういった働き方が主流になってくると考えています。
──ハイブリッドワークを踏まえた上で、新しい会議の形を目指されているわけですね。では、2つ目は?
五十嵐: 2つ目は、70年代にあったような参加者が意見を出し合える会議を取り戻すことです。日本人は、以前から、「10人いても3~4人しか喋らない」と言われてきましたが、これは日本人特有の奥ゆかしさによるもので、「あなたの意見は?」と問われるとみんな答えられるのです。これがリモートになったことで、以前よりもっと発言し難い環境になっています。なぜなら、ビデオ会議はテクノロジー的に会話を被せにくいからです。
何かしないと、日本はコロナ禍以前にすら戻れないでしょう。戻ったとしても失われた30年と言われるほどです。かつて日本は、みんなで寄り集まりディスカッションをすることで、多くの優れたものを生み出してきました。そんな喧々諤々(けんけんがくがく)な積極的な会議を取り戻す仕掛けとなるのがMiroだと考えています。Miroは、声に出さなくても、手書きや付箋、「いいね」などのリアクションがとれますので、奥ゆかしい日本人の意思表示にも合っており、意見出しのきっかけになりますね。
コラボレーションツール導入の課題とは?
──ここからは松本さんにも伺いたいと思います。リモートワークのためにさまざまなツールが各社から提供されていますが、ウィズ/ポストコロナ時代の企業のチームコラボレーションにはどのような課題がありますか?
松本: 日本では新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、テレワークを導入する企業が拡大しましたが、その大半が、これまで対面型のコミュニケーション手法で仕事をしてきた方々でした。それが、突然端末だけで仕事をすることになったのです。このため、IT環境の未整備や従業員への教育不足から、十分なコミュニケーションがとれず、苦戦している企業は多くあります。今回のような緊急時の事業継続はもちろんですが、時代に合わせて、ビジネスにスピードが求められる今、リモートワークであっても、必要なコミュニケーションを取れる環境が必要です。
とはいえ、アナログとデジタルのスキマを埋められるツールはそれほど多くはありません。また、五十嵐さんが仰っていたように、かつての日本にあったアナログの良い面は失われてきています。ですから、もう少し紙と鉛筆に近いアナログ感覚で使えるツールがいま求められているのではないでしょうか。そうでないと、リモートワークの環境において、さまざまな社員の知見を活かすことができず、優れた製品やサービスや、新しいビジネスモデルにつながるアイデアを創出し、競争優位を確立するという、本当の意味でのDXは実現できないのではないかと思います。
-
日立ソリューションズ シニアエバンジェリスト 松本 匡孝 氏
──Miroは、そんなコラボレーションの課題を解決するツールということでしょうか?
松本: はい、これからのハイブリッドワーク時代のチームコラボレーションを成功に導く、重要なキーパーツだと感じています。最近、心理的安全性が注目されているように、コミュニケーションが円滑で何でも言える環境であれば、チームパフォーマンスやエンゲージメントが向上します。
そのためには、働く環境問わずみんなが発言しやすいツールを使わなくてはなりません。Miroは全員が同じキャンバスに向かっているため、そういったハンディがなくなり参加しやすくなると思います。
──とはいえ、企業はMiroのようなコラボレーションツールの導入に二の足を踏みがちです。その理由はどのような点にあるのでしょうか?
松本: やはり使い始めの難しさにあると思います。DXを実現するためには、”CX”(コーポレートトランスフォーメーション:企業文化やマインドの変革)が必要です。つまり、DXを推進するための仕掛けや仕組み作りが求められるのです。これがないと、「やっぱり使い慣れたExcelのほうが仕事しやすいよね」と新しいツールは活用されないままになるでしょう。
では仕組み作りとしてなにが必要かと言いますと、1つ目はユーザーに明確なメリットを伝えることです。2つ目はユーザーが手厚いサポートを受けられること。そして3つ目は、とにかく使ってもらう仕組み(場)を提供することです。
五十嵐: 使い始めには食わず嫌いもありますよね。Miroもなんでもできるがゆえに「用紙だけ置かれても何を書いていいのか分からない」という状況にならないために、さまざまなテンプレートを用意しています。なかにはアイスブレイク用のテンプレートもあり、みんなで自分の似顔絵を作ったり、好きな食べ物を教えあったりできます。最初のハードルを超えてしまえば、その後にはMiroの持つ広がりを感じていただけると思います。
──それはすごく面白いですね!心理的安全性を向上させる効果もありそうです。
五十嵐: はい。たとえば「好きな食べ物は何ですか?」というテンプレートで、部長が「豚骨ラーメンだね」と書き、ファシリテーターの方が「部長、どこのラーメンが好きですか」と返したら、それだけで和みますよね。上司の人間性に触れ、発言しやすい空気を作ることができれば、その後の会議は間違いなく活性化するはずです。
製造業や情報・通信業におけるMiro導入事例
──それでは、実際の導入事例について伺っていきたいと思います。Miroは主にどのような分野で利用されているのでしょうか?
松本: 製造業のお客様は多いですね。日本のものづくりの現場では、ホワイトボードや模造紙をみんなで囲み、付箋紙を活用したブレストやアイデア出しを行ったり、図面を広げて、手書きをしながらレビューを行ったりする業務が多くあります。そのような分野では、模造紙や付箋紙、手書きの再現を求めているのです。そんなところにMiroを提案すると非常に興味を持っていただけます。
五十嵐: 実際、Miroが一番使われているのが製品開発部門です。ほかには情報・通信分野でも使われています。とくにアジャイル開発やスプリントデザインを行う現場では人気が高く、開発部門で使われると、その製品を販売する際に周りの部門も使い出し、どんどんMiroを使う人が増えていくのです。製品開発をコアに全社に広がっていくパターンが非常に多いと感じます。
──実際に使われているユーザーからの声で、印象に残っている感想はありますか?
五十嵐: あるお客様は、Miro導入前は、会議室をプロジェクトルームにし、模造紙や設計図をたくさん貼り、ホワイトボードに「消すな!!」と書いていたそうです。なんでこんなことをしていたかというと、議論の中身をライブなまま残しておきたいからです。
しかし現実には時間や空間の制限があるので、いつかは撤収しなくてはなりません。そうすると写真などを撮って記録するのですが、そのお客様はこう言いました。「写真に撮って記録した段階で全て消えてしまう。あの熱い議論を巻き返すのはものすごく大変だ」と。しかしMiroの導入で、未来永劫そのプロジェクトルームを残すことができるようになり、ものすごく助かったと仰っていました。
──それでは松本さんに伺います。日立ソリューションズはMiroの販売代理店という立場にありますが、貴社ならではの強みはどんなところにあるのでしょうか?
松本: 当社は、お客様のDX推進、働き方改革に必要なIT環境の提供、整備だけではなく、知見を活かした提案をすることが可能です。我々は、2016年から全社で働き方改革を推進してきました。IT環境の導入だけでは機能しないことを、身をもって知っており、働き方改革におけるノウハウは、国内のどんなベンダーよりも熟知していると自負しています。
当時の働き方改革のテーマが、テレワークとコミュニケーション活性化でした。テレワークについては、実施している企業はまだ少なく、社員が利用するに至るには非常に苦労しました。そこで、管理職以上が率先して利用することをルール化したり、外部のサテライトオフィス提供会社と提携したりして、オフィス以外でも仕事ができるよう環境を整備しました。またコミュニケーション活性化では、勤務時間中に自由に雑談ができるようオフィスビルに休憩場所を設置し、お菓子とドリンクも提供し「仕事以外の話をする場を作る」ことを実施しました。上司と雑談する際にも職制上なりがちな一方的な会話にならないよう「人の話は絶対否定しない」というルールも作りました。とにかく会話によるコミュニケーションの量を増やし、活性化させるための施策を徹底的にやってきたのです。もちろん、失敗も何度も経験しています。そして、その失敗の部分にMiroが適用できると実感しています。
また、当社のビジネスにおいてもMiroを活用しており、お客様のDX推進を支援する「日立ソリューションズ DXラボ」サービスを提供するなど、自社のビジネスにも活用できています。そのため、これらの経験から、お客様に対して親身になってご提案できること、働き方改革の知見を提供できることが、我々のなによりの強みだと思っています。このようなノウハウを、お客様の現場で説明会や勉強会を開催することも可能ですし、制度や施策のアドバイスをするという構想的な面でもご協力できます。
五十嵐: 日立ソリューションズさんには多くのエンジニアがいて、お客様の業務に密接に関わっています。それゆえにお客様の業務や言葉、その中身をよく知っていますよね。加えて、日立ソリューションズさんはコアな部分でMiroを実際に使われています。この両面から、お客様にベストな使い方をご提案できるのではないかと期待しています。
「Miro」が企業にもたらす本質的な価値は
──ここまでさまざまな視点からお話いただいてきましたが、最後に企業がMiroを導入することで得られる価値について、端的に教えていただけると幸いです。
松本: ナレッジマネジメントですね。Miroを活用したコミュニケーションを行うことでMiroのボード上にナレッジが蓄積していきます。企業のナレッジは財産であり、それを残すことができ、さらには、誰がどう発言したのかも残すことができますので、誰が何を知っているかも把握できます。
会議もただの議事録ではなく、どういう経緯でどうなったかまで可視化されます。こういった財産が貯まっていく企業と流れ出てしまう企業では、将来の価値が全然違ってくると思います。DXの観点でいえば、その企業の競争優位に影響を及ぼす要素です。
五十嵐: あえてMiroを一言で表すなら、私は「全社一丸ツール」と表現します。Miroを入れることで社員全員の力を一方向に向かわせることができる。その会社のビジョンを示し、従業員の思いを一緒にしていこうという、パーパス経営と一緒です。
そしてパーパスを実現するためには、若い人、昔とった杵柄な人、役員、さまざまな社員の声が反映され、ダイバーシティのあるディスカッションが進まないといけません。これを企業に実装するのがMiroだと思っています。私は、Miroを通じて全社が一丸となることで、70年代の強い日本を取り戻すことができると信じています。
[PR]提供:日立ソリューションズ