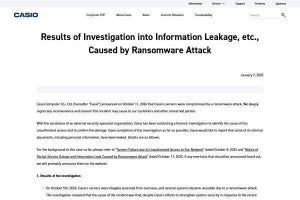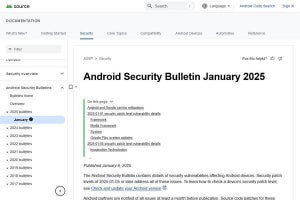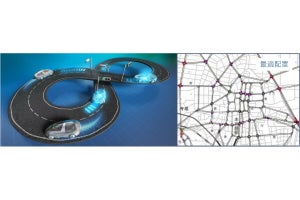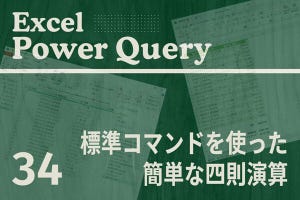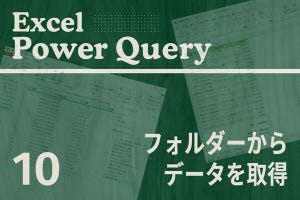先日、オンラインで日本オフィス開設2周年のメディアイベントを開催したSlack。本稿ではイベント後半に行われたSlackの導入企業における対談を紹介する。
対談は、Slack Japan 日本法人代表の佐々木聖治氏に加え、NECネッツエスアイ 取締役執行役員常務の野田修氏、クレディセゾン 専務執行役員 CTO(兼)CIOの小野和俊氏、ベルシステム24 業務統括本部 DX企画局 局長の川崎佑治氏が参加した。
コロナ禍による働き方の変化
はじめに「コロナ禍における各社の働き方の変化」に関して各社の見解が述べられた。Slackでは、昨年2月に完全リモートワークをスタートし、バターフィールド氏が「今はがんばらずに安全を第一に」という方針を示し、従業員に対して自宅におけるIT環境の整備をいち早く進めるための支援や、Slackを中心とした働き方で移行はスムーズだったという。
佐々木氏は「導入企業からは『コロナ禍でもSlackがあるから業務を進められている』と言われたことが励みになり、もっと普及していきたいという心持ちになりました。Zoomなどで企業の経営層の方とも意見交換ができたほか、ストレスとの付き合い方も従業員同士で工夫したり、お客さまからもアイデアをもらったり、議論したりするなどの機会を作りながら変化に対応しました」と振り返っていた。
2019年からSlackを全社導入しているNECネッツエスアイでは、月間アクティブユーザー数が4867人、月間メッセージ投稿数が2万5240件、パブリックチャンネル数は3027件(パブリック率は91%)と積極的なコミュニケーションを図っている。コロナ前は部門内のみでコミュニケーションで利用していたが、コロナの感染拡大以降は出社できずにリモートワークに移行したことから、既存の業務に課題があった。
そうした状況に対し、野田氏は「業務に関連する組織横断チームのチャンネルを作成したことに加え、承認やボットによる健康管理確認、システムインテグレーションの作業予定・結果・出社予定などの社内プロセスをSlackに組み込んで活用することが爆発的に増えました」と、組織を横断した活用で乗り越えたという。
次に、コロナ禍でSlackの全社導入を決定したクレディセゾンの小野氏と、ベルシステム24の川崎氏に対する導入の決め手について話が移った。
まず、小野氏は「金融業界は書類保管の必須の場合があり、ある程度出社しなければならないこともありますが、エッセンシャルワーカーでもSlackは有効です。と言うのも、リモートワーカーとのやり取りが電話もしくはメールに限定されると、マルチキャストができないなどの問題があります。そこで、Slackを導入して部分的に適用範囲を広げていきました。すると、電話やメールよりも伝えやすく伝達も速ければ、記録にも残るため好評でした。出社が必要な業務を抱える当社であっても、このようなことから全社導入しようと決断しました」と話す。
川崎氏は「リモートワークの場合、疎外感を感じることなどが多く起こりがちですが、Slackを利用すれば気軽に雑談ができます。人間はそういったコミュニケーションの中に”つながり”を感じることが多いのではないかと思いますし、自然なコミュニケーションを可能とします。その一例として、社内のコロナ対策について検討していた際に、各地のコロナ対策がチャンネルで共有されるなど、中央集権的な対策ではなく、常に各地からの対策による横ぐしの連携でアップデートされていきました。これは、従来なかった新しい方法であり、驚きでした。このようなことが起こるのだ、という体験が決め手となりました」と述べ、両社ともにリアルでは考えられなかったコミュニケーションの新しい体験を経て、導入を決めたようだ。
“デジタルワークプレイス”を職場とするメリット
そして「これまでの物理オフィスをSlackに置き換え、”デジタルワークプレイス”を職場として働くことには、どのようなメリットがあるのか」ということについて議論が交わされた。
これに対し、小野氏は「デジタルワークププレイスで変わったと感じたことは”カジュアルな記録”が習慣化したことです。リアルの場合だと会話だけでその場で終わってしまいますが、経緯が文字として残ります。もちろん、対面で口頭によるコミュニケーションで伝わりやすいこともありますが、その場にいない人もいるため、話した内容をSlackに残せば後々に参照しやすくなりました。この良さはコロナが明けても全社で一度体験していることから、消えていかないものだと思います」と語る。
また、川崎氏は「デジタルワークプレイスは、どの会社も移行している最中ではありましたが、Slackがある種決め手になったというイメージを持っています。当社にとっては”非同期的”であることが大きいですね。これは、リモートワーカーとオフィスに出社しているメンバー間でもシームレスに連携し、時間差であっても確認できるほか、同じテーマについても物理的なオフィスだと数十人しか共有できなかったことが、全社のチャンネルに書き込めばデジタルにつながるメンバーと共有が可能になっています」とメリットを話す。
野田氏は「物理的なオフィスの場合、つながりが限定されることがありました。しかし、デジタルであれば組織横断的なチームが構成され、多様な知識を持ったメンバーが集まり、生産性が向上する可能性が高くなりました。さまざまなメンバーが多様なスキル・役割を持っていますが、フラットかつオープンに話すことを可能とし、これまで思いつかなかったアイデアが生み出され、業務の幅が広がり、スピードが向上したと感じています。また、トップが決断した結果を全員が同じチャンネルを閲覧することが可能なため、迅速に意思疎通を図ることができています」と、デジタルワークプレイスにより生み出される効果について触れていた。
小野氏、川崎氏、野田氏の話を踏まえ、佐々木氏は「お三方の話を聞いていると、Slackは公平性がメリットとしてあるのではないかと思います。デジタル化した情報をSlackを介して扱うことができ、コミュニケーションデザインの仕方によってはオープン性を保つことで、例えば職種や役職、新入・中途社員に対しても公平に情報にアクセスを可能とし、早い段階で活躍できる場を提供することがデジタルワークプレイスのメリットなのではないかと思います」との認識を示していた。