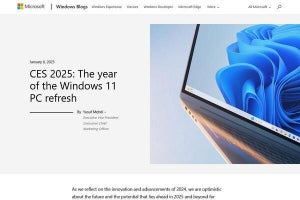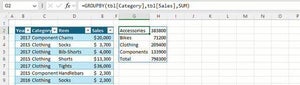コロナ禍でテレワークを導入したものの、うまくいかずにオフィスワークに戻った企業も多い。その最大の理由は”出社しないとできない業務”が多いからだ。一筋縄ではいかないこの課題を解決する方法はあるのだろうか。
11月26日に開催された「マイナビニュースフォーラム 働き方改革 Days 2020 Nov.」に、コニカミノルタジャパン いいじかん設計企画部 副部長の牧野陽一氏が登壇。コロナ禍以前からテレワークを推進し、現在はテレワークとオフィスワークを使い分ける体制で大幅な業務効率化を実現した同社の改革ノウハウを語った。
テレワークへの全面移行で何が変わったか
コニカミノルタは、売上高の合計が9,961億円、従業員数4万人超の規模を誇るグローバル企業だ。そのグループ会社の1つであるコニカミノルタジャパンでは、国内に3,300名超の従業員を抱え、オフィスサービスやデジタルマーケティング、ヘルスケア、計測機器、商業/産業印刷など幅広い事業を展開している。
同社は、従業員と組織にとって最適な働き方を「いいじかん」と名付け、コロナ禍以前から国内全従業員を対象にテレワークを実施してきた。経営トップや人事だけでなく、総務や情報システム、マーケティング、営業、サービスなどさまざまな部署が参画しており、一般的な人事施策ではなく、企業全体の事業活動としてテレワークに取り組んでいる点が特徴だ。
テレワーク推進の旗振り役を務める牧野氏は、テレワークの目的として「ES(従業員満足)とCS(顧客満足)の向上」を挙げる。加えて、自然災害などへの備えや、子育て/介護と両立できる環境を用意することで優秀な人材を確保する狙いもあるのだという。
そもそも、コニカミノルタジャパンの働き方改革は国内企業としては早く、2013年から始まっている。オフィスを移転した2014年頃から社内外の環境整備を整え、フリーアドレスやサテライトオフィス、フレックス制度などを導入。2016年には”保管文書ゼロ化”を目指して紙ベースの書類を削減した。同年、従業員2,800名を対象にテレワークのトライアルを行った結果、手応えを得たことから本格的にスタートし、全社員のうち約3分の1が週に1回以上テレワークを実施するようになった。
これらの施策の結果、従業員一人あたりの生産性は約28%向上し、月の平均残業時間は15%の減。社内保管文書は88%減り、離職率も一般的な企業の数値に比べて5割以上低くなるなど、高い効果を得た。
「ただし」と牧野氏は続ける。「ここまではビフォーコロナの話」だ。
順調に思えた同社の働き方改革だったが、2020年に発生した新型コロナウイルス感染症の拡大で状況は一変する。
1月中旬に従業員への注意喚起を行い、2月中旬にはガイドラインを発信。可能な限りテレワークやフレックスを活用し、出張は中止や延期を求めた。3月に入るとテレワークを原則とし、従業員同士が物理的に会うことはほとんどなくなったという。従業員の意識が変化したのもこの時期だった。
「当初こそテレワークオンリーの勤務に慣れない従業員もいましたが、6月頃にはすっかりテレワークが定着しました。意外と業務はできるし、オフィスって必要なの? という意識へと変化したのです。アンケートをとってみると、アフターコロナにおいてもテレワークを希望するという声が8割を占めました」
テレワークへの急激なシフトが進んだウィズコロナ。経営側にとって気になるのは業務の生産性だ。
この点については「生産性が上がった」と感じている社員は全体の31%おり、「生産性が下がった」と感じている割合の21%を上回る。これは他社調査の結果よりも良好な数値であり、「我々が改善しながら(テレワークに)取り組んできた結果」と牧野氏は胸を張る。
牧野氏は今後、従業員の住まいの状況も変わっていくと予想している。オフィスの近くに居住する者は減り、オフィスから遠い場所に居住する者が大きく増加するのではないか、というわけだ。これは、コロナ禍を経てオフィスの役割が変化したことによる。
「ビフォーコロナではオフィスは単に働く場所でした。しかし、ニューノーマルでは働く場所は主に自宅になり、オフィスは”知を生む場所”という機能を持つ場になっていくでしょう」