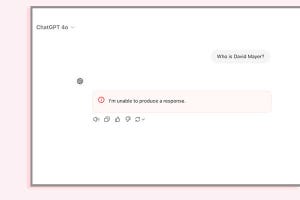ECサイトをはじめとする各種ネットサービスの台頭によりリアル店舗が苦境に立たされるなか、2019年4月にオープンした次世代型ショールーム「蔦屋家電+(プラス)」は、リアル店舗の変革に挑戦している。
7月9日に開催されたオンラインセミナー「マイナビニュースフォーラム 2020 Summer for データ活用」では、蔦屋家電+のプロデューサーである蔦屋家電エンタープライズ 商品企画部 新規事業チームLeader 木崎大佑氏が、これからのリアルマーケティングの可能性や蔦屋家電+のビジネスモデルについて、詳しく紹介した。
減るリアル店舗と増えるリアル店舗
リアル店舗の撤退や閉店の発表が相次いでいる。その背景の一つにECの拡大があるが、ECサイトという領域だけ見ても、総合型からメーカー直販型、フリーマーケット型まで多様なチャネルがあり、各チャネルでさまざまなサービスがしのぎを削っている。消費者からすれば、数多の選択肢があるというわけだ。こうした状況にあるなかで、「『あなたの店で買わなければならない理由は?』という問いに答えられないリアル店舗は苦戦する」と木崎氏は指摘する。
一方で、リアル店舗が伸びている領域もある。例えば、米Amazonが運営する無人店舗「Amazon GO」は、アプリを起動してチェックインするだけで商品をレジに通さず購入できるといったフリクションレスな購入体験をリアル店舗で提供している。中国Xiaomiは実際に製品を体験できるリアル店舗の数を伸ばしていく方針を打ち出しているし、フリマアプリを運営するメルカリも、出品の方法をワークショップで学べたり、スタジオで商品の写真撮影ができたりする「メルカリステーション」を展開している。つまり、オンライン企業がオフラインへと手を伸ばし始めているのだ。
では、なぜここに来てこのようなOMO(Online merges with Offline)の取り組みが目立つようになってきているのだろうか。木崎氏は、「ファンマーケティング」がその鍵であるとする。より顧客の情緒に訴えかけるような戦略として、企業はOMOを重要視し始めているのだ。
「近年では、新規顧客獲得よりも、上位顧客の満足度と購買頻度を上げてLTVを伸ばすような考え方が主流になりつつあります。さらに、モノがあふれてスペック戦争が終焉を迎えつつある今、商品の機能だけを訴求していても消費者には届きません。ストーリーや体験から顧客の心をつかんでいくことが重要だと考えられています」(木崎氏)
D2Cビジネスが注目されつつあるなか、リアル店舗ができること
プロダクト自体の機能からストーリーや体験といった情緒的なものへと提供価値が移り変わっていることを象徴する出来事として、D2C(Direct to Consumer)ビジネスの盛り上がりがある。
D2Cの体表例として挙げられるのが、米国の衣料品ブランド、Allbirds(オールバーズ)だ。同ブランドのECサイトでは、商品の機能を全面に出すのではなく、「CARBON FOOTPRINT 0.0」を掲げ、「製品をつくる過程における温室効果ガス排出を限りなくゼロにする」というメッセージを強調して伝えている。
また木崎氏によると、NIKEもD2Cに分類できるという。その理由を木崎氏は「ブランドと直接コミュニケーションを取ることができるし、製品だけではなくライフスタイルそのものを提案してくれている」からだと語り、「自分自身も一消費者として大ファン。大型ECサイトでの販売を中止するとも発表しており、今後は自社ECで販売するかたちを取っていくだろう」と予測する。
このような状況下において、重要視されるリアル店舗の価値とは何だろうか。木崎氏は「体験」と「データ取得」であるとした上で「体験とは、自分たちのブランドの良さを伝えていくこと。データ取得は、お客様のことを知ること。お客様にブランドを五感で体験してもらう場、そして企業が顧客をより理解するための場としてリアル店舗を捉えなければならない」と見解を語る。