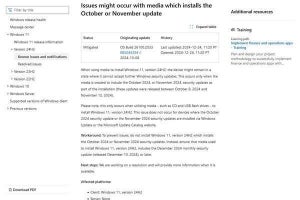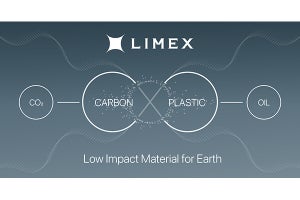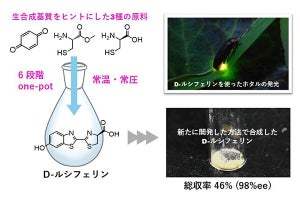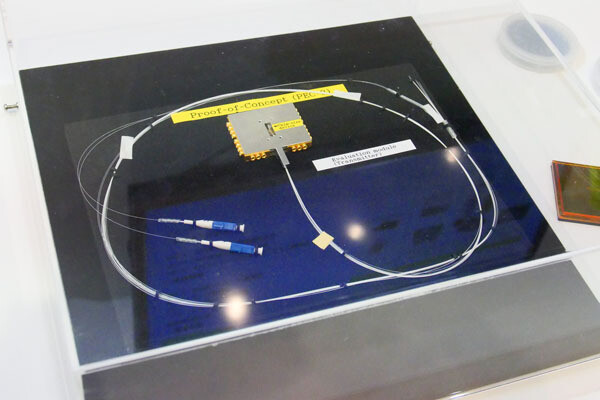かつては研究者たちが扱う専門用語の1つだった「AI(人工知能)」だが、技術の進化とともに身近な機器やサービスへの利用も増え、今では日常的によく耳にするキーワードとなっている。だが、SF小説などの影響も相まって先進的なイメージが先行した結果、実体がつかめずに「そもそもAIとは何なのか」「AIには何ができるのか」「AIを導入するためにはどうしたらよいのか」という疑問を持つ方も少なくないだろう。
4月21日にオンラインにて開催されたマイナビニュース スペシャルセミナー「AI Day 2020 Apr.~事例で学ぶAI 実践活用シーン~」では、NTTドコモ R&Dイノベーション本部 サービスイノベーション部 大西可奈子氏が、AIでビジネス課題を解決するために必要な基礎知識からAIを効果的に活用するための発想力の身に付け方まで、事例を用いて解説した。
AIにできること、できないこと
AIとはそもそも何なのだろうか? Wikipediaで調べてみると「人間の知的能力をコンピュータ上で実現する」などという記述があるが、その説明で腑に落ちる人はおそらくいないだろう。実は学術業界でも、統一されたAIの定義がなされていないのが現状だ。大西氏は「そもそも『人間の知能』がいったい何なのかが定義できていないことが問題」と指摘する。
そうした背景も踏まえた上で大西氏が考えるAIとは、あえて言うならば「教えた以上のことができること」。そして、それを可能にするための技術の1つが機械学習であるとする。最近よく耳にするディープラーニング(深層学習)も、機械学習の一手法だ。
機械学習には、大きく分けて「学習フェーズ」と「予測フェーズ」がある。さらに、学習フェーズは、「1.学習用のデータ準備」「2.データを学習させる」「3.学習モデルができる」、予測フェーズは「1.予測したい入力を学習モデルに入力」「2.学習モデルで予測」「3.予測結果を得て活用する」という流れに分けて考えることができる。ポイントは、「学習フェーズで学習していない入力に対しても、データを基にある程度の精度で予測できること」。何を予測するかは、予測したいもの、そして学習データ次第となる。
大西氏が気をつけてほしいと呼びかけるのは、「SFに出てくるような、何でもできる万能なAIがあるわけではない」ということだ。例えば、AIスピーカーは実際には、「対話システム」「音声認識システム」「音声合成システム」という3つのAIから構成されている。対話システムは、テキストの入力に対してテキストを出力するものなので、ユーザーの発話(音声による入力)を一旦テキストに変換する必要がある。それを行うのが、音声認識システムと呼ばれるAIだ。そして、対話システムが返答として出力するテキストを音声合成システムのAIが音声に変換する。これにより、ユーザーからするとあたかもAIスピーカーと対話ができているように見えるというわけだ。
「AIと一言で言っても、多くの場合はある特定の機能を担うAIの組み合わせによってできています。基本的に、1つのAIは1つの機能を行うように作られているので、単体でできることは限られているのです」(大西氏)
大西氏は、そんなAIができることとして、「分類」「未来予測」「クラス分け」の3つを上げ、AIによる分類の実例として迷惑メールの判定機能を紹介した。一般に、メーラーが迷惑メールかどうかを自動で判別してフォルダに入れていく仕組みには、AIによる分類が使われていることが多いと言う。「ざっくり言うと、迷惑メールであるメールと、迷惑メールではないメールを判別し終わったデータをコンピュータに学習させ、学習していない新しい迷惑メールが来たときに、それがどちらに当たるかということを自動で判別している」と大西氏は説明する。
ここで注意したいのは、AIにとってはデータが”命”であるということだ。「AIを開発するということは、『AIで解決したい課題に合ったデータを見つけること』と言っても過言ではない」と大西氏。データにもさまざまな種類があるため、「データを保存しておくことはもちろん大事だが、どんなデータがどれだけあるかを常時把握し、すぐに取り出せるようにしておくことが大切」だと続けた。