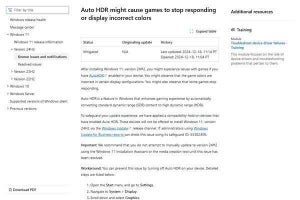この春に大きな問題となったランサムウェアだが、その多くは「バラマキ型攻撃」で、巧妙に偽装されたメールによる流入が多かった。
IIJによれば、2010年以降は落ち着きを見せていた迷惑メールが、ランサムウェアの流行と重なる今年3月頃から急激に増加し、ウイルスが添付されたメールの「バースト的増加」がたびたび見られたそうだ。
実際に警察庁も「上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」という資料を9月に公開。ウイルス添付ファイルの99%が圧縮ファイルとなっており、送信元メールアドレスを偽装した「なりすましメール」の割合も91%に上っていたそうだ。
今年起きた大規模情報漏えい事件で言えばJCBの例があるが、これについても送信元を偽装したメールにウイルスファイルが添付されており、結果的にマルウェアに感染している。
メールアドレスを偽装できる理由
そもそもなぜ、なりすましが起きるのか。これは送信者情報を定義する「メールヘッダ」の仕様に起因する。当初は「マイナビ太郎
しかし、この仕様を悪用して「taro @ example.jp
この対策には、アドレス帳に登録されたメールアドレスと、表示名ではない送信元メールアドレスをメールソフト/アプリでマッチングしてdisplay name代わりに表示する機能がある。しかし、アドレス帳登録がなければ表示される事実は変わらず、サーバーサイドでの根源的な対策が求められる。
その対策がSPF(Sender Policy Framework)やDKIM(DomainKeys Identified Mail)などの技術で、いずれも送信元の認証を行っている。
SPFは、送信元のDNSサーバーに送信用メールサーバー(SPFレコード、IPアドレス)が存在するか問い合わせ、メールの真偽を確認する。一方のDKIMでは、電子署名を利用してメールの真偽を確認する。具体的には、DNSサーバーで公開鍵を公開し、送信メールに電子署名を付与、受信サーバー側で電子署名を照合して認証する。
それぞれの技術が単体で動作した場合、認証チェックで漏れてしまうメールが存在する。「ドメイン認証できない場合は100%問題」というわけではなく、技術的なミスからDNSサーバーへの問い合わせが不調に終わるといった可能性もあり、すべてを排除して良いとは限らないためだ。これでは「排除が正しいのか」がわからず、結果的にドメイン判定だけでは迷惑メールを排除できない状況となっていた。
この問題を解決するため、送信ドメインの認証を高度に行おうという取り組みが「DMARC(Domain-based Message Authentication,Reporting and Conformance)」だ。