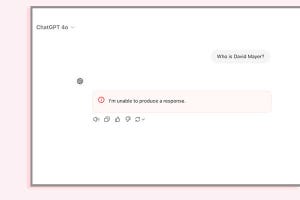いまWeb産業で「元社員が激白」というと、GoogleからMicrosoftに移り、古巣を「広告会社」と痛烈に批判したJames Whittaker氏を思い浮かべる人が多いと思う。13日にMSDNに投稿した「なぜGoogleを去ったのか (Why I left Google)」が論争を呼んだ。だが今回、取り上げたいのはWhittaker氏ではなく、同じ13日にWIREDに掲載されたもう一つの"激白"、元Yahoo!のAndy Baio氏の手記だ。Whittaker氏の投稿ほど話題にはなっていないが、同氏の暴露以上に、かつての輝きを失ったインターネット企業の危うい一面を浮き彫りにしている。
米Yahoo!は3月12日に、10件の特許侵害で米Facebookを提訴した。その中にBaio氏が考案者となっている技術が含まれているという。そもそも、その技術はYahoo!が特許がらみの攻撃から資産を保護したいと申し出てきて、同氏が特許申請に協力したものだった。ところが今、それが特許トロールのように使われようとしている。「(守るための)盾を与えたつもりだったが、私の名前が彫り込まれたミサイルになってしまった」と嘆く。
Baio氏の経歴を紹介すると、2003年にソーシャルにイベントを共有するUpcoming.orgを設立。05年にYahoo!がUpcommingを買収してから2年間在籍し、その後09年-10年にKickstarterのCTOを務めた。
Web 2.0がバズワードになる前の頃のYahoo!の活動を、Baio氏は「新しいいのちを吹き込んでいた」と賞賛する。OddpostやFlickrなど、将来性のあるスタートアップを見極めて買収し、Yahoo! Developer Networkを立ち上げ、リサーチラボも効果を発揮していた。だからUpcommningを売却したし、また冷戦構造を作り上げるのが特許トロールに対する防衛になるという説明に納得して、Yahoo!の特許ポートフォリオを強化する「Patent Incentive Program」に参加し、8件の特許を申請した。しかし、それを今は「世間知らずだった。当時の目的が本当に防衛策だったとしても、特許ポートフォリオの所有者はすぐに変わってしまう。企業は、いともたやすく心変わりする」と後悔している。
「これ以上ないほどに退屈な特許によって創造性が踏みつぶされることがあるからゾッとする。わたしが共同で考案した特許のうちの1つはあまりにも概念的で、Facebookのニュースフィードだけではなく、実質的にあらゆるフィードのアクティビティに適用できる」
これがBaio氏の思い過ごしでないのは、Yahoo!が特許侵害を主張する他の技術にも、同様の意図が見え隠れすることから明らかだという。例えばYahoo!の前CTOによって1997年に特許申請された「Dynamic page generator」は、さらに適用範囲が広く、FacebookからTwitter、Pinterestまで、あらゆるWebアプリケーションが侵害を問われる可能性があると指摘する。
Yahoo!は2004年にGoogleがIPOした時も特許侵害を主張しており、Facebook提訴はその再現と見る向きもある。しかしBaio氏が言うようにYahoo!が特許を盾ではなく、矛として使っているのなら、牽制する意味合いが強かったGoogleの時と今回はまったく異なる。Facebookとの和解が実現すれば、今回は訴訟の範囲を他のWeb企業に広げる可能性が高い。
今後Webサービス分野においても特許訴訟合戦が広がることを、われわれは覚悟しなければならない。ただ、どのような形で決着するにせよ、この騒動で重要なのは裁判の行方ではない。数年前までインターネットが育まれる場であったYahoo!が、いま特許紛争の最前線になろうとしていることだ。今はGoogleがWebをけん引する役割を担っている。しかしGoogleが救世主であり続けられるかというと、皮肉にも同じ日に、かつて「イノベーションの生産工場」だった同社が今は「広告売上げばかり追求している」とWhittaker氏に批判された。
今は想像もできないが、将来新しい勢力に押されたGoogleが特許トロールに乗り出す可能性だって否定できない。だから、Baio氏の後悔が繰り返されないように考えることが肝要だ。さもなければ、同じような問題にわれわれは直面することになる。すでにコピーライトでカバーされているソフトウエアが、さらに特許で保護されるべきなのか。突きつめれば、ソフトウエアやサービスの保護のあり方に行き着く。
「すでに誰かが見つけていたであろう一般的なもの(例えば"車輪")で最初になるのと、限られた人たちの想像の産物(例えば"Segway")は対照的なものであり、大きく異なる。スタートアップのCEOにたずねれば、誰もが"実行が全て (execution is everything)"と答えるだろう」(Baio氏)。