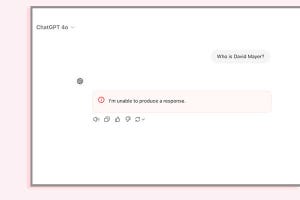「iPad」予約しました!
アカデミー賞中継では、「初のiPadテレビCM投入」→ 中継再開直後の長編アニメーション部門発表で「Pixerの『Up (カールじいさんの空飛ぶ家)』が受賞」と、Appleはマーケティングの賭けにも成功 (流れが出来過ぎで「Up」の受賞がちょっとしらけちゃいましたが……)。先行予約も始まり、実際にはまだ20日間ぐらいあるけれど、米国ではまもなく発売という雰囲気が日ましに濃厚になっている。
iPadの発売を心待ちにしているのはエンドユーザーだけではない。iPadアプリ市場を狙う開発者も自分たちが考えているアプリをエミュレータではなく、実際のハードウエアで走らせたくてうずうずしていると思う。そんな時期の読み物として、今回はNSConferenceとPodCampで行われたiPadのユーザーインターフェイス(UI)・デザインに関するワークショップを紹介しよう。前者のスピーカーはMatt Legend Gemmell氏、後者はGriffinのCameron Daigle氏だ。何のつながりもない2人のUIデザイナーによる別々のワークショップなのだが、「iPadは大きなiPhoneなのか?」という同じ切り口で、しかも2人のiPadに対する見方には多々共通点が見られる。いま日々iPadアプリと格闘している人たちの考えが似通っているというのは、そこにiPadの核心があるようで興味深い。しかもデベロッパではなく、エンドユーザーの視点で聞いても面白い内容である。
iPadは大きなiPhoneなのか?
答えは「イエス」かもしれないが、Gemmell氏に言わせれば「ノー」になるべきなのだ。
「ハードウエアや基本システムという点でiPadは大きなiPhoneかもしれないが、同じデバイスとして扱うのは愚かなことだ」と同氏。
2人のiPad論はあまのじゃくである。例えば、iPadではiPhoneアプリの多くがそのまま動作する。iPadが評価されている大きなポイントだと思うが、Gemmell氏に言わせれば「実用的だが、(デベロッパとして)特に興味を引かれるものではない」となる。逆に、iPhone OSベースであるiPadに対して「どうせならMac OS Xベースで、Macのソフトが動くように設計して欲しかった」と思った人が少なからずいたと思う。だがGemmell氏に言わせれば、そのiPhone OSベースという足かせが"iPadの大きな可能性"なのだ。
つまりiPadで動くiPhone/iPod touchアプリはおまけのようなもので、9.7型のディスプレイでデスクトップ・クラスのアプリをiPhoneのような使い勝手で使える"可能性"こそiPadの価値である。そのために開発者はユーザーインターフェイスを根底から考え直し、デスクトップ・アプリのワークフローをいかに取り込むかに苦慮しなければならない。そうしてホンモノのiPadは生まれるというのだ。
Daigle氏は、この点をUIを設計する上で考慮すべき「20%ルール」で説明する。
「平均的なユーザーはアプリケーションが備える機能の20%程度しか利用しない」
UI設計者は、その20%をユーザーが効率よく利用できるようにデザインする。ただこの20%ルールは、ユーザーがパソコンを仕事からエンターテインメントまでありとあらゆることに活用しようとしていた頃から存在する。「一般的なユーザーはOfficeやPhotoshopの機能の20%程度しか使っていない」と言いかえた方が分かりやすい。ところが今やパソコンに万能など求めず、とりあえずネットを使えれば十分というユーザーも多い。そうしたユーザーにとってPhotoshopの機能で必要なものはほんの数%だろう。ネットブックやネットノート、ネットデバイスやスマートフォンなどが普及している現在、20%ルールは「平均的なユーザーは"デスクトップ・アプリケーション"の20%しか利用していない」とアップデートされるべきだいう。
使うことがなくても、その機能がどこかにあるだけで人は安心するものだが、使わない機能はムダな機能である。メニューから長い選択肢がプルダウンするソフトは一見頼もしく思えるものの、実際には目的の操作を見つけにくいものが多い。Daigle氏は、将来的に一般ユーザー向けのソフトはパソコン用を含めて不要な機能がそぎ落とされ、今日の機能豊富なソフトは専門家やパワーユーザー向けになると見る。iPad向けにデスクトップ・アプリの利用体験を損なわないように機能を選び、タッチ操作の使い勝手を損なわないようにUIを工夫するデベロッパの取り組みは、そのシフトの第一歩になるというわけだ。
では「iPhoneでは無理なのか?」という疑問が出てくるが、小さな画面のiPhoneでは機能がそぎ落とされ過ぎてデスクトップ・アプリの利用体験には至らない。iPhoneとiPadの違いはというと、豊かな機能を取り込むためにAppleはiPadに「Master-Detail」の仕組みを用意した。例えばiPadのメール・アプリでは縦向きでインボックスがフロートし、横向きでは左側にバー表示されるなど、大きな画面内でインボックス(Master)とメール(Detail)が表示される。
他にも、例えばPagesアプリはビューワーのような状態が標準で、編集のために画面に触れるとツールバーなどが現れてエディターのようにふる舞う。また操作という点でiPadは、"両手"によるマルチタッチが可能である。iPhoneでもできないことはないが、スクリーン・サイズが小さいので両手だと画面がふさがってしまう。このマルチハンドのマルチタッチの可能性も、より多くの機能を使いやすく取り込む上で大いに役立つという。
他にもカーソルのないタッチ操作デバイスではタップできるボタンやエリアを容易に見分けられるようにする必要があるなど、UIデザイン上の多数のアドバイスが述べられている。ここでは全てを紹介できないので、興味のある方はGemmell氏とDaigle氏のブログを訪れて欲しい。
"触れる"心理が引き起こす親しみやすさ
iPadに対しては「パソコンを敬遠する高齢者に適している」という感想が多い。中には「シンプル過ぎてパソコンユーザーには物足りない」というニュアンスを含む皮肉っぽい意見も見られるが、これらは的を射ているのだ。Gemmell氏は、iPadアプリのUIは"触れる"ことに対する人の心理を刺激するようにデザインされるべきとしている。iPadサイズの板に触れるという行為は、人にドキュメントやノートパッド、ファイルフォルダ、クリップボード、書物などを思い起こさせる。パソコンには関心を示さない高齢者でも、そうしたものに接する感覚で手にとってしまうようなシンプルさがGemmell氏などが目指すところである。ただし、そのシンプルさで、一般ユーザーがデスクトップ・アプリに求める利用体験やワークフローを実現してこそ意義がある。
Gemmell氏らのiPad論に従えば、アプリ開発者が悩み抜いてiPadアプリを完成させるまでiPadはでっかいiPhoneに過ぎない。iPhoneが軌道に乗るまで1年強を要したように、iPadも真価を発揮するようになるまではしばらく時間がかかりそうだ。日本発売は米国よりも1カ月近く遅れることになるが、それでも早すぎるぐらいかもしれない。