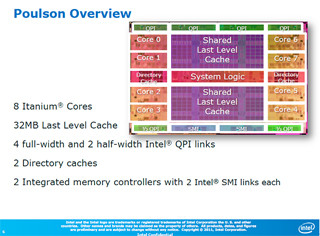昔のガラクタの中から1997年発行の「Microprocessor Report」の6月/8月号が見つかった。前回は、それぞれの見出しを紹介したが、今回は、その中から3つのトピックスを選んで内容を簡単に紹介しようと思う。
編集長コラムから見るIntelのCPU戦略のその後
Microprocessor Reportの初代編集長Michael Slaterから編集長を引き継いだLinley Gwennapによるこのコラムは大変に読みごたえがある。というのもこの記事が書かれたのは1997年であり、ここで論じられている事とその後に起こった事については2020年の現在ではすでに歴史的事実となっており、その事実から検証するとGwennapの洞察力について大いに敬服させられるからである。当時のIntelの2路線戦略の背景は下記のようなものであった。
- P5コアベースのPentiumの大成功を受けて、Intelは次世代コアP6をPentium Proとして1995年に発表する。この新しいマイクロアーキテクチャは後にネットバーストという名称でIntelのハイエンドCPUの基本アーキテクチャーとなっていく。
- IntelはP5の後のP6、そしてその後を継ぐP7コアの開発チームを矢継ぎ早に立ち上げ、2年おきに新しいアーキテクチャを世に出すことでAMDやCyrixという競合を振り切るはずであったが、P7コアの開発チームをHPとの協業によるVLIW(超長命令語)のコンピュータの開発に振り向けてしまった。「Merced」の開発コード名のこのCPUは後にIA64というx86とは互換性のない命令セットを持つ独自のハイエンドCPUである「Itanium」となって2001年に市場に登場することになるが、これは結局大きな失敗となりIntelはすでに2021年でのItaniumファミリー製品の製造停止を発表している。
1997年時点で明らかだった事はAMD、Cyrix、Centaur、VIAなどのx86互換の競合企業が盛んにこの巨大市場への参入を始めていた事くらいである。K6で復帰を果たしたAMDが次世代製品の開発を秘密裏に行っている事は噂レベルでは存在していたが、K7のマイクロアーキテクチャは翌年の1998年の発表まで待たないと誰も知る由もない。
この状況で書かれたこのコラムでは「IntelのIA32/IA64という2路線CPU戦略は見直しが必要」と評論し「この2路線戦略は将来的にIntelの市場独占をローエンドとハイエンド両方で崩す結果を生むであろう」と予見している。その後の切磋琢磨でAMDのみがIntelの唯一の競合として生き残り、現在ではIntelにとって大きな脅威となっている事実をも予見しているようでもある。果たしてK7はAthlonとなり大成功し、その後のK8はOpteronとなりIA64を葬り去ることになったわけである。
IDT子会社が低価格x86市場に参入
この時代が面白かったのは何と言っても競合が群雄割拠していたことであろう。Centaur Technology社は現在ではルネサス エレクトロニクスに買収されてしまったシリコンバレーの老舗企業であったIDTの子会社である。
Centaurはx86市場に当初「C6」というCPUで参入したが日本のDIY市場に現れた時には「WinChip」というブランドになっていたのでこの名前で憶えている方もいるかもしれない。このC6を扱った詳細な当時の記事によるとC6の設計思想は下記のようなものであった。
- AMDやCyrixがIntelのハイエンドCPUに真っ向勝負する中、C6はPentiumの成功で形成されたアフター市場を狙うべく、最初から低価格を意識した設計を取り入れた。
- 低価格を実現させるためにダイサイズを最小限にするべく、PentiumやK6で取り入れられたスーパースカラーの要素を排除し、Out-of-orderなどの命令処理への対応をするロジック部分をすべて落としている。その結果、浮動小数点演算などの性能向上ははじめから視野に入れていない。クロックスピードもトップが200MHzという抑え気味の設計である。
- ロジック部分をシンプルに設計することで空いたスペース分を利用して、キャッシュメモリーを増やす方策を講じている。これにより通常の業務用のアプリケーションなどでの総合性能ではPentiumやK6といい勝負をする。このため、Centaurはマーケティングでは「Winstone97 Business」などのビジネス用途向けのベンチマークを多用した。キャッシュメモリーのデザインにはIDTが得意とするSRAMのトランジスタ技術が使用されていることがコスト低減に役立っていることも大変に興味深い。
この記事を読んで初めて知ったことは、低コストのx86互換CPUをデザインするために動員された設計エンジニアはIntelのそれの10分の1以下の規模で、しかもこのデザインが一年足らずで完成し、最初のテストチップでWindowsがブートできたという完成度であったことだ。
さらに興味深いことにこのチップデザインにNKK(日本開閉器工業)が50%の出資社として参加していた。こうした背景説明と技術的な考察を加えた上でMicroprocessor Reportとしては下記のような結論を導き出している。
- Pentiumの成功によって現出したx86市場はローエンドの製品でも生き残るくらいの規模があり、IDTのプロセスが現行品C6の280nmから250nmにシュリンクすることによってさらなるコスト低減も可能となるし、低消費電力が実現されればローコストのノートブック市場や組み込み市場なども取り込める可能性がある(プロセスはサンプル品に基づくものと思われる。実際のWinchip C6は350nmプロセスとされている)。
- C6のチャレンジはCPUブランドとしてまったく無名のIDT・Centaurがマーケティングに成功できるかという問題と、IntelとのクロスライセンスがないIDTが特許侵害などでIntelから訴えられる可能性があることである。
実際にはWinChipは後継機種がなく、DIY市場で非常に限定的な成功を収めて市場から姿を消してしまったが懐かしいCPUではある。
SGS Thomsonが486ベースの統合チップを発表
前段のCentaur社の話でも分かるように、IntelのPentiumが扉を開いた巨大なx86市場ではハイエンドはサーバーからローエンドでは1000ドル以下のパソコンや組み込み用途へという急速な拡大がいよいよ現実味を帯びてきた時代であった。
その後の歴史を見てみれば明らかなように結果的にはこの両方は実現されたことになるが、現在x86市場でCPUビジネスを展開しているのはIntelとAMDだけになってしまった。
最後に紹介するのは欧州の国策企業SGSが486ベースの組み込み用途の統合チップを開発した話である。この件は私もすっかり忘れていた。
SGS ThomsonはイタリアのSGSとフランスのThomsonの半導体部門が合併してできた欧州では伝統のある半導体会社である(現在のSTMicroelectronics)。当時AMDでも486をコアとした統合チップ「Elan」を売り出しており、このころはハイエンドを爆走する向かうところ敵なしのIntelが残していったx86のアフター市場での可能性が現実的に議論されていた時代である。
SGSの統合チップ「STPC」はCyrix486のコアにPCI、ISA、IDEなどの周辺ロジックを1チップに統合したものである。当時のSGSの350nmのプロセスを使用してダイサイズを51mm2に抑えたというから、かなりコンパクトな設計である。
このチップが私の記憶に残っていないのは、AMDのElan同様に市場では受けが悪かったからであろう。当時、統合チップはIntelも含めCPUを手掛けるいくつもの会社が挑戦したが、仕様・タイミング・アプリケーションの多様化などの理由からほとんどすべての試みが失敗した。
私ががらくたの中から見つけたMicroprocessor Reportであるが、当時の活気に満ちた業界の雰囲気を感じる記事ばかりである。他にも紹介したいものがあるがキリがないのでこの辺でお開きとするとしよう。