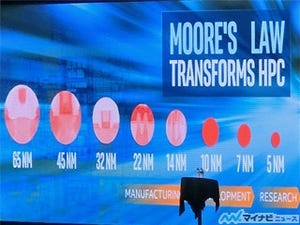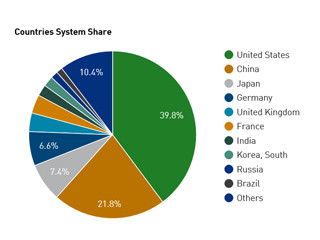IBMのJun Sawada氏のポジション
最後に登壇したのはIBMのSawada氏である。同氏らが開発したTrueNorthチップは、水色の部分がニューロンとして働く。横線が他のニューロンからの入力であり、1本の縦線が1つのニューロンとなる。入力にはニューロンへの入力を蓄えるバッファがあり、信号のタイミングを合わせている。交点はON/OFFスイッチではなく、ONになっている交点ごとに、横線に入力された値に重みを掛けて、その合計を縦線に出力する。そして、縦線は出力線でバッファを介してニューロン間を接続するグローバルなグリッドの横方向バスに接続される。グリッドは交点にクロスバを持っており、任意のニューロンの出力をどのニューロンの入力にも接続できるようになっている。
TrueNorthチップは28nmのCMOSテクノロジで作られ、4096コアを1チップに集積している。トランジスタ数は5.4Bで、チップサイズは4.3cm2である。各コアは256ニューロンを含んでいるので、チップ全体では1Mニューロンとして動作する。消費電力は、0.75Vの電源電圧で、平均20Hzでニューロンが動作する場合65mWであり、非常に低電力である。
次の図は、左がTrueNorthのチップ全体の写真で、右側は1コアの拡大写真である。コアには重みなどを格納するSRAMと重みを掛けて合計を求めるニューロン部分があり、チップ上のグリッドを通して出力と入力を繋ぐルータや、制御を行うスケジューラやトークンコントロールなどの部分が存在する。なお、このチップは多数個を相互接続して、さらに大規模なシステムを作ることが出来るようになっている。
すべての信号は、神経と同様に、パルス的に信号を伝えるという構造になっているので、消費電力が小さいのであろうが、1つのニューロンあたり0.065μWで動作するというのは驚異的なエネルギー効率である。しかし大脳皮質は100億~180億ニューロンと言われ、さらにエネルギー効率が高い。
同氏の個人的ポジションで、IBMのポジションではないと断っているが、ニューロチップが適している用途としては、ビデオやオーディオのようなファジーなデータの処理に適しており、将来的には自動運転などのロボットに使える可能性がある。ニューロチップの問題点としては特にラーニングのような、チップのプログラミングが難しく、時間がかかることを挙げている。
大量生産に関しては、使われているのは普通の28nm CMOSテクノロジであり、まったく問題がない。このようなニューロチップが将来デジタルを置き換えるかという質問に対しては、デジタルとは補完的であり、置き換えることはないとの立場である。
ポジショントークの後のディスカッションでは、会場からは、ニューロコンピュータに関する質問が多く出された。一番のポイントは、デジタルコンピュータのようにプログラムにしたがって動作するのではなく、学習にしたがって動作するという点で、どのように学習させればどのようなことが出来るのかが分からないという点で、掴みどころがないということではないかと思われる。
今回のパネルは、デジタルと量子、ニューロを比較するというものであったが、かなり確立されたデジタルに対して、量子ゲートを使う量子コンピュータは、まだ、実用的な計算ができる数のQubitを持つシステムの実現には距離があるし、量子アニールを使うD-Waveのマシンは、何ができるのか良く分からないという状態である。また、ニューロはIBMのTrueNorthのように、大規模ハードウェアは作れる見通しが出来たが、そのような大規模なニューラルネットワークをどのようにして学習させるか? それで何ができるのか? が分からない状況である。
この状態では、ムーアの法則が止まったとして、その先は量子コンピュータ、ニューロコンピュータという可能性を議論する環境は、まだ、できていないという感じであった。したがって、当面は、Borkar氏の言うようにMore of Moore、あるいはShalf氏のいうような3D実装などの色々な技術を集めて改善を行っていくという方向しか無いようである。もちろん、量子コンピュータやニューロコンピュータも使えるところでは使って、技術を磨いていくということも必要である。