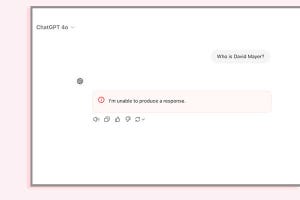「メディア革命」は、社会システムばかりでなくライフスタイルをも劇的に変えてゆく。今回から数回にわたり、米国の政治過程、特に大統領選挙にインターネットがもたらした"革命"を跡付けてみよう。
ネットを活用した悪役プロレスラーがミネソタ州知事に
日本ではいまだに、選挙公示期間中に候補者がホームページを更新することが原則禁止されている。一方、米国ではマイクロソフトのOS「Windows95」が普及し始めた1990年代中盤以降、選挙活動の全分野でインターネットの役割が飛躍的に増大し続けている。今や、ネット戦略が選挙結果を左右するようになった、と言っても過言ではない。
こうした動きが最も象徴的に現れるのが大統領選だ。2008年11月の大統領選挙は、「YouTube選挙」であるというのが筆者の見方だ(あるいは、「Facebook」や「MySpace」でもかまわない)。
選挙運動におけるインターネットの威力を米国民に知らしめたのは、1996年、あまり売れっ子とは言えなかった悪役プロレスラー、ジェシー・ベンチュラ氏が、ヒューバート・ハンフリー元米副大統領の息子で州司法長官のヒューバート・ハンフリー三世(民主党)や、現職のセントポール市長ノーム・コールマン氏(共和党)など有力候補を押しのけ、ミネソタ州知事に当選した時である。
「増税はしない」などのシンプルな公約をひたすら掲載
政治キャリアもほとんどなく、二大政党にも属さない泡沫候補扱いのベンチュラ氏は、選挙期間中、テレビCMを一切流さなかった(流す資金もなかったようだ)。自らのインターネットサイトに、遊説日程や、「児童一人当たりの教師を増やす」「増税はしない」などのシンプルな選挙公約をひたすら掲載。さらに、「こうすれば貴方でも50ドル、100ドル節税できる」という確定申告のノウハウなどをアップし続けた。
やがて、数少ない支持者が一斉にメール送信し始めた。そこから、ベンチュラ氏の行く先々に市民の輪ができるようになった。自然発生的なタウンミーティングでTシャツを売ったり、寄付を募ったりしているうちに、津波が起きたのだ。
テレビクルーや新聞記者は、こうした動きが顕在化した後、やっと取材に来た。ベンチュラ氏は一期で州知事を退いたが、「米国で最初にインターネット選挙で当選した知事」として歴史に名を残した。
以後、2000年と2004年の2回にわたる大統領選キャンペーンを通じ、インターネットの役割はさらに進化。当初は、候補者から有権者に、キャンペーン日程やボランティア募集など「上からの」告知手段として始まった。だが、メールやブログ機能が加わり、候補者と有権者の間を双方向につなぐコミュニケーションツールができたことによって、「草の根」の政治参加が多様化し、よりアクティブなものになっていった。
既存メディアの世論調査を"陳腐化"させるネット集計
2008年の大統領選挙キャンペーンは「デジタル第3期選挙である」といわれる。市民をつなぐネットワーク形成を行っている「Digital Divide Network」のアンディ・カービン氏は、「今回の選挙におけるインターネットの進化は、YouTubeなどの動画投稿サイトやFacebookなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)などによって、市民がより積極的、実質的にキャンペーンの全過程に参加していることだ」と指摘している。
例えば、2007年2月に開設された「techPresident.com」を見てほしい。各候補者の日程、サイト比較、ネガティブ情報を掲載、そしてYouTubeでのアップ数、書き込み数のデータなどが連日集計されている。
またYouTubeにログインして、「米大統領選挙」「オバマ」といったキーワードで検索すれば、関連する膨大なビデオを楽しむことができる。ここでは、支持者らが写真やビデオの投稿数を競っている。
こうした投稿やアクセス数などを継続的にチェックすれば、既存メディアが行う世論調査は陳腐化してしまうのではないか、と思えるほどだ。
ネガティブキャンペーンの"有力ツール"にも
無論、ネットはネガティブキャンペーンの有力なツールでもある。
「オバマ氏はイスラム教徒」といったデマ情報は日常的に流されている。日本人にはピンとこないが、世界貿易センタービルなどに対する「9.11」を経験し、イラクでも戦闘状態が続く米国において、大統領を目指す人間が「イスラム教徒」と報じられるイメージダウンは想像以上のものがある(もちろん、イスラム教徒であること自体が悪いはずはない)。
オバマ氏が若い時に通った教会の神父が激烈な白人攻撃をした演説も、隠し撮りに近いビデオ映像がYouTubeにアップされたことで、全米に広がった。
マスメディアという「ゲートウェイ」は不要か?
デジタル選挙という観点から見た今回の選挙の新しさは、民主党のバラク・オバマ、ヒラリー・クリントン両候補が、ともに出馬表明を自分のサイトで行ったことだ。なぜ記者会見という場が選ばれなかったのだろう? 選挙のプロに聞くと、「候補者は有権者との間にゲートウェイ(関門)は要らないと考え始めている」という答えが返ってきた。
候補者から見れば、既存メディアであるテレビも新聞も、有権者に自分をアピールし、有権者の反応をつかみ、支持を拡大するためのツールにすぎない。もし候補者が有権者、支持者に直接つながる有効な双方向のコミュニケーションツールを持てるなら、他の伝送路に頼る必要がなぜあるのか?
自分のサイトで出馬表明すれば、支持者の反応や情勢の変化によって出馬を取りやめても批判されることはない。カメラに不本意な姿を撮られることもない。意地悪な質問に答える必要もない。
かくて天下のニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポストも、「ヒラリー・クリントン氏は(またはバラク・オバマ氏は)、自らのウェブサイトで2008年の大統領選挙への出馬の意向を表明した」と報道するしかなかった。
執筆者プロフィール
河内 孝(かわち たかし)
1944(昭和19)年東京都生まれ。慶應義塾大学法学部卒業。毎日新聞社政治部、ワシントン支局、外信部長、社長室長、常務取締役などを経て2006年に退社。現在、(株)Office Kawachi代表、国際福祉事業団、全国老人福祉施設協議会理事。著述活動の傍ら、慶應義塾大学メディアコミュニケーション研究所、東京福祉大学で講師を務める。著書に「新聞社 破綻したビジネスモデル(新潮新書)」、「YouTube民主主義(マイコミ新書)」がある。