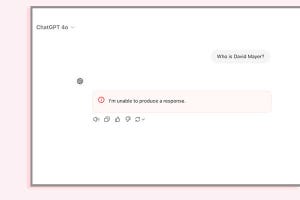電子新聞は成功できるのか
メディアコンテンツを有料化する動きが日本でも本格化してきた。日本経済新聞社は14日以降、関係者にその発行計画を説明しはじめた。
現在、同紙の新聞購読料(朝、夕刊セット)は月額4,300円。現行購読者が電子版を並行して契約すれば、プラス1,000円で提供するので合計月額5,300円。電子版単独の場合の購読料は月額4,000円である。課金は基本的にカード決済である。
この料金設定を高いと見るか、リーゾナブルと見るかは立場によって分かれるだろう。「現在、無料でサービスしているNIKKEI NETとどこが違うんだ」という不満の声も聞く。
日経側は、「携帯端末からもアクセスできるし、日経BPやQUICKの企業情報、さらに人事情報や過去の記事、データも検索できる」とデータ・ベースとしての利便性と充実度を強調する。しかし日経がメインの顧客層としてきた官公庁、金融・証券界は、すでに日経テレコンやQUICKと法人契約している。となると電子新聞は、一層のこと、個人ユーザー層を狙わなくてはならない。オンライン証券を駆使するデイ・トレーダーたちの、「お値ごろ感」にフィットするかどうか、が成否を決めることになるだろう。
「市場調査は十分やった」と喜多恒雄日経社長は語るが、日経は鳴り物入りでスタートした投資情報紙、「ヴェリタス」が不振で苦戦中という"既往症"がある。
電子新聞の成否を分けるのは、料金設定だけではない。確かに米国のウォールストリートジャーナル電子版(以下WSJ)が契約者100万人のラインを突破し採算ラインに乗ったという"先例"は、ある。紙と併読で月額1,000円という設定もWSJの月額13ドルにならっている。
購読者情報を握っているのは新聞販売店
しかし、アメリカと日本の新聞販売システムが全く異なることを考えると単純なアナロジーは難しい。
何よりもアメリカの新聞(電子版を含めて)購読者は発行本社の"もの"であり、顧客管理は発行本社が行っている。これに対して日本の販売システムでは基本的に新聞購読者は販売店の"もの"であり、顧客管理も販売店が行ってきたという慣習がある。
紙の時代は新聞拡張員による購読カード生産で販売店の経営が支えられてきた。いわば、「誰が、いつから、何ヶ月間購読する」という情報が記載された講読者カードは現金と同じで、その詳細情報は通常、発行本社にすら知らせていない。
日経の電子新聞ビジネスが軌道に乗るためには、「顧客Aさんが紙の日経新聞を購読しているか、いないか」の確認が不可欠である。そのためには、販売店に問い合わせて顧客情報を提供してもらわなくてはならない。
日経の場合、定着率がよいとはいっても、新聞購読者というものは毎月のように入れ替わるものだ。だから顧客確認は、販売店にしてみれば単に面倒くさいというだけでなく、発行本社側に顧客データが蓄積されてゆくことで商売のための貴重な情報が流失する、という不安を抱えることになるのだ。
新聞販売店が抱く不安と日経の目算
さらに難しいのは、日本経済新聞社の場合、多くの地域で販売、集金を全国紙3紙、または有力地方紙の販売網に委託していることである。自らが生殺与奪の権限を握る専売店に対してなら相当強引なことはできるが、いわば他社の暖簾を借りている地域では無理な相談である。
もともと新聞販売店側には、電子新聞の発行は紙の新聞との「カニバリズム=喰い合い」となるという恐怖心があるし、この認識は、ある面で正しい。とすると、「何故、自分の足元を崩すようなことに、しかも配達、集金を委託された他社に対して協力しなくてはならないのか」という店側の疑問にストンと胸に落ちる説明は難しい。
日経だけの損得勘定でいえば月額4,300円の紙の読者が、月額4,000円の電子版読者に移行してゆくことで失うものは、さほど多くない。むしろ顧客情報を本社が管理し、決済もカードで行われるのであれば販売店手数料が省け、デジタル時代にふさわしい流通、課金決済システムが構築できるという利点がある。
喜多社長は業界紙インタビューで、「電子版単独価格の設定では、紙媒体と、ほぼ同額でなければ電子版の方にシフトしてしまう可能性もある」(文化通信1月11日)との判断があったと述べている。相当シフトする事態が視野に入っているからこそ、こういう発言が生まれるのである。
以上のような販売店サイド、および同業他社の不安に対して日経関係者は、「電子版プロジェクトは、紙の新聞に影響を与えないことを前提に進めている。デジタル情報を紙でも確認する。日経ブランドが高まり、二つの媒体は"ウイン・ウイン関係"にある」と言う。
この説明で納得する人は、よほどの楽天家であろう。
執筆者プロフィール : 河内孝(かわち たかし)
1944(昭和19)年東京都生まれ。慶應義塾大学法学部卒業。毎日新聞社政治部、ワシントン支局、外信部長、社長室長、常務取締役などを経て2006年に退社。現在、(株)Office Kawachi代表、国際福祉事業団、全国老人福祉施設協議会理事。著述活動の傍ら、慶應義塾大学メディアコミュニケーション研究所、東京福祉大学で講師を務める。近著に『次に来るメディアは何か』(ちくま新書)のほか、『新聞社 破綻したビジネスモデル』『血の政治 青嵐会という物語』(新潮新書)、『YouTube民主主義』(マイコミ新書)などがある。