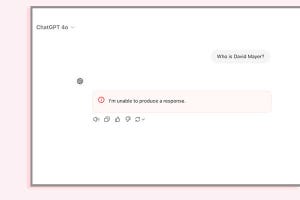"新聞後"の報道を考えるとき、米国でリストラされた記者や編集者らがたくましく「新ジャーナリズム」のビジネスモデルを模索、あるいは起業している姿に勇気づけられる。
彼らが果敢に再スタートできる背景には、英語が持つ国際性もあるが、日本に比べてはるかに低い人件費と、起業家に資金を提供する投資家グループの存在が見逃せない。
日本に比べ数百万円は低い米国新聞記者の平均年収
米労働省が公表している2006年度職業別給与表によると、新聞記者、特派員の平均年収は33,470ドルにすぎない。為替レートにもよるが、300~400万円というところである。
さらに詳しく見ると、中間領域の50%は24,370~51,700ドル、最低水準の10%が19,180ドル以下、最高水準の10%は73,880ドルとなっている。
比較的物価の安い地方記者が多数を占めること、ほとんどが共稼ぎであることを考慮に入れても、日本の同業者に比べ数百万円は低い。紙の新聞からインターネットサイトに切り替えても、ある程度固定の読者が付けば、アドセンスやアドワーズからの広告収入でやりくりできるのは、この人件費の低さが寄与している。
こうしたことを考えると、日本の新聞産業が「紙離れ」して広告モデルの電子新聞で生き残るには、よほど"骨身を削る"体質改善が必要となることが分かるだろう。
「有望」と見ればサイト立ち上げに投資する米ファンド
もう一つの要素は、新しいビジネスを育てようという投資家集団の存在だ。
スタンフォード大学アジア・米国技術経営研究センターのR・ダッシャー所長によると、米国の起業ファンドは1年間で約4,000のプロジェクトに300億ドルを投資しているという。これに対し日本では、プロジェクト数では3,000とさほど変わらないが、投資額は30億ドルで10分の1、最近では中国が年間14億ドルで日本を急追している。
無論、投資ファンドは慈善事業ではない。大きなリターンを期待してリスクを背負っての投資だ。しかし、これらのファンドがGoogleやAppleを世界企業に育て上げたという実績がある。
当コラム第36回の「TPM(Talking Points Memo)」の例でも見たように、有望と見ればサイト立ち上げに米国の投資家は、惜しげなく金をつぎ込む。これも日本との大きな違いではないだろうか。
原口総務相で、「メディア行政」はこう変わる
このあたりで話を日本に戻そう。
民主党への政権交代で、デビューした各大臣が活発に発言している。電波、メディア行政を担当する原口一博総務大臣も例外ではない、というより人一倍積極的である。
政権交代を機に行われる政策転換には、古い根を断ち切るような驚きと新鮮さがある。自民党万年政権のもと、惰性的に行われてきた行政運営を切り替えるのにもいいチャンスだ。
一方で、「新しさ」を追い求めるあまり拙速に走ると、将来に禍根を残しかねない。ここらのブレーキとアクセルの踏み方が難しい。
そこで原口大臣が提唱する「日本版FCC(※)」と、本コラムでも何回か取り上げた情報と通信の融合を目指す「情報通信法」の行方について検討してみよう。同法案は、これまで来年の通常国会への提出を予定していた。このスケジュールは、どうなるのだろう。
※ FCCは米国の「Federal Communications Commission(連邦通信委員会)」の略
「日本版FCC」、つまり独立委員会方式の「放送・通信委員会」のイメージについて、原口大臣は次のように語っている。
「言論の自由は民主主義の基本的インフラだ。政府が電波を所管し、放送局の生き死にの権限を握っている。政権を握っている者がそこに入ってきて所管する今のやり方でいいのか。統治機関が言論機関に様々な権限を行使しうる、というのを早いうちに変えておいた方がいい」
その具体的形と職権については、以下のように語っている。
「放送局の免許の付与や更新は総務省がやり、委員会は総務省だけでなく与党、野党といった政治権力による言論の自由への侵害をチェックする役割をイメージしている。国家公安委員会が警察庁をチェックしているようなシステムが必要だ。法にもとづき、報告や是正を求める権限を持つ」
委員の選任はどうするのか。
「議会で選ぶ、国民の直接投票で選ぶなど色々あると思うが、できたら公選にしたい。学者やジャーナリズム、国民の代表を含め議論をしていただいて、それをもとに制度設計にかかりたい」
「(新しい委員会は)放送倫理・番組向上機構の『公』(おおやけ)版ではない。表現内容については、放送局が自らを律してもらう。モデルにしている組織はない。世界初の事例だ」
(以上の発言は朝日新聞10月6日付による)
米国のFCCでは、大統領が5人の委員を選定し、議会が承認を与える。結果的に米国のFCCは、時の政権の意向を色濃く反映してきた。その轍(てつ)は、踏まないというのだ。
原口大臣は9月の連休中に、米ワシントンのFCC本部を訪問した成果を踏まえ、このような構想をブチ上げたのだが、放送界の反応は、予想以上に厳しいものだった。
執筆者プロフィール
河内 孝(かわち たかし)
1944(昭和19)年東京都生まれ。慶應義塾大学法学部卒業。毎日新聞社政治部、ワシントン支局、外信部長、社長室長、常務取締役などを経て2006年に退社。現在、(株)Office Kawachi代表、国際福祉事業団、全国老人福祉施設協議会理事。著述活動の傍ら、慶應義塾大学メディアコミュニケーション研究所、東京福祉大学で講師を務める。著書に「新聞社 破綻したビジネスモデル(新潮新書)」)」「血の政治 青嵐会という物語(同)」、「YouTube民主主義(マイコミ新書)」がある。