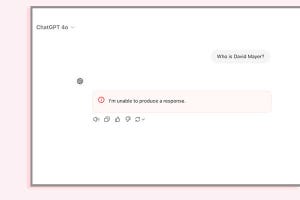新聞・テレビは「受動的」、ネットは「能動的」な利用
「新聞社、通信社、出版社、テレビ局――。様々な情報産業が送り出す情報コンテンツを消費者が受容する共通端末が、次世代スマートフォンになるだろう」。
こういう前提に立って今後のメディア革命の構図を占ってきた。しかし、そのことは新聞紙がなくなるとか、居間のテレビがなくなるということを意味しない。新聞紙は、(広げるスペースがあれば)情報を一覧できる発見メディア、つまり消費者が検索するのでなく、送り手が情報を提供し、消費者が、「そんなことがあったのか」とか、「役に立つ情報で得した」と受動的に受け止めることができる機能を持っている。
これに比べインターネットで情報を得るためには、消費者が、「何を知りたいのかを知っている」能動性が必要となる。無論、ネットにも「ネットサーフィン」という回遊型の一覧技術もあるが、得意とするとするのはあくまで関心事項に的を絞った検索機能である。
「情報送出と受容の構図」が根本的に変化
テレビにしても居間のワイドスクリーンで、映画を楽しみたい人にとっては素晴らしいツールだろう。だから新聞紙もテレビも、一つのコミュニケーション・ツールとして存続し続けるではあろう。しかし情報伝送の首座は、他の伝送機器・端末に取って代わられるということなのだ。
こう言い換えてもいい。ニューヨーク・タイムズが創刊されたのは1870年代。これ以降半世紀、新聞が情報伝達の主流を占める。ラジオが全米に普及し始めたのが1920年代、そして1940年代以降がテレビの時代と言える。伝送媒体は印刷物から音声無線、映像無線と変わったが、共通していたのは、いずれも情報送出側が「装置産業」であったことだった。高速輪転機、送信機、中継器、アンテナ――などである。
この伝送設備(ラジオ、テレビの場合は、これに加えて周波数免許)というボトルネックによって、一方的で、独占的な情報送出のフローが出来上がり、そこにビジネス・チャンスが生まれた。
1995年の「Windows 95」発売以降のPCの普及とインターネット網の整備が、設備と規制のボトルネックを形骸化し、情報送出と受容の構図が根本的に変わった。これがメディア革命の発端である。
法整備で「縦割りメディアを超えた横断的なビジネス」可能に
すでに述べたように総務省は、デジタル化が一段落した段階で「情報通信法」を2011年に制定するべく、経済人、有識者の意見を取り入れながら検討作業を行っている。総務省の谷脇康彦・情報通信政策課長は、法改正の狙いを、以下のように説明している。
「技術革新によって可能なのに、法整備が遅れているがためにできないことをなくす」
例えば現在は、光回線で流れているUSENの「Gyao」や、NTTグループの動画配信は、「放送」と同じなのに、放送法の適用を受けない。だから放送法、電波法、電気通信事業法などを融合させ、テレビ、インターネット、ラジオという個別の伝送手段を超えたコンテンツ、プラットフォーム、伝送インフラ、伝送サービスという風に、機能別(レイヤー別)に法体系を組み替えてみようというのだ。
総務省は、この法改正によって「従来の縦割りメディアを超えた横断的なビジネスモデルの構築による、新サービス・新事業の創出」が可能になるとみている。
なぜならコンテンツ(従来は通信社、新聞、出版社、映画、番組製作会社、ラジオ、テレビ局が制作)、プラットフォーム(共通の情報伝送、検索手段)、伝送インフラ、伝送サービス、伝送設備(従来は新聞社、放送局、通信会社、ポータルサイトが保有)を垂直的につなぐ統合、連携が原則自由になるからだ。
つまり、法改正後は、通信キャリア、商社、金融機関などが資本を提供し、放送、出版、映画、新聞社などを傘下に置くメディア・コングロマリット形成が可能になる。欧米ではすでに、タイムワーナー、ディズニー、GEなど5~7グループの巨大メディア・コングロマリットが、コンテンツ市場を支配している。
将来のコンテンツ市場の主体は「メディア・コングロマリット」
経済産業省も、こうした動きに呼応して、現在14兆円規模のコンテンツ市場を20兆円に拡大すべく「コンテンツ・グローバル戦略」を構築中だ。2007年9月に出した報告書では将来のコンテンツ市場の主体は、「すべてのコンテンツを最終的なマーケットに送りだすまでを垂直的に統合し、制作するコングロマリット」と想定している。
筆者は、その中核を資本力、技術力もさることながら消費者に一番近い情報端末を提供、運営している通信キャリアが担うと予測している。コンテンツの創出と、発信という企業形態になる新聞社、放送局は、メデイア・コングロマリットの"一子会社"として存続してゆくことになる。
では、日本型メディア・コングロマリットが、いつ、どのような形態で登場するのかについて分析を進めよう。
一方でメディア・コングロマリットが、メディア市場を独占することを危惧する声もある。米国もオバマ政権になり、同一地域で新聞資本が放送局を保有することを規制するクロス・オーナーシップをFCC(米連邦通信委員会)が強化する可能性も取りざたされている。
情報通信法の制定にあたっても、言論の自由の確保に係るメディアコンテンツ規制や、NHKの将来像などについて慎重に検討する必要があることは、言うまでもない。
執筆者プロフィール
河内 孝(かわち たかし)
1944(昭和19)年東京都生まれ。慶應義塾大学法学部卒業。毎日新聞社政治部、ワシントン支局、外信部長、社長室長、常務取締役などを経て2006年に退社。現在、(株)Office Kawachi代表、国際福祉事業団、全国老人福祉施設協議会理事。著述活動の傍ら、慶應義塾大学メディアコミュニケーション研究所、東京福祉大学で講師を務める。著書に「新聞社 破綻したビジネスモデル(新潮新書)」、「YouTube民主主義(マイコミ新書)」がある。