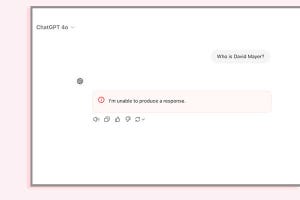「マス排原則」撤廃を提言した竹中懇談会
日本におけるメディア・コングロマリット形成の必要性について提言したのは、2年前、竹中平蔵総務相(当時)の「通信と放送の在り方に関する懇談会」報告書(2006年6月)である。
この中で、これまで民間放送行政に対する指導上の指針となってきた、「マスメディアの集中排除原則」撤廃の必要性が提唱された。
「マス排原則」で知られるこの指導基準(省令)は、テレビ放送が少数の資本に独占されるのを防ぐために、
新聞事業、テレビ事業、ラジオ事業を同一事業者が所有することを原則禁止
1事業者が所有、経営できる放送局は1つまで
また、この事業者が複数の放送局に出資する場合は、(a)地域をまたいで複数の放送局を所有する場合は20%を超えて、(b)同一地域で複数の場合は10%を超えて、株を保有することはできない
というものだ。
1959年に制定されたこの原則は、多チャンネル時代の到来、BS放送の開始などに合わせ何回か、その基準が緩められてきた。
しかし、竹中懇談会の報告書は、メディア・コングロマリット形成のために、放送法の全面的な規制緩和を提唱した。
竹中懇提言を踏襲した今年の放送法改正
まず「現状認識」の項では以下のような判断を示した。
放送事業でも、50年以上前に制定された放送法に基づき、アナログ時代に確立された規制体系や過度の行政指導などにより、事業者が自由な事業展開を行いにくい環境となった結果、欧米のメディア・コングロマリットと比肩しうるような国際競争力のあるメディアが育っていない。
より具体的にはマス排原則の抜本改正が必要、として以下のように提唱した。
同原則が21世紀の日本に必要な"国際的に通用するメディア・コングロマリット"の出現を妨げている面もある。したがって同原則を自由度の高い形で早急に緩和し、IP化・グローバル化にふさわしい原則を確立するべきである。
今年、成立した放送法改正、及びこれに伴う施行規則は、原則的にこの提言を踏襲した。
「産業環境」を整備するとは言えない改正放送法の省令
しかし、実際に在京キー局を経営する立場から見れば自明なのだが、改正放送法が定めている認定持ち株会社の制度は、メディア・コングロマリットの形成に向けた「産業環境」を整備しているとは、とても言えない。その理由は、改正放送法の認定放送持ち株会社に関する省令を見れば一目瞭然だ。
省令の「原則」では、
子会社である地上放送業者の放送対象地域が重複しないこと
子会社である地上放送業者の放送対象地域の数(関東・中京・近畿の広域局は都道府県の数)の合計が12以下であること
2以上のBSデジタルの委託放送事業者を子会社としないこと
などが定められている。
つまり、東京に本社を置く基幹放送局(キー局)の放送対象都府県は7だから、基幹放送局間の合併は不可能ということである。
また地方でも、同一放送圏の放送局を買収することはできないわけだ。これでは、例えばフジテレビとTBSの合併によってJNN(TBS系)とFNN(フジ系)を統合する、といったダイナミックなメディア再編成は、したくてもできない。
デジタル化の設備投資で疲弊する地方零細局を"救済"
「メデイア・コングロマリット形成の推進」をうたいながら、こんな矛盾した省令を出した総務省の真意はどこにあるのか。
総務所担当記者は、「地方局、特に中京、近畿地域の準キー局対策ですよ」と語る。
確かに総務省の電波、放送行政の最優先事項は、2011年7月の地上デジタル放送への移行。アナログテレビからデジタルへの切り替えは、不況の影響もあって、計画スピードを下回っている。この中で特に手を焼いているのは、地方零細局の設備更新だ。
日本の民放ビジネスとは、「主要局を除くと民放は、売り上げが平均70億円程度の中小企業に過ぎない」(池田信夫『電波利権』新潮社)。
そこに1社平均45億円かかる(民放連推定)デジタル移行のための設備投資を強いられているわけだから、地方局の経営は火の車。そこに昨年来の広告収入ダウンというダブルパンチを浴びているわけだ。
だから総務省としては、地方局がデジタル移行をスムーズに行えるような、「環境整備」が緊急課題となった。このための「飴(アメ)」が、電波税からの設備投資への補助金支給と、キー局が経営統合で零細局救済に乗り出すことができるようにする放送法の改正だったわけだ。
デジタル化完成までは"みんな仲良く"護送船団方式
ここでもう一つの問題が持ち上がった。中京、近畿圏の「独立志向の高い」準キー局が、「子会社化、持ち株保有比率に制限をつけないと、東京キー局に飲み込まれてしまう」という懸念を表明し始めたのだ。
準キー局にそっぽを向かれてはデジタル化が進まない。デジタル化完成までは、何としても「"みんな仲良く"護送船団方式」を維持しなくてはならないのだ。
かくて原案にはなかった放送事業子会社を12局以下とする保有制限などが挿入されたわけだ。
総務省は、前述したように2010年に「情報通信法」の国会提出準備を進めている。そして2011年にデジタル移行。その様子を見て放送法に伴う省令が大幅改正されるだろう。
「メディアの本格的再編成は環境の整備が必要」というフジ・メディア・ホールディングスの日枝久会長の発言は、2年半後を見通したものなのだ。
執筆者プロフィール
河内 孝(かわち たかし)
1944(昭和19)年東京都生まれ。慶應義塾大学法学部卒業。毎日新聞社政治部、ワシントン支局、外信部長、社長室長、常務取締役などを経て2006年に退社。現在、(株)Office Kawachi代表、国際福祉事業団、全国老人福祉施設協議会理事。著述活動の傍ら、慶應義塾大学メディアコミュニケーション研究所、東京福祉大学で講師を務める。著書に「新聞社 破綻したビジネスモデル(新潮新書)」、「YouTube民主主義(マイコミ新書)」がある。