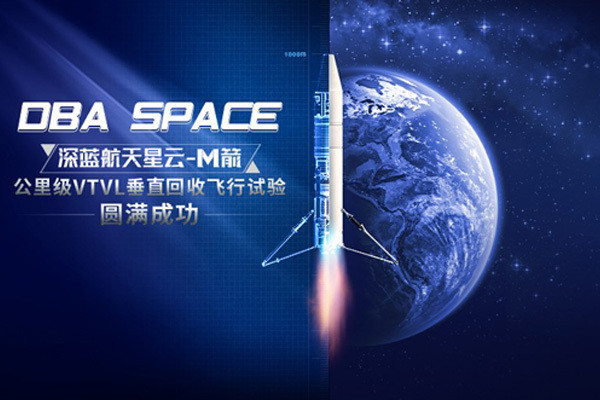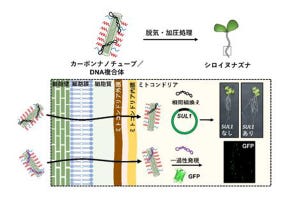理化学研究所は2022年5月23日、磁場による超伝導電流増幅機構を解明したと報じた。この研究結果は、従来の超伝導電流の増幅にトポロジカル相が関与するという議論に終止符を打つ物理学上重要なものであるという。今回はそんな話題について触れたいと思う。
超伝導電流増幅機構とは?
理化学研究所の創発物性科学研究センター量子機能システム研究グループの樽茶清悟グループディレクターらの研究グループは、半導体のナノ細線上に作製したジョセフソン接合に、磁場を加えることで超伝導電流が増幅される効果について、これまで想定されていたトポロジカル相が関与していない、ということを明らかにした。
同研究結果は、科学雑誌「Physical Review Letters」(5月20日号)のEditors' Suggestion(注目論文)に選ばれており、オンライン版に5月19日付で掲載されている。
では、今回理化学研究所の研究グループは、なぜこの研究に従事してきたのだろうか。
実は、これまでこの磁場を印加した状態で超伝導電流が増幅されるという現象は、トポロジカル相やマヨラナ粒子が関与しているのではないかという議論がなされてきたのだが、その根拠となる実験結果には不可解な点があったという。
そこで、理化学研究所の研究グループは、インジウムヒ素(InAs)の半導体ナノ細線に2つの超伝導体アルミニウム薄膜を接合したジョセフソン接合デバイスを作製。そして、接合間を流れる超伝導電流を測定した結果、弱い面直磁場のもとで、超伝導電流が増幅されることを確認。さらに、磁場の向きや接合の電子密度を変えて実験を行い、この増幅が起こる機構を解明したのだ。
もう少し具体的に説明したい。下の測定結果をご覧いただきたい。
アルミニウム電極薄膜の面直方向に10mTの磁場をかけたときに、スイッチング電流が増幅されることが確認されている。加えて、この増幅がゲート電圧、つまり接合の電子密度に依存しないこと、また、面内方向の磁場にも依存しないことも判明している。
磁場の掃引方向(磁場を変化させる方向)と磁場の大きさによって、増幅が起こる10mTより磁場が小さいときのみヒステリシスが現れることも分かったのだ。この結果は、測定温度を変えても同様だという。
では、これから何が言えるのだろうか。
超伝導体は常に外部ノイズにさらされている。このノイズによって励起されている準粒子が存在し、超伝導状態を悪化させている。このような状態に面直方向に磁場を印加すると、超伝導体に磁束が貫いて超伝導状態が壊れる部分、量子渦が発生する。
その量子渦に準粒子が捕捉されることで、超伝導状態が準粒子により見出されなくなり、結果として接合部分付近の温度が下がり、スイッチング電流が増幅するのだ。この機構は、上述の結果の磁場面直成分にのみ依存し、ゲート電圧に依存しない、増幅磁場以下でのみヒステリシスが現れるといった性質と整合しているという。
いかがだっただろうか。今回の機構の解明によって、磁場による超伝導電流の増幅機構にトポロジカル相が関与するという議論に終止符を打つことができた。
これにより、マヨラナ粒子の探索が加速したり、超伝導量子ビットの性能が向上したりする可能性が高まったという。