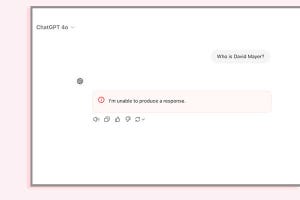梅棹忠夫らが構想した、テレビ、マスコミを核とした「情報社会」のイメージを、今日の実際に近い、高速通信網によってパーソナル・コンピュータが結ばれるという社会像に変えたのは、1980年に出版されたアルビン・トフラーの『第三の波』であった。
「パーソナル」へのこだわりが強かった「アップルII」時代
トフラーがこの書で述べたのは次のような社会像である。
自然環境に恵まれた郊外に建つ家庭の中にある小型のコンピュータが高速の電話回線で結ばれれば、それがエレクトロニクス・コテージ(電子小屋)になる。そうなれば、もうわざわざクルマに乗って会社のあるダウンタウンまで出かける必要はなく、家にいて会社と通信して仕事をこなすことができる。
この「在宅勤務」の概念は、今ではもう誰もが構想し、学者や評論家でなくとも、一般の人が(そんなことになるはずはないよ、という正しい直感とともに)抱く「情報社会」のイメージとして定着している。
だが、トフラーが「在宅勤務」の概念を始めて提案した時代には、まだ誰もそんなことが可能になるとは信じられなかったのだ。とういのも、そのわずか2年前にアップルが(今のマッキントッシュの前世代機である)「アップルII」を発売したばかりであり、当時のパソコン少年たちは、ゲームに夢中になるあまり、それを結んで通信を行うということまでは考えていなかったのだ。
もっとも、彼らの中にはパソコンとともに、ハム(アマチュア無線)に凝っていた少年も少なくなかったし、相互に通信する必要性は感じていた。だが、パソコンによって通信することに対しては、これらのパソコン少年にも、その代表としてアップルを創設したスティーブ・ウォズニアックらにも、当時BASICというパソコン用プログラム言語を発売していたマイクロソフトのビル・ゲイツらにも、拒否感が強かった。
それは、彼らが当時この小型コンピュータを呼ぶ際、ゼロックスのパロアルト研究所の窓際族であったアラン・ケイが発案した名称である「パーソナル・コンピュータ」と呼び、その「パーソナル」という言葉にあくまでこだわっていたからだ。
「マイコン」の伝統が「ファミコン」生む
と言うのも、1970年代までは、IBMの大型電子計算機に知能を持たない端末機を繋げる「TSS」と呼ぶシステムが、世界の政府、行政機関、大企業、大学などを支配していたからだ。今は資本主義の権化のようなビル・ゲイツも、商売上手な不死鳥、スティーブ・ウォズニアックも、当時は、このようなIBMの情報支配体制に反抗するするカウンター・カルチャーの旗手だったのだ。
だから、「通信」というと、パソコンが大型機に結ばれ、その「端末機」として「支配」されてしまうというイメージにとらわれすぎ、パソコン同士が積極的に通信しあう仕組みの構築より、あくまでスタンド・アローンとして「自立と自己情報管理」というパーソナル性にこだわったのだった。
そしてそれが、将来、マイクロソフトがインターネットに乗り遅れてしまう遠因となっていく。最近のヤフーの買収失敗以前に、すでにインターネット閲覧ソフトを、ネットスケープより前に出すことができず、実際はそれを元にしてインターネット・エクスプロラー(IE)を完成せざるをえなかった時点で、ネット時代におけるマイクロソフトの敗退は決まっていた。
また、当時、日本では、アップルIIですら、「パソコン」とは呼ばず、「マイコン」という日本語で呼んでいた。このことは、日本人がパソコン以前から、ゲイツやウォズニアックらが抱いていた「パーソナル」という概念を持たず、それ以前の「マイカー」や「マイホーム」という言葉と同じように、同じ機械を公と私の概念のあいまいな、私事としての会社用コンピュータ、家庭用コンピュータと受けとっていたことを意味している。
そして、それは結果的に悪いことばかりだったのではなく、1980年代初頭にはもう「日本語ワープロ専用機」と、任天堂の「ファミコン」(「ファミリー・コンピュータ」という商品名がそれをよく象徴している)を開発、素晴らしく「日本的に」変容させていくことになる。
アップル間の通信システム「アップルトーク」が誕生
ただ、アップルは、つまりスティーブ・ウォズニアックは、1978年に生まれたばかりのアップルIIを、大型機に結ぶのではなく、当時は同好の志しかもっていなかったアップル同士での通信ができると考えた。
これにより、彼らの間で連絡しあったり、一緒にゲームを楽しんだり、共同作業が可能になると考え、アップル間の通信システムとして「アップルトーク」を提案していた。
当時新聞記者だったアルビン・トフラーは、このアップルのシステムを見て、これが大きく世の中を変えると、ジャーナリストの勘で直感した。トフラーは、これがどんなコンピュータ同士でも、また大型機とも、近いうちには簡単に結べるようになると短絡的に考えた。
また、当時アップルトークは、お互いのデジタル信号を一旦アナログ音に変換して、一般の電話回線で音として伝達しあうというファクシミリに似た「電話カップラー」というデバイスを使用した。
「ストレスなしでの高速通信」を直感したトフラー
通信速度は非常に遅かったが、技術的知識があまりなかったトフラーは、いずれはなんらのストレスを感じないレベルで通信できるようになると楽観した。このトフラーのパソコンと通信に関する技術的かつ文化的な無知が、幸運にも『第三の波』の大胆仮説を生み出すことに貢献した。
彼は、米国中のオフィスと家庭にあるパソコンが、高速の電話回線で相互に結び合うことになれば、先進国の社会に大きな変容、第三の波が起こると考えたのだ。その骨子が、先述した「在宅勤務」の概念であり、そこから当然「オンライン・ショッピング」が起こり、また、給与とそこからの支払いの自動化が可能になり「オンライン・バンキング」になる。
そして、やがては生産者と消費者が直接取引をすることが一般化して、商品の品質や価格もこれまでの「消費者」が決定権を握るような(今日で言えばネット・オークションのようなこと)逆転が起こり、消費者であり生産者である「プロシューマー」が誕生すると予言した。
トフラーの予言を実現させた「情報ハイウェイ構想」
だが、この大胆かつ今日の情報社会の本質を見抜いた予言は、それから10年後に、インターネットとして現実化される1990年代まで「バラ色の未来学」として夢物語に過ぎないとされてきた。この夢物語を蘇らせたのが、「失われた10年」の巻き返し策として、米民主党の大統領候補だったビル・クリントンが大統領選挙時に掲げた「情報ハイウェイ構想」だった。
だが、実際にその構想を作ったのは、クリントンのブレーンで、後に副大統領に就任したアルバート・ゴアだった(昨年度、『不都合な真実』で、ノベール賞を受賞した環境主義のリーダーが、そのときは情報革命のリーダーだったことは記憶しておいてよいだろう)。
そして、クリントン&ゴアの「情報ハイウェイ構想」は、具体的にアメリカのインターネットの一般開放に結びき、これによってアメリカは一挙に、1980年代の不況から脱出し、一時的にせよ再生した。
「IT革命」は『第三の波』のコピー
代わって、1990年初頭に「バブル崩壊」を経験した日本は、その後の「失われた10年」の再生策として、米国の「情報ハイウェイ構想」の翻訳版を唱えた。つまり、森喜朗政権から小泉純一郎政権まで呪文のように唱え続けられた「IT革命」は、アメリカの「情報ハイウェイ構想」の翻訳版であり、そのルーツをたどれば、アルビン・トフラーの『第三の波』にあることが理解されるだろう。
そして、その頃、日本で出版された有象無象の「インターネットで儲かりまっせ」といった類の本は、結果的に、トフラーの作った米国型「情報社会」の誤ったイメージのコピーでしかなかった。そこで作られた「物語」が必ずしも正しくなかったことは、今日のインターネットの世界の現実が示している。また、この「米国の未来」がそのまま、世界の未来でないし、ましてや日本の未来であっていいはずはない。
そもそもトフラーだけでなく、D.ベル、M.マクルーハン、梅棹忠夫ら、「情報社会」の概念を最初につくってきた先人たちが前提にしてきたように、本当に「情報社会」は「工業社会」の後に来るのだろうか? 社会は「段階的」に発展するのだろうか? 次回以降に、考えていきたい。
(敬称略)
執筆者プロフィール
奥野 卓司(おくの たくじ)
1950年京都市生まれ。京都工芸繊維大学大学院修了。学術博士。米国イリノイ大学客員准教授、甲南大学文学部教授など経て、1997年から関西学院大学大学院社会学研究科教授。2008年から国際日本文化研究センター客員教授。専攻は情報人類学。ヒトと動物の関係学会副会長、社団法人私立大学情報教育協会理事。著書に『ジャパンクールと江戸文化』(岩波書店)、『日本発イット革命・・・アジアに広がるジャパンクール』(岩波書店)、『人間・動物・機械・・・テクノアニミズム』(角川新書)など。訳書に『ビル・ゲイツ』(翔泳社)、『ジェスチュア』(筑摩学芸文庫)、『イヌの心がわかる本』(朝日文庫)などがある。