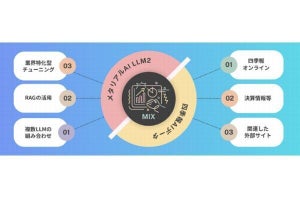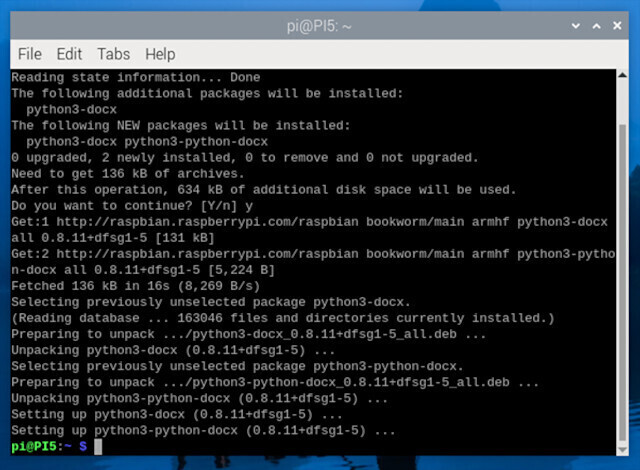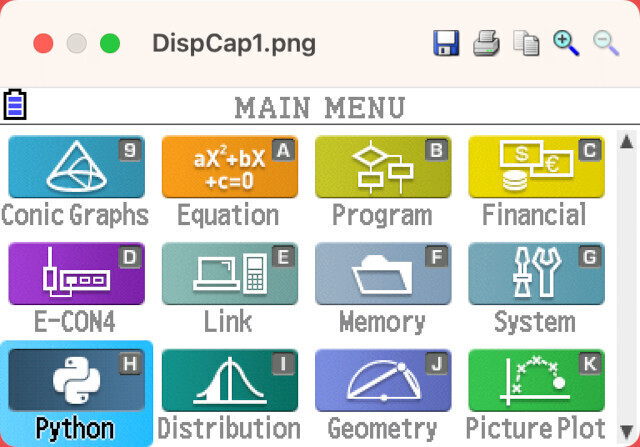日々のビジネスの中で生まれる大量のデータを企業の意思決定や価値創造へ生かす「データ活用」の取り組みは、もはや、全ての企業にとってのミッションと言える。事業環境の変化が加速し続ける中で、組織としての「データ活用能力」をどのように高めていけば良いのだろうか。
今回は、データ活用に不満や課題を抱える企業がその能力を高めていくために有効と思われる「3つのステップ」の中から、データ活用を進めたい組織やデータ活用を推進するデータアンバサダーがイメージすべき未来について解説する。
「リアルタイム性」と「オープン性」はデータ活用の必須要件
第3回で、データ活用のための環境整備を行っていく過程では、活用したいデータの「リアルタイム性」と「オープン性」を可能な限り高めていくよう意識するのが大切だと述べた。この2つは、企業内にデータ活用の風土を築いていく際に極めて重要な意味を持つ。
リアルタイムでデータを見られる環境は、経営者や管理職の意思決定を助けるだけでなく、現場の社員がデータに関心を持つ機会の増加にもつながるはずだ。年単位、四半期単位、月単位など比較的長いタイムスパンで何が起こったのかを振り返る「結果指標」だけではなく、今何が起こっていて、この先どうなりそうなのかを示す「先行指標」が見えるようにする。これにより、経営層だけでなく現場レベルでも、データを見て、考え、アクションを起こし、その結果に基づいて次のアクションを考えるというサイクルを回せるようになる。
また、データのオープン性を高めて、特定のチームだけでなく全社で情報を共有できるような「データの民主化」を進めることで、それを見る社員の事業全体への関心も高まる。各部門がデータを抱え込んでしまっていては、他の事業部門や他のチームが何をやっていて、今どのような状況にあるのかを知ることができない。
一般的に、会社組織では経営者が会社として目指すべき「目標」を立てる。事業部やチーム、そして社員個人が行う仕事は、常にその全社目標の達成に貢献するものであるべきだろう。会社全体や他の事業部に関するデータを社員が見られない環境では、「組織の掲げているゴールへ到達するために自分たちはどのように仕事をすべきか」を意識できない。
反対に、自分たちの仕事が組織の目標にどれだけ貢献しているのかが可視化されていれば、社員の中には、自発的により貢献度が高くなるような仕事の仕方を考えてチャレンジする人も現れてくるだろう。
チャレンジを通じた小さな成功体験の積み重ねが、さらなるデータ活用へのモチベーションとなる。これが、組織としての「データ活用能力」が高まりつつある状態だ。
経営者がイメージすべき「データ活用能力向上」のビジョンは、データのリアルタイム化とオープン化を通じてデータに対する社員の好奇心を刺激し、部門の壁を越えたコラボレーションや、現場レベルでの「小さな意思決定」が同時多発的に起こるような環境作りである。この際にマネジメント層が意識しなければならないのは、現場に対する適切な「権限委譲」だ。
データを見て何かに気づき、「アクションを取りたい」と思った社員がいても、「必要な権限がないので実行できない」という状況が繰り返されれば、次第にデータへの関心は薄れていく。社内に生まれ始めたデータ活用の芽を育てていくためにも、小さな意思決定からのアクションを促す仕組み作りは不可欠だ。こうした文化の醸成や仕組み作りにおいて中心的な役割を果たすのが、前回に重要性を強調した「データアンバサダー」である。
「ペイン」が解消された後の「ビジョン」を共有する
企業が「データ活用能力」の向上を目指すにあたり、最終的に「こうありたい」と望むビジョンを共有しておくことには価値がある。このビジョンは、組織に属する全ての人の目線を合わせ、目標に向かって取り組みを進めていくためのモチベーションとなる。
第2回ではデータ活用のステップ1として、経営者、事業部門、IT部門がそれぞれ抱える「ペイン」(痛み)の例を紹介した。では、データ活用能力が高まった組織でこれらのペインが解消された先に、どのようなビジョンを描けるだろうか。
「経営者」のビジョン:データアンバサダーを推進役として、社内にデータ活用の文化が根付きつつある。経営指標に関するデータはスマートフォンでリアルタイムに確認できるようになり、不測の状況にも以前より早く気付いて指示を出せるようになった。また、常にダッシュボードで各事業部の状況を把握できるため、定例会議では単なる状況報告をやめて、より多くの時間を価値の高い議論に割けるようになった。
「事業部門」のビジョン:自分たちのビジネスの状況をリアルタイムに把握できるようになったことに加えて、現場の権限が増したことで自らの判断によるアクションが以前よりも取りやすくなった。毎日、始業時に最新データのチェックから業務を始める習慣ができつつある。また、所属チームだけでなく他のチームの状況や経営指標に関わるデータが見られるようになり、自分たちの仕事が経営目標に対してどのように貢献しているのかを実感できるようになった。メンバーの中には、社内にあるデータの一覧や利用できる社外のデータを調べながら、それらを組み合わせた新たな指標や、新規ビジネスのアイデアをデータアンバサダーに相談する人も出始めている。
「IT部門」のビジョン:データ活用の取り組みは、データアンバサダーから業務部門のニーズを聞きながら対応を進めている。要求に対応するだけではなく、技術的な視点で新しいデータの収集や、活用方法を含むシステム企画を、IT部門から経営や事業部に対して提案できる体制ができてきた。既存システムの保守運用が重要な業務であることは変わらないが、それだけに忙殺されるのではなく、会社に対してビジネス的に競争力の高いシステムの企画および開発を戦略的に提案できる、「守り」と「攻め」を兼ね備えたIT組織への進化が視野に入りつつある。
これらのビジョンを「夢物語」「絵に描いた餅」として否定するのは、データ活用に向けた取り組みを実際に始める決断に比べれば、極めて簡単だろう。しかし、動き出さなかった組織と「理想」としてのビジョンを共有して最初のステップを登り始めた組織との間に生じる差は、数年、早ければ数カ月で決定的となるはずだ。
まとめ
コロナ禍において、日本企業のデジタル変革へのスピードは加速している。あらゆる業種、業界のビジネスモデルが、デジタル技術の力で否応なく変化する中、DX(デジタルトランスフォーメーション)の取り組みを着実に進めて高い成果を生み出すには、本連載で述べた3つのステップが役立つだろう。
ITスキルのレベルを問わず誰もがデータにアクセスできる環境で、データを簡単に共有し、データ活用を迅速にビジネス成果につなげていく。このデータ活用の力を通じて、日本企業のデジタル変革が進むことを期待している。