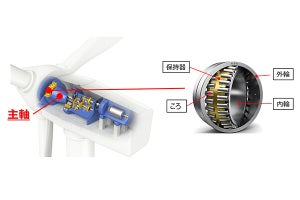結婚式や出産など、めでたいお祝いごとには必ず登場する「祝儀袋」。紅白の色遣いが伝統的ですが、近年はその他の色・かたちも増え、デザインのバリエーションもとても豊富になりました。
お祝いのきもちを自分らしいデザインで表せるようになった反面、贈る相手によってどういったデザインのものを選んだらいいのか、また贈る際のマナーなどについて、迷ってしまうのもまた事実。そこで、祝儀袋をはじめとした紙製品を長年販売している文具メーカー・マルアイの担当者に、祝儀袋に関する豆知識やマナー面について聞いてみました。
今回は、そもそも「祝儀袋」がなぜ使われるようになったのか、その起源に迫ります。
――まずは「祝儀袋」の起源について、ご説明いただけますか?
祝儀袋(金封、のし袋)の起源は、「贈答」という文化の起源までさかのぼり、日本古来の神道において、神様を鎮めるため奉納する物品を包んだことが発祥です。神様へのお供え物として農作物や魚介類を束ねるため、和紙で包み、上からいくつかの紙縒り(こより)を束ねたもので結ぶ形をとっていたことに由来にするそうです。
その文化が、中世~江戸時代における宮中の儀式や武家社会の礼儀作法によって、また、全国の各地域それぞれの風土・文化によって、少しずつ変化しながら独自の作法として、贈答品を包む文化や祝儀袋にかけられている水引の文化に形成されていきました。
――祝儀袋には「熨斗」がついていますが、これはどんな意味があるのですか?
まず、祝儀袋が一般的に熨斗(のし)袋とも言われます。そして熨斗は、本来「のしあわび」といいます。鮑(あわび)は現在も高級食材として扱われますが、古代から貴重な食物であり、その肉を薄くはぎ、引き延ばし干したものが「のしあわび」です。伊勢神宮などの祭祀に供えられたり、中世には武家の出陣や帰陣の祝儀、そのほか吉事の贈り物に添えられました。
熨斗をつけるのは、その贈り物がけがれていないしるしとされ、鮑の香気をもっていろいろなけがれや邪悪を防ぎ退けるという考えに基づくものと考えれています。また、一般には、大事な食料としての「のしあわび」を贈り物に添えることは「いざというときには、こののしあわびを食べて生き延びてください」という相手への切実な思いやりの意味が込められているも言われています。ちなみに、熨斗は、鳥、魚、鰹節など、魚介類を贈るときにはつけません。また、弔いごとでは、なまぐさは断ちますので熨斗はつけません。
――そのほか、祝儀袋を構成する素材やデザインについて、教えていただけますか?
熨斗のほか、伝統的な「贈答」の文化にとって、和紙の存在も重要です。例えば、四季の庭に咲く花を和紙に包んで贈るなど、日常生活での包み紙として使用します。また、お祝いごとや弔いにおいて、お金や物を和紙に包んで贈る際には、中身や相手によってそれぞれ決まった折り方で美しく包み上げるなど、古くから日本人の生活に欠かせないものでした。
また、贈り物の包みに用いる用紙は、古くから奉書、また檀紙とされていますが、紙包みは相手の手に直接渡るものですから、しっかりした立派なものであるとともに、変色したり、しわや手垢がついているもの、一度使って折り目がついているものなどは、絶対に使ってはならないとされていたので、今日の和紙製法の品質は非常に高いものになりました。昨年、「日本の手漉(てすき)和紙技術」がユネスコの無形文化遺産に登録されたことも記憶に新しいですが、和紙は世代を超えた伝統的な技に支えられて、今日も「贈答」文化の中では欠かせないものになっています。
次回は、祝儀袋を「贈る」際に知っておきたい知識をお送りします。