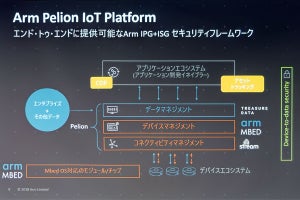MPUに新属性追加
MPUでは新たにPXN(Privileged eXecute Never)という属性が追加された。これは名前の通り「特権レベルでは実行できない」で、この属性が付いているメモリ領域のコードは、非特権レベルでプロセッサが動いている時だけ実行可能で、特権レベルで動いている場合はAccess Violationを発生させて処理が中断する。これは例えば、攻撃者が非特権レベルで侵入コードをシステムに潜り込ませ、これを特権レベルで実行させようとした時などに効果的であるとする。
デバッグ拡張
Armv8.1-Mでは、従来からあるDWT(Data Watchpoint and Trace)機能が拡張され、Cortex-Aシリーズとよく似たPMUに進化した。こちらでは、従来の機能に加えてさらにキャッシュのHit/Missなどの情報も取得できるようになっている。ただDWTとPMUは物理的には同じハードウェアなので、両者を同時に使う事は出来ないとしている。またData Watchpointではbit maskが利用できるようになったほか、カウンタ付きのBreakpointも新たに追加された。
RAS機能
Armv8.1-MのRAS機能はCortex-Aほどではないが、結構充実している。具体的には
- ESB(Error Synchronization Barrier)命令を追加
- Error Reporting Registerが17種類追加された
- Bus InterfaceにParity/ECCチェックが追加されたほか、Poison Signalingが追加された
となっている。
ちょっと逆順になるが、Poison Signalingというのは何か? というと、例えばプロセッサのデータキャッシュなどにDouble bit Errorが発生したとする。ECCでもこれは修正しきれないので、そうなるとそのCache Lineは不正(Poisoned)になる。
この状態でCache Flashが発生した場合には、Poisoned Dataがそのままメモリに書き戻されることになる訳だが、Poison Signalingがあると、この際にプロセッサからメモリシステムに対してそのCache LineがPoisonedであることを通知できる。ちなみにこの段階ではまだFaultは発生しない。
ただそののち、再びその内容が再びキャッシュにロードされることになったら、再びPoison Signalingを利用してPoisonedであることをメモリからプロセッサに通知する。この段階で、初めてFaultが発生する形だ。
ちなみにマルチプロセッサシステムなどで、あるプロセッサがPoisoned Dataをメモリに戻した後で、別のプロセッサが同じメモリアドレスに上書きした場合は、Poisonedが消える形になるのでFaultは発生しない。そもそもそんな事があっていいのか? という疑問は無くも無いが、RASの考え方としては正しい。
Poisoned Signaling以外にも様々なエラー要因が考慮可能であり、こうした様々なエラー要因を最大56個までError Reporting Registerはハンドリング可能であり、そしてエラーが発生した場合にこれをハンドリングするための命令がESBというわけだ。
(次回は2月25日に掲載します)